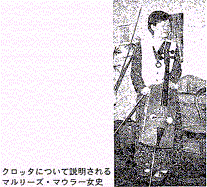3.マルリーズ・マウラー女史の音楽療法
「人智学の音楽療法で大切なことは言葉を使用しないこと。すべての問題を音楽で解決する」といわれるマウラー女史をスイスのベルンにある自宅に訪ねた。マウラー女史は15年間音楽療法をされ,ルーカス・クリニックの初代音楽療法士として6年間勤務された。まず最初に,チェロの原型であるクロッタという楽器を紹介された。これは昔ケルト族が使用していたもので,今世紀の初めに発見されて以来,作り始められた。チェロは習わないと弾けないが,クロッタは初めての人にも弾け,これを弾くと弾いている本人により響いてきて,自分の中に深く入っていくことができるので,音楽療法にたいへん適した楽器である。ライアーもよく使うとのことである。
音にはそれ自体に特色があって色あいや感じが違い,聴いたときに違う感情がわき起こる。C〜Aという音のパターンは心が開く癒しの音だといっておられた。また,8〜9世紀頃は,心臓の鼓動と息の流れを音楽に取り入れていて,生理学的に体内からおこるリズムに則ったメロディー(例えばグレゴリアン・チャント)が人間を内的な世界に導いて癒しとなる。心臓は同じように打っていても,速度にわずかな変化がある。現在はタクトで進めていくので,ハートビートとは合わなくなるとの話もあったが,これは揺らぎを大切にするということだろう。
がんにかかると上腹部だけで呼吸していて細胞は十分に呼吸しなくなるので,下腹部まで解放されるあくびは大切だといわれ,口を開けてあくびのようにしながら体を起こすデモンストレーションをされた。あくびで空気が身体全体に入り,体中が浄化されるということであるが,これはやりすぎないように,2回までで止めるようにとの注意があった。
マウラー女史はつづけて,「死にゆく患者さんとの音楽療法は,患者さんに精神世界のあることを伝えるという高い目標があり,音と同様に,人間にも死ぬと戻って行くところがあるということを生の音楽を通して認識させていきます。自分を超えたものからの導きでメロディーが生まれます。テープやCDなどの再生音は本来の音ではない死んだ音であり,必要のないもの。人生も音も動きが大切なのです」と話された。
「音を目で見ることはできません。楽器をバラバラにしても音は見つかりません。それは人間を解剖しても,精神がどこにあるのかわからないのと同じです。音というものは,音楽を奏でるまでは別の世界にいて,奏でた瞬間この世にきます。そしてすぐにまた別の世界に戻ってしまいます。それと同じように,人間は誕生するまでは違った世界にいましたが,誕生と共にこの世にきました。亡くなると,音と同じように別の世界に戻っていくのです。そうしたことをしゃべらないで音だけで行うので難しいのです」とも話された。その患者さんがどの宗教に属しているかを知り,その世界からその人の大切なものを見つけることが大切であること,死ぬ前の大事な時はバッハのメロディーをよく使い,バッハが演奏される空間からは神へと通ずるものがあり,パラダイスを感じられるとも話された。
私たちも小型のライアーで簡単な即興演奏をした。