しかし、家族援助論では、これからますます複雑化する家族形態のなかで、どのような家族か、家族の機能がどれくらい果たされているかを明らかにして看護介入する必要性を学んだ。緩和ケアにおいて家族の一人を亡くすという予期的悲嘆に対して悲しみを十分に表出することの大切さ、遺族ケアの重要性も学んだ。病気という危機状況を通して家族的成長を援助できるような関わりを目指したいと思う。
事前レポートの結論
今回の研修に臨むに当たり、事前レポートとして2つのターミナル期の外泊や一時退院が困難だった事例から、家族との関わりや社会資源の活用法など、あるいは医師との葛藤などについて、どうすれば良かったのか答が欲しいと思っていた。講義や施設実習を通して自分自身に導き出した答は、外泊や退院の是非が問題ではなく、医療者と患者・家族との関係の中にこそ答が潜んでいるという結論だった。つまり、患者・家族の真の思いを引き出すようなコミュニケーションや、最期までしっかりと支えていく保証を実感させることができなかったのではないか。医療チームの多くが「帰ろうと思えば帰れたのに」という悔いを残したのは外泊や退院に対してではなく、精一杯関われなかったことに対する後悔ではなかっただろうか。患者の思いがはっきり表出されていれば、必要な社会資源も具体的にすることができたのではないだろうか。今後の教訓として次に活かしたいと思っている。
まとめ
今回緩和ケアナース養成講座を受講する機会に恵まれ、人間誰も避けて通ることのできない『死』に至るプロセスを尊厳を持って関わる緩和医療について基礎から実践までを学ぶことができた。『死』を考えることは『生』を考えることであると改めて実感した。その人らしい『生命の質』に多少の差はあっても、誰もが求めているのは暖かい人間の心ではないだろうか。チャプレンさんの「医療者は最後の癒しの器となれる特権を持った職業である」という言葉を胸に刻んでおきたい。
最後にこの研修での学びを自己の施設でどのように還元できるかを考えてみた。
? 緩和ケア病棟についてまだ具体化されていないので、一般病棟でのホスピスマインドで研修の成果を活用したい。
?伝達講習や病棟学習会、院内ターミナル研究会などで、この研修で学んだ知識を共有したい。
?県内の目的を同じくするグループや個人と情報交換や学習会を通して、ネットワークをつくって協力し合いたい。
?この研修で知り合えた仲間と情報交換し、緩和ケアについてさらに自己研鑽したい。
以上のことを気持ちを引き締めて頑張ろうと思っている。
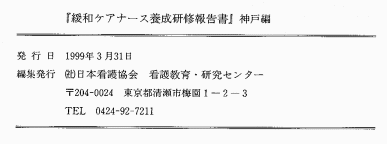
前ページ 目次へ