どこにでもあるスミレの類とアリとの関係がそうです。スミレは、種子をアリに運んでもらいます。
図4の一番手前のアリが抱えているのが、スミレの種子です。その種子の右の端のところに、小さなこぶみたいなものがくっついていますが、それはタンパク質の多い栄養分に富んだ部分で、種子がその後育っていくためには必要でなく、アリのためにスミレが用意した餌なんです。アリは種子を巣に持って帰ってその部分だけを食べ、種子の本体は巣のまわりへ捨てます。その結果スミレはアリに種子の散布をしてもらい、そのための代償をちゃんと用意している。アリとスミレは一生一緒に住んでいるわけではなく、アリは種子ができた時だけしかスミレを利用しない。しかし、こういう関係も広い意味での「共生」だというわけです。
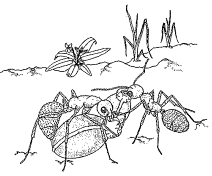
図4 スミレの種子を運ぶアリ。BEATTIE(1985)による。
実は自然界というものは、生物と生物の間のこういう共生関係のかたまりみたいなものなんです。それを、生物学では生態系(エコシステム)と呼びます。生態系は、たくさんの生物が一地域に一緒に住んで作っているシステムですが、その中では、植物、動物、微生物、それから空気・水・土などの無機環境を一つ、そういうものすべての間に非常に複雑なこういう共生関係、相互依存関係があって、それが全休を一つのシステムヘと結びつけているのです。従って、一つの種類だけが単独で生きている生物は極めて少ない。普通の生物はみんな、他の生物といろいろな関係で結びついたシステムの中で生きている。このことが非常に大事な点てす。それが、後でお話しすることと関係してくるわけです。
人と人、人と自然の共生とは
さて「共生」というのは、もともとはこういう意味で使われた言葉なんですが、それなら人間と自然との間にその意昧での関係が成立しうるかというと、これはちょっと無理なようです。というのは、自然のシステム、生態系は、人間が地球上に誕生してくる前にすでにできあがっていたシステムでありまして、人間は初めはその一部分として出現してきたけれども、やがてそのシステムからはみ出した独自の文明システムを作って暮らしています。人間は自然がなければ生きていけない、自然の恩恵をこうむって生活しているわけですが、自然にとっては人間はいわば邪魔者であって、いなくてもいい存在である。だから、今述べたような意味での共生関係は、自然と人間との間には成り立たないのです。
「自然と人間との共生」という場合には、生物学でいう共生とは少し違う意味か含まれているはずです。「共生」という言葉は、現在は、人間と人間の間の関係、あるいは人間の集団と集団との間の関係、にも拡張して使われるようになっています。
私が知っている限りでは、そういう意味で「共生」という言葉を以前から使っておられるのは、建築家の黒川紀章さんで、『共生の思想』(1986、1991)という本を出しておられます。その中で黒川さんか言っておられることを私流に解釈したのを、お手元の要旨の中に書いておきました。要するに、人間と人間、あるいは人間の集団と集団の間で、相手の文化や伝統などを理解しあい、相互に十分尊重して、その存続を認める。お互いの間では、批判もするし交流もする。そうすることによって、より次元の高い共存の道を求めていく。そういう意味で使われているようです。
異民族間や宗教のちがう集団間の対立が非常に多く、それが紛争の大きな原因になっているわけですが、そういう文化・伝統の違う人たちの間の争いをどのようにして解決していくかという時に、この思想は非常に有力な考え方になるだろうと思います。この考え方で最も重要なのは、相手の生き方を十分理解し、尊重するということ、それか一つです。もう一つは、相手の文化・伝統がそのままで存続ずることを認めること。