ストレスと人間との関係でいえば、その人にとって良いストレスと悪いストレスがある。
したがって、ストレスと付き合う基本としては、適度のストレスとなるように、また悪いストレスは良いストレスに変えることが出来るようにしていくことになる。
いずれにしても、人生上での困難な状況を自己発展の機会ととらえて、積極的に利用していきたいものである。
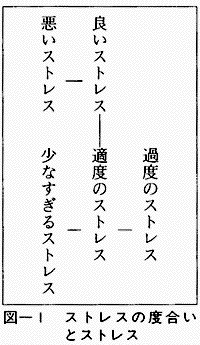
(3) ストレス対策の構図
基本になるのは、個人が毎日の生活の中で、健康を保つための健康習慣を維持してゆくことである。例えば、「?@朝起きる時間、夜眠る時間を規則的にする。?A1日3回の食事を栄養のバランスを考えて食べる。?B体力に合った適度の運動を毎日続ける。?Cくよくよせずに、努めて朗らかな心を保つ。」などの規律のある健康習慣を保つことが重要である。このことは生活習慣病とよばれている、いわゆる成人病の予防にも役立つことになる。
日常の健康保持を目的とした生活習慣を基本として、その上に2つの事柄によりストレス対策が成り立っている。1つは、ストレスを解消する技術を個人が持つことである。例とえば、旅行・運動・趣味などによる気分転換のほかに、各種のリラクゼーション法を習ったり、また、ヨーガ・気功法・心理技術などにより、自己理解を深めるといったことなどである。
他にはサポートシステムとして、困ったときに相談することのできる人間関係を、ふだんから心掛けてつくっておくことである。上司・同僚・友人・家族といった人間関係を大切にし、お互いに支えあえることができるようにしておく。また職場も組織として、相談窓口を設けたり、ストレス解消の技術を習う機会を提供したりするなどの、メンタルヘルス対策が必要であろう。
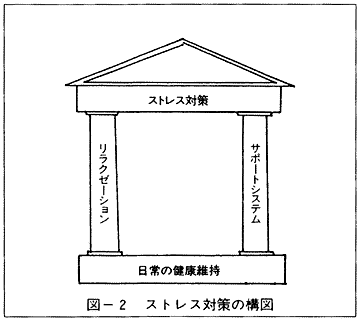
(4) 職場でのストレス解消法
ア 職場でみられるストレス要因
ストレス関連要因のあり方によって、職場内・職場外・個人的要因に分けることができる。職場内要因で重要なものは仕事の質や量、職業適性、それに職場の人間関係によるものであろう。昇格・昇任・異動などが期待に反していたり、適性を欠いたものであったりすると、そのことがストレス要因となり、職場不適応に関連することもある。
職場外の個人的要因には、家庭問題・金銭問題・病気などがストレスとなり、職場生活に影響することが多くみられる。
イ 職場管理者の役割
職場のストレスを解消し心の健康を保つために、管理者の役割は重要である。職場の問題に対して、日頃から暖かい目で職員を見守り、変化に素早く対応して、問題を解決しようという積極的態度が望まれる。部下職員から相談を持ちかけられたら、じっくりと相手の悩みを聞く。解決法を与えられなくても、相手の心を聞くつもりで耳を傾けることが大切であろう。
職場内でのストレス関連要因を解消し、職場外の要因をも考慮に入れて職員を助け、
前ページ 目次へ 次ページ