・ 出来るかぎり、下の方まで波反射板を持っていきたい。
6) 空気室模型は水槽の出来るだけ後ろの方に持っていった方がよい。
7) 水槽の幅は何mあるか。
・ 約3mである。
8) 水槽の底へはボルト締めするのか。
・ おもりで転倒を防止する。
9) 水槽の床はコンクリートか。
・ コンクリートである。
10) 千葉港や平潟港は干満の差が大きい。実験項目に干満を考慮するという項目はないようだが。
・ 昭和60年頃の「灯標等へ利用する波力発電システムの研究開発」の研究をしたとき、空気室前面のカーテンウォールの深さによる効率の差は少なかった、という実験結果が出ている。
但し委員より干満差を考慮した方が良いというアドバイスがあれば、実験項目に入れたい。
・ 港研の実験データでは効率が異なっていた。
・ 干満差の影響を考慮して、実験する方向で検討したい。
11) 実験はいつ頃から開始するか。
・ 今のところ、8月を想定している。
・ 千葉の36通り、平潟の135通りを全部実施すると、実験に約1週間かかる。
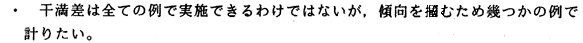
12) 平潟港の周期測定の9通りは、少し多いと思われる。
・ 1秒おきでも、だいたいの傾向はつかめると思われる。
13) 空気室の圧力を測ることは考慮していないか。
・ 今までの調査研究では、圧力は内部水位の変化から計算していたが、圧力を測る方向で検討する。
14) 圧力を測る場合は、模型の周期が1〜2秒と短いので、応答性に気をつけた方が良い。
15) 不規則波を実験に入れることはできないか。
・ いくつかのポイントを選んで、比較の意味で実験に取り入れたい。
16) 不規則波のスペクトルは、造波機の能力の関係で決めた方が良い。
17) どういった波高計を使う予定か。
・ 超音波、ないしレーザー式を想定している。
・ 超音波は広がる欠点があり、レーザー式は海面ではなく海底を測る場合もある。
・ レーザー式は下に発泡スチロールを置き反射板を貼ることを考えている。
18) 今回の実験は発電装置の台数で開口比を変えているが、千葉港の場合も平潟港の場合も発電装置の大きさは同じなのか。
・ 同じである。
19) 回流水槽概略図の安全ネットの下側にある点線はなにか。