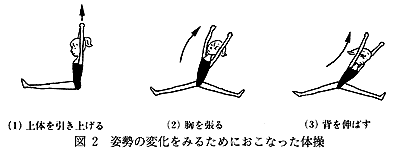
c:胸引腹引型(凹凹型)
d:胸引腹出型(凹凸型)
の4種類に検者の主観で分類した。背・腰部については、前述のStaffel(姿勢研究所12)、山口ら18)より引用)やWiles(姿勢研究所12)、山口ら18)より引用)の直立位での脊柱形状による分類方法を用いず、今回注目している長座位のアラインメントの変化をよく反映するように、側方から見た型により、
A:反りのある型(凹型)
B:平らな型(平型)
C:丸みの浅い型(小凸型)
D:丸みの深い型(大凸型)
の4種類に検者の主観で分類した。
これら、胸・腹部の型や背・腰部の型に違いがあるかないかを体操前後で比較し、さらにリラックス姿勢」と「意識姿勢」についての比較をおこなった。
「よい」姿勢の判定基準について、猪飼3)は『耳孔、肩甲関節の中心、股関節の中心、膝関節の前面が真直に縦に並んで、これが足底の中心付近に落ちる』としている。姿勢研究所12)は『骨格とそれを支えている筋肉群のバランスがよくとれている状態。1.背筋が伸びている 2.うなじが伸び、あごがひけている 3.胸を張っている 4.両肩は後ろに引かれている 5.全身の筋肉に緊張がなく、リラックスしている 6.バランスがよく、安定している 7.横からみたとき、重心が耳たぶ、肩、股関節、膝関節を通り、足のくるぶしの少し前に落ちている 8.脊柱はゆるいS字状のカーブを描いているなど』としている。このことを踏まえて今回の分類では、この条件をなるべく多く満たしている胸・腹部ではa(凸凹)型がもっとも「よく」、d(凹凸)型がもっとも「よくない」、b型(凸凸)、C(凹凹)型はその中間であるとした。背・腰部ではA(凹)型、B(平)型、C(小凹)型、D(大凸)型の順に「よい」姿勢であると考えた。立位体前屈(図1−?D)と後屈(図1−?E)、長座体前屈(図1−?I)については、体操によるその前・後屈度の変化を知るため、第7頸椎の床からの高さを体操前後で比較した。
研究結果および考察
1.直立姿勢、長座姿勢における胸・腹部、背・腰部の型について
各対象者の直立位、長座位での「リラックス姿勢」と「意識姿勢」における体操前後の胸・腹部、背・腰部の型を判定し、その割合を図3〜6に示した。年代による大きな違いはみられなかった。直立位の背・腰部の型を除くすべての場合(直立位の胸・腹部、長座位の胸・腹部と背・腰部)において、体操後「意識姿勢」、体操前「意識姿勢」、体操後「リラックス姿勢」、体操前「リラックス姿勢」の順により「よい」姿勢の人数が多かった。姿勢研究所12)では「よい」姿勢の基準のひとつとしてリラックスしているという条件をあげているが、今回の結果では全体的に「リラックス姿勢」より「意識姿勢」のほうが「よい」姿勢であり、この条件を満たすことは難しいと思われる。
直立位、胸・腹部の型の例として写真1(若年者)のように、体操前「リラックス姿勢」では胸を引き、腹を出している(今回の分類ではもっともはくない」としている)d(凹凸)型、体操後「リラックス姿勢」では胸も腹も引いているc(凹凹)型、