潮高は基本水準面からの高さで海図に記載されている水深にプラスすると高低潮時の水深を知ることが出来る。潮流の転流時を調べて,出港日時を調整すると順潮に乗ることが出来る。
天測暦
本来は天文航法をするのに便利な様に,各天体の位置を記載した暦であるが,この中で日出没・月出没時間を知る為「港別日出没時表」「月出没時表」を利用する。始めて訪れる港への入港は,なるべく日中となる様計画する。暦の使用法がむつかしければ水路部が監修した「海のカレンダー」が便利で親切である。説明も平易であるから誰でも利用出来る。又日出没月出没にかかわらず,容易に入手出来る理科年表等で日頃から,潮汐とか天体の運動等に関し,知識を深めておくとずっと海に対する近親感も湧いてきて航海計画も建て安くなるものである。
灯台表第一巻
全国の航路標識外を収録してあるが,地理的光達距離や,航海中に物標の正横距離等を求めるとき利用する。P・Bは相対に眼高が低いのでH・Eが2m位の船は海図に書いてある光達距離から-1.7浬の補正が必要である。海上で見える距離は地球表面の曲率が関係するので,本船から視水平までの距離は
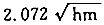
初めて見た物標までの距離は

である。hは眼高Hは物標の高さなので覚えておいてほい。さて次に環境関連の資料として,どの様な資料があるかについて概説する。我々は,中緯度地方に住み四季の変化が激しい季節風帯に居る訳であるから,海に出るからには一刻も気が抜けないのは当然で,特にP・Bは運動性能が優れている反面環境に対して極めて弱い点に留意していなくてはならない。
天気図
航海計画を建てるについて,出港日を予定したらその数日前から同時刻の天気図を順番に集めて,天気の動向や,流れ等を低気圧や前線の推移を中心に調べる。気圧の変化や等圧線の混み具合の外に,天気を読むには雲の走り等にも注意する。天気は普通西側から変化して来るから西の天気は特に留意する。テレビ・ラジオをよく聴取し,電話気象情報の入手にも努める。
?地方局番+177番
?東京湾海上交通センター
TEL 0468-44-4521
テレフォンサービス気象現況
?石廊埼航路標識事務所
TEL 055-86-5-0010
海潮流情報
潮流は潮汐の干満の為に起る海水の流れで,上潮流(低潮から高潮まで)と,下潮流は流れる方向が反対となる。浅い海面では,流速が速くなる。海流の成因は,海水密度の差や風で潮汐とは関係無く,海洋を移動する流れで,黒潮や親潮等が有名である。黒潮は御前埼沖に冷水塊があると,流路が北にかたよって流れる。海上では,海流や其の分枝流潮流や沿岸流が混じり合って複雑な流れ方をする。