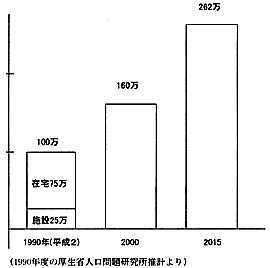
図1 日本における痴呆性老人の推移
には、262万人までに増加すると推計されています(図1)。
在宅ケアと施設ケアのうえでの対策
在宅または施設での痴呆性老人への対策には以下のものが準備されつつあります。
A. 在宅ケア対策
家族を支援する体制づくりの強化
1. ホームヘルパー・サービス
2. デイサービス、デイケア・センター・サービス
3. 老人保健施設でのショートステイ事業
4. 日常生活用具の給付、または貸与、特殊ベッドなど
B. 施設対策
1. 特別養護老人ホームに入所、これについては痴呆性老人介護加算(入所者の3分の1以上である施設の場合)があります。
2. 老人保健施設内痴呆性老人性両用病棟に入所(中・高度)
3. デイケア施設への受け入れ
4. 痴呆性老人ケアハウス(個人、公的施設)の活用
痴呆性老人への接触の仕方
さてここで、私は在宅ケアにおける痴呆性老人への接し方について私の考えを述べ、施設内でもこの在宅ケアでの心の通ったケアがなされることを希望するものです。このことに関しては、軽度、中等度、重度によってそれぞれの対応を考えなければなりませんが、たとえ重度でもその老人を1人の人格体として、欠陥はもつが、人間としては尊厳ある人格をもつ老人として、残された人格の面を接点として、交わりをすべきです。
在宅ケア対象としての軽度痴呆性老人へのとり組み:痴呆症はこれを軽度、中等度、重度と分類されますが、そのなかの軽度と分類された患者のなかに、私は部分的痴呆や一時的痴呆があることを特記します。また、重度においても部分的痴呆として重度を示す者があることを特記したいのです。一般には医療従事者や老人介護に携わる人は、痴呆患者という呼び名をするとき、それは痴呆になってしまっている患者または痴呆になりつつある患者というように、その患者の全体像に痴呆の着物を着させてしまう傾向のあることに気がつかなければなりません。俗に「まだら痴呆」という言葉があります。たとえば、数を計算するとか、時間や場所や、また目の前にいる人を認識することについても、間違いがある患者でも、その他の面では、ある程度の認知が可能です。これは痴呆性老人に音楽療法や音楽的レクリエーション作業を試みてみるとよく分かることです。昔覚えた歌曲を音程をはずさず正確に歌え、適切な言葉が出なかった老人が歌詞を日本語やときには外国語で正確に歌うことさえ可能な例があるのです。
痴呆患者との接触上の問題
徘徊老人の介護のなかで、身体を清潔に保つことや徘徊の世話などは最も難しいことです。
徘徊する患者は、夜となく、昼となく、暴力を用いても戸外に脱出しようという意図が強くあります。このような老人に対して、老人と相性のよい介護人は上手に徘徊を抑制したり、短時間の徘徊ですませることに成功できることがあります。
これは老人と介護人または家族のある特定の人との間に、心と心とのタッチがある場合にのみ、不思議なよい人間関係が生まれ、それで問題を解決できるのです。どのように老人とタッチするか、老人に残された感性にどのようにすれば上手にタッチできるのかの術、これこそ介護のアートといえましょう。
犬の好きな人間、その人間を犬がどのようにして見分けるのか、それは動物と人との双方の直感力がそれを可能にし、そのことで両者間に心のコミュニケーションが