労働時間の一層の短縮、家事の外部化、介護や保育の社会化などによって、21世紀初頭にかけてむしろ増加していくと推測される。
実際に、全国の昭和61年、平成3年、平成8年の15歳以上の人について、この10年間の生活時間の推移をみると、男性の1次活動時間は、昭和61年が10時間20分、平成3年が10時間19分と、ほぼ横ばいで推移したが、平成8年は10時間26分と増加している。
また、2次活動時間は、昭和61年の7時間41分から、平成3年が7時間33分、平成8年は7時間15分と大きく減少している。
3次活動時間は、2次活動時間とは逆に、昭和61年の5時間59分から、平成3年が6時間8分、平成8年が6時間19分と大きく増加している。
一方、女子の1次活動時間は、昭和61年と平成3年がともに10時間30分と横ばいで推移したが、平成8年は10時間39分と増加している。
2次活動時間は、昭和61年の7時間54分から、平成3年が7時間46分、平成8年が7時間21分と大きく減少している。
また、3次活動時間は、2次活動時間とは逆に、昭和61年の5時間36分から、平成3年が5時間44分、平成8年が6時間と大きく増加している(図表3-1-36)。
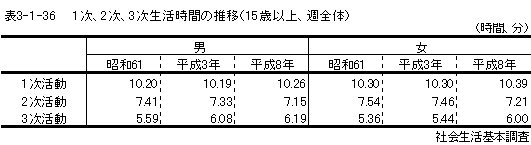
例えば高齢期の生涯学習について、横浜市民の年代別に積極的要望(複数回答)の度合いをみると、現在の高齢者では、高齢期の生涯学習に対する要望は複数回答総計で約200%となっているが、現在の20歳台から50歳台では、平均約250%に達しており、次世代の高齢者層での、高齢期の生涯学習に対する意識の高まりが示されている(図表3-1-37)。