
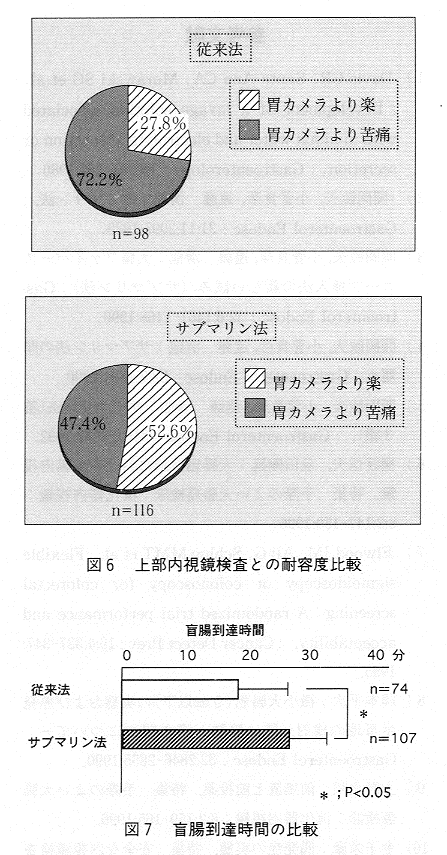
2)同様に検査の安全性を高めるために前投薬は鎮痛剤のみとする。スライディング・チューブは極力使用しない。
3)時間よりも苦痛の少ない検査を優先しサブマリン法を導入する。
4)検査回数を減らすため精査時ポリペクトミーの適応のあるものはその場で切除し、可能なかぎり精査=治療として患者の利便性の要求に応える。
5)ポリペクトミー当日から翌日までは入院経過観察とするが、急変時来院可能であれば入院期間は一泊を原則とする。
上野は大腸癌検診における“内視鏡への要求”として安全性、簡便性、受容性を強調している。無論、これらはあくまでCFの必要条件であって、診断治療を的確に行うという十分条件を満たすことが本来の目的である。改善の基本にあったのは、高齢者が安全に苦痛なく受けることのできる大腸検査体制を確立することにあった。従来当院での被験者の平均年齢は71.1歳、最高82歳と高齢者が大半を占めていた。高齢者での問題点は腸管が脆弱であること、前投薬の耐谷量が低いこと、腸管の空気による過伸展で迷走神経反射を起こしやすいこと等があげられる。加えて慢性便秘に悩むものが多くまた腸管の長い症例が多いことから前処置が不十分なことが少なくない。そのため洗腸剤の内服もやや多めの3,000〜4,000mlで行ってきた。特に65歳以上の超高齢者の場合腸管が硬化していることが多く、苦痛を訴える頻度や穿孔などの偶発症の頻度が増大すると言われている。
今回の改善点のなかの最大の点はサブマリン法の導入にあった。サブマリン法は1989年関岡らによって提案されたCF手技であって、腸管内に水を注入しつつ内視鏡を挿入していく方法である。あたかも潜水艦が管腔内を進むかのようであることから関岡らが銘々したものである。この方法は表4に示した長所/短所を有している。本法は検査時間が通常より長くなること、水注入操作の繁雑さといった点から多数症例のスクリーニングを目的とする施設では馴染まない方法である。そのため検査処理効率が問題となる施設では必ずしも広く普及していない。サブマリン法の導入により、明らかに患者の苦痛の亡訴えは減少した。さらに補助具であるsliding tubeは有用な反面、その使用には腸管穿孔のリスクを伴
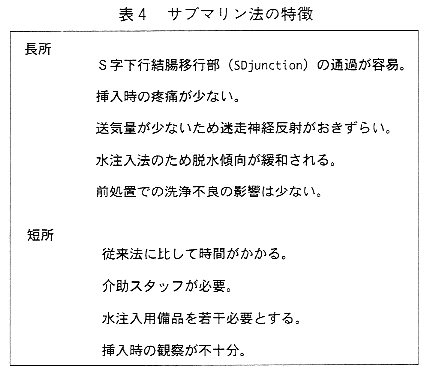
前ページ 目次へ 次ページ
|

|