
|
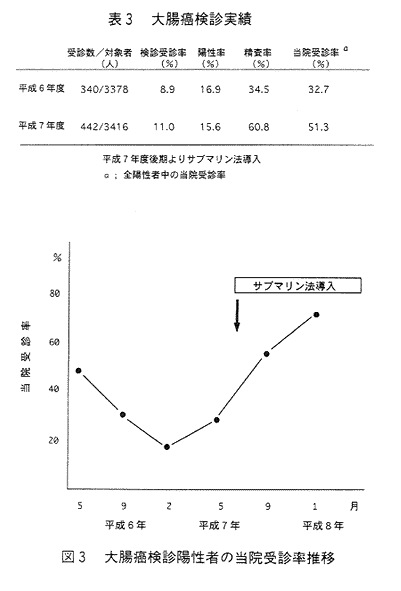
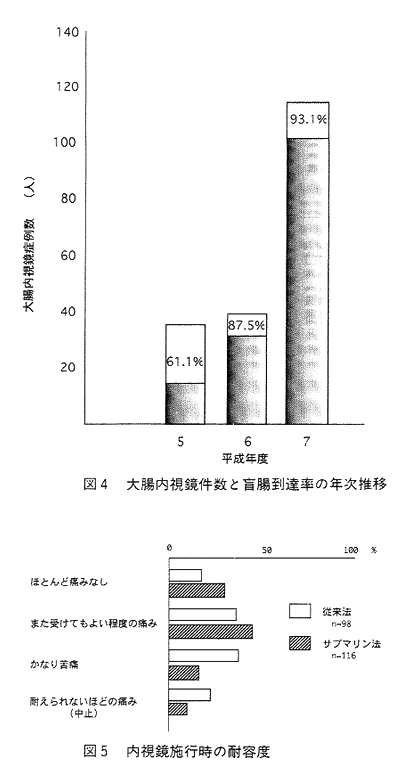
低さは一般的に問題となっている。樋渡らによれば全国集計で60%台であり、当町では平成6年度で30%台という低率であった。EdwoodらはCF経験者の受容度について詳細に検討を加えておりその中で、被験者の52%が前処置時何らかの異常を自覚し、S字結腸のみの精査で87%、鎮静剤投与下の全大腸検査であっても42%が挿入時不快感を訴えたと報告している。我々の結果も同様であり、大腸検査そのものに対する恐れや不安が、CF経験者では2度目以降の精査をためらわせ、伝え聞いたCF未経験者の受診動向も強く呪縛していると考えられた。僻地においてはこれ以外に都市部の大病院指向がもう一方にある。
しかし、当町は道東の東端に位置し近隣の都市部と最短で60kmないし160kmの距離による隔絶があり、他医で精査受診を希望したとしても距離の問題が受診者の精査意欲をさらに低下させていると思われる。大腸精査受診率を向上させるためには、苦痛が少なく、安全で質の高い精査をしかも地元の僻地自治休でも提供できるようにする事が必要である。
一方、当院の従来の体制では、ベット占有率に余裕があること、年間CF件数が少なく検査設備、スタッフ、時間といった医療資源(resource)の面でも比較的余裕があったこと、被験者の多くが病院の近隣に在住しておりポリープ切除後の急変に対しても即応できるといった、大都市病院では望めぬ僻地病院ならではの利点もあった。大きさ5mm以下の微小大腸癌が注目を浴びている今日、質の高い検査と治療を兼ねた利便性を被験者に提供していくことが要求されている。
以上から我々は当院の利点を生かしつつ大腸精査卒向上のため次のような改善を行った。
1)対象者は高齢者が多いことから前処置の患者負担を減らすため、PEG内服量を従来の3,000mlから2,000mlへ減量する。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|