
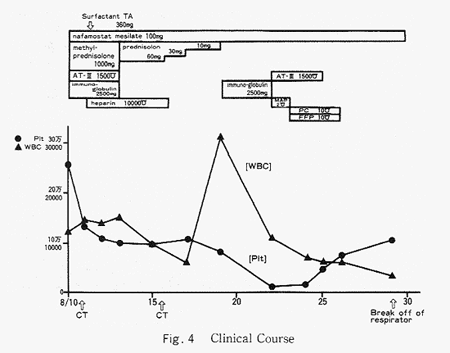
考察
切迫溺水におけるような大量の水や吐物の気道内誤嚥はともに肺胞・毛細血管膜障害を惹起し、ARDSを発症させる。本症例は切迫溺水の状態で搬入され、人工呼吸管理・高濃度酸素療法にもかかわらず、高度の肺内右左シャントによる低酸素血症の持続と特徴的な胸部X線写真、CT所見よりARDSと診断した。
ARDSの原因として傷害因子の作用後time lagを経て肺胞・毛細血管膜傷害が起こり、血管より血液蛋白成分や細胞成分が肺胞腔に進入し、肺サーファクタントが不活性化される州ことが考えられる。その結果、RDSにみられるような肺胞の虚脱、無気肺領域の換気−血流比の不均衡、肺内右左シャントの増人により、高度の低酸素血症がもたらされる。また、肺胞II型細胞が死滅し肺サーファクタントの産生と再生−再分泌機構が障害され、悪循環に陥る。
RDSに対する肺サーファクタント補充療法はすでに碓立されており、ARDSに対してもその有効性が検討されている。わが国でもS-TAを用いた全国共同試験が実施されつつあるが、RDSと異なり、ARDSの基礎疾患は多様であるため、臨床応用は未だ少ない。しかだって個々の治験例の蓄積は将米ARDSに対するS-TA補充療法の大規模研究をデザインする上に重要である。
ARDSの急性期は呼吸管理によって少なくとも1週間接続する。本症例では新生児RDSに対するS-TA補充療法の報告3)にみられるような急性効果を証明する経時的計測値の収集は比較的乏しいが、a/APO2はS-TA補充後12時間で0.34、18時間で0.60と上昇していることによりARDSにみられる高度の右左シャントがS-TA補充後に確実に減少していることを示す。その結果、FlO2はS-TA補充後の12時間で0.6以下となり、その後数時間で0.4、さらに36時間で0.3と減少できた。同時に、胸部X線写真、CT所見の改菩がみられていることから、これらの改善はARDSの自然経過とは考え難く、S-TA補充療法の効果によるものと考える。
また、これらの急性効果も重要ではあるが、ARDSが記載されて20年を経て、さらに最近の呼吸管理の進歩にもかかわらず、いまだ極めて高い死亡率(50%)を維持している事実に鑑み、本症例が救命されていることは重要である。
しかし、いまだARDSに対するS-TAの補充量に関し一定の見解が得られてはいない。RDSで投与されているS-TAの量は100mg?kg-1(リン脂質)で、この量は成熟新生児の肺サーファクタントプールサイズに相当する。もし、ARDSで同量を換算すると、50kgの成人体重ではS-TAの必要量は5g
前ページ 目次へ 次ページ
|

|