
名(62.5%)であった。初回は3月23日であったが、前夜からの季節はずれ積雪量が70cmにもおよぶ大雪で道路の除雪もおいつかず、このため市街地以外からの参加者が少なくなった可能性がある。5回の講習すべてに出席した者は6名であった。土曜日の午前中に連続5回出席することは相当の努力を要すると思われる。次回からは1回の時間を多少長くしても回数を減らして行う必要があると考えられた。
B.クラス方式の問題点
今回はクラス方式を採用したために、個人のレベルおよび問題にあわせた細かな個別指導は困難であった。しかし、総論的に包括呼吸リハがどういうものであるかを理解してもらう目的ではクラス方式は有用と思われた。今後は不足した点を個別指導で補うようにする必要があると考えられた。
C.受講者の理解度
受講者は1名を除きすべて65歳以上であり、4名は80歳以上であった。このような高齢者に講習内容がどの程度理解されるか心配であった。しかし、質問表による理解度の評価では、61%から81%と正解率が改善し理解度は良好と考えられた。
D.専門医のいない地域小規模病院での包括呼吸リハとりくみの問題
われわれの病院には呼吸器専門医はいない。今回は都老人医療センター呼吸器科のスタッフにより包括呼吸リハの実施方法を学んだ。その後チーム・メンバーは各自学習し理解に努めたが、学習時間が足りず理解不十分なまま講習会にのぞんだことも一部のメンバーから指摘された。しかし、十分ではない点があったとしても、全体としては受講者には好評であり、講習内容もほぼ理解されたと考えられた。今後経験を重ねてゆけばよりよいものができるという期待がもたれる。はじめに呼吸器専門医による実施方法に関する伝授があれば、専門医のいない地域の小規模病院でも包括呼吸リハ指導は十分に可能と思われた。同時に、勤務時間外に学習をし講習を実施するなどチーム・メンバーの積極的な姿勢と意欲が必要である。
E.今後の課題
受講者が包括呼吸リハを学んでも自ら実践しなければ意味がない。最終の評価会では呼吸法を実践し呼吸が楽になったという受講者の声もきかれた。包括呼吸リハが受講者の症状やQOLの改菩にむすびつくかは今後の検討が必要である。受講者の症状や日常生活活動度について講習前評価をおこなったが、数か月から半年後に再び同じ評価を行い、これらがどのように改善したか検討する予定である。また、病状や療養方法の改善が入院回
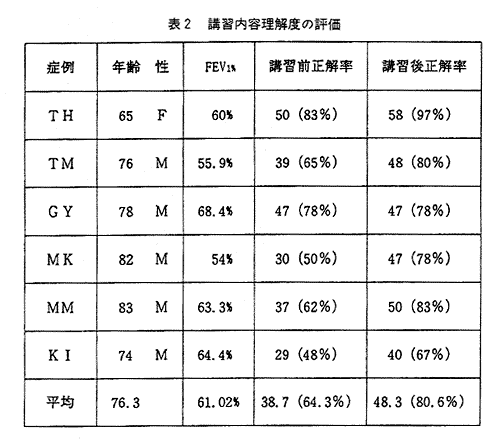
前ページ 目次へ 次ページ
|

|