
が高くなっていたが、その割合は各ADL関連項目により大きく異なり、明らかな階層性が認められた。すなわち、老年期の最も早期から有障害者の割合が高いのが知的能動性で、以下、手段的ADL、対外交渉の順で続き、咀嚼会話と身体的ADLは、老年期後期になるまで障害を持つものの割合は低かった。
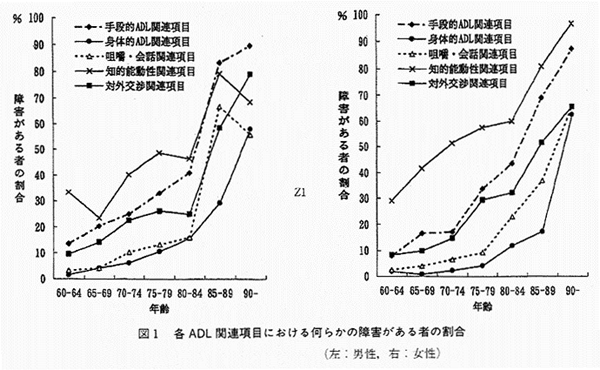
3.対象の属性事項と社会生活機能との関連性
年齢、性、配偶者の有無、同居状況とADLとの相関を一元配置分散分析を用いて検討した(表4)。年齢および同居状況と社会生活機能との間には有意の相関を認めたが、性および配偶者の有無との間には有意の相関を認めなかった。各要因の組み合わせによる二次の交互作用では、年齢との組み合わせで有意の相互作用を認めた。
各ADL関連項目の障害に対する属性事項(年齢、性、配偶者の有無、同居状況)の影響の強さを、ロジスティック回帰分析を用いて解析した。各属性事項の各ADL関連項目の障害に対する影響を、障害のOdds(障害のOdds=障害を有する者の割合÷障害のない者の割合)を求め、両者の比(Odds比または優比)を用いて表したものが表5である。女性であることの優比は、手段的ADLで0.66、知的能動性では1.30と相反する傾向を認めた。年齢が5歳増すことの優比は、いずれのADL項目においても有意で、1.5前後の高い値を示した。配偶者がいることの優比は、0.6前後と低く、手段的ADLで有意とならなかったものの、対外交渉。知的能動性では有意であった。夜間または終日同居人がいることの優比は。手段的ADLで、2.0前後の有意に高い値を示したが、他のADL項目では1.03〜1.31を示し、有意ではなかった。
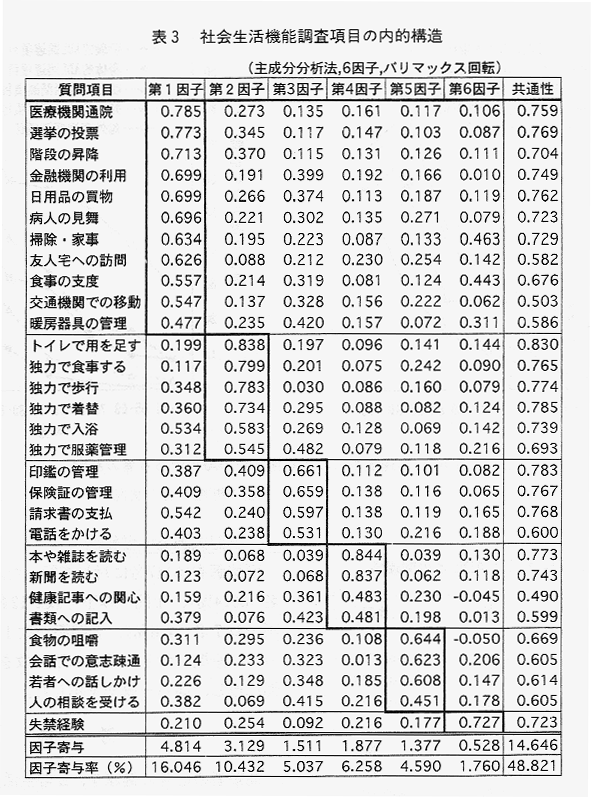
前ページ 目次へ 次ページ
|

|