
|
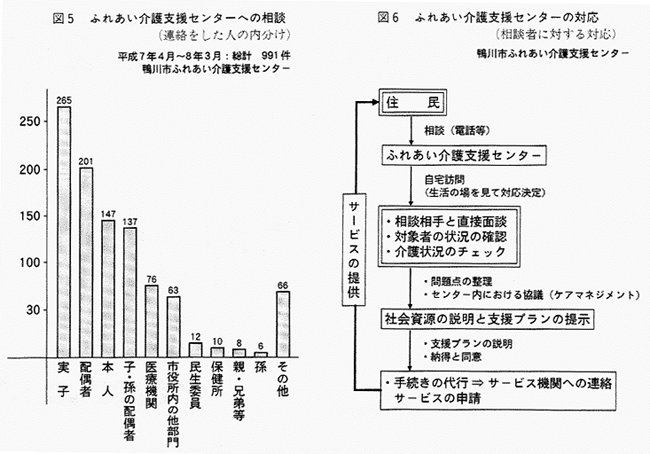
のニーズも次々と掘り起こされて来た為、これらを元にした行政側並びに私達ケアワーカーの今後目指すべき方向が示されて来た。
さて、平成7年4月にふれあい介護支援センターの開設が決まり、担当職員が任命された後に私達と担当職員が頻回に集い話し合いの機会を持ったが、その際に私が特に強調した事は、"住民からの電話相談には必ず相手の家庭を訪問して問題の解決を図ろう"という事である。必ず相談相手の生活の場を見た上で相手の立場に立ってその家族には何が必要かを考えて選択メニューを提示し、その上でその家族に選んでもらう。そして必要な申請は可能な限り慣れた支援センターの職員が代行し、可及的速やかにサービスの利用が出来る様配慮する。この様な心構えと体制作りがこれからの超高齢社会の地域作りには最も大切な事ではなかろうかと考える(図6)。
以上の様に、悩みを持った住民の家には行政側が出向いて行って直接話し合い、可能な社会資源の活用を提示し、その中から利用者に選択してもらい、活用の便を図る。勿論申請書類を書く煩わしさは一切無し。そして住民は自分の家で希望したサービスを即座に利用出来る。役所に出向く苦労は一切無し。従来とは逆に動くのは行政側である。以上の様なコンセンサスが行政側にも住民側にも急速に浸透して来た為にふれあい介護支援センターは開設後僅か1年間の実績にも拘わらず相談件数が急速に増加して来ているものと思われる。
3.ここで改めて私達が10年間の在宅医療への係わりからの経験から市側に行政主導の在宅介護支援センターの設置を強く主張した理由をまとめてみた。
先ず高齢社会においてはすべての人が何らかの福祉サービスを必要とする事に成る。又それと同時に保健サービスと医療サービスも同等にニーズは高く、住民に近い関係になければならない。この様な理由からもこの3者の境目を取り除き、住民に判り易く利用し易い総合相談窓口が各地域に存在すべきである。
そしてその窓口として最適な組織が"在宅介護支援センター"ではなかろうかという発想であった。そして将来は相談内容をセンターに持ち帰って検討するのでは無く、家庭で相談を聞きながら直ちに生活者の悩みを解決出来る様にする為に支援センターそのものにヘルパー組織と訪問介護ステーションを組み込んでしまってはどうかと提案した。当初市上層部の反発が大きかった事は既述したとおりであるが、しかし最終的には市長の英断でこの様な総合相談窓ロ機能を果し得る在宅介護支援センター
前ページ 目次へ 次ページ
|

|