
います。大学病院と違って患者さんが「あの薬は飲みにくい」とか、「自分の血圧は160位がよくて、下げすぎると調子が悪い」などとはっきり自分の意見を言ってくれるのも助かります。他のスタッフは長年村に住んでいる人たちですから、患者の家族構成、仕事の内容など、色々と患者の背景を教えてくれます。私と患者さんの話が筒抜けなのはプライバシー保護の面では問題なのかもしれませんが、「この方は心配症ですから、あまり強く言わないで下さい」と書いたメモを受付の人がそっと渡してくれたりするのです。このような患者の背景は、大切なデータとして私以外の医師が見てもわかるようにカルテの最初にまとめて残すようにしています。
生活の中の医を求めて
往診ではより患者の実際の生活が見えます。毎週往診に行く老夫婦があります。子供がそばにいなくて寂しいのか、とにかく往診を楽しみにしていて、15分ほど愚痴を聞いているうちに少しずつ元気になってくるのがわかります。大腿骨骨折で歩けないけれどもニコニコと編物をするおばあさんや、脳卒中による片マヒであっても、油絵を描き続けているおじいさんなど、こちらが励まされる人も何人かいます。診療所実習を選択した佐賀医大6年生の学生を往診に連れていくのですが、大学病院での病気の患者しか見ていなかった学生が、このように生き生きと生活している患者さんの姿を見る意義は大きいようです。
毎月の高齢者サービス調整会議は、役場の福祉係、医師、保健婦、看護婦、介護支援センター、ホームヘルプサービス、デイケア、社会福祉協議会の人間が一緒にケースの情報交換をする大切な時間です。全員揃っても約10人の小さな会ですが、みんなが現場にいる人たちなので話は具体的ですし、その連携は抜群です。ヘルパーさんから足のむくみを指摘されて早期治療できたり、昼間介護する人のいない寝たきり患者さんのケアを毎日交替で誰かが見に行くような日程調整をしたりと、色々な取り組みをしています。
診療所の建物も老朽化し、建て替えが必要な時期です。保健事業が市町村に下りてくる平成11年を目標に、上記の調整会議のメンバーを中心に予防からリハビリまでができるような総合施設『三瀬村保健医療福祉センター』を作りたい、これが今私の一番の夢です。なんとか村民の皆さんと一緒に実現させたいと願っています。
(編者注)教育医療Vol.22No.1より
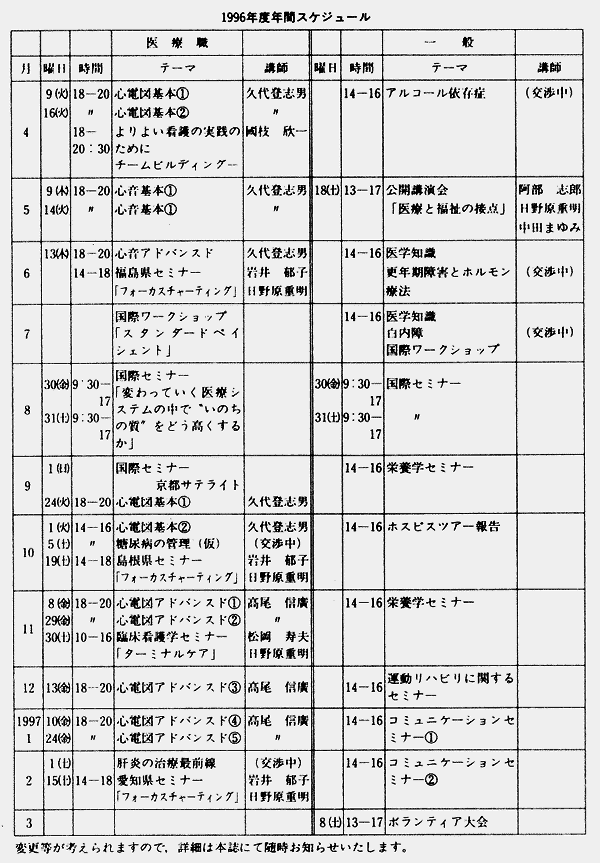
前ページ 目次へ 次ページ
|

|