図V−1 農家、農業労働力の長期的動向
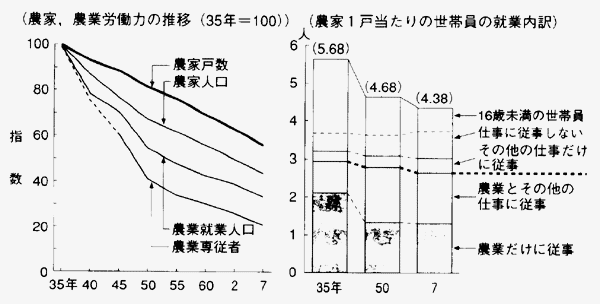
資料:農林水産省「農林業センサス」
沖:1)総農家べースで算出したものである。
2)農業就業人11とは、農業に主として従事した者をいう。
3)農業専従者とは年間の農業従事日数が150口以上の者をいう。
4)35年40年の農業専従者は、基幹的農業従事者の変化率を用いて算出した。
5)「農会1戸当たりの世帯員の就業内訳」の7年は、15歳以上の世帯員についてみたものである。
6)( )内の数値は、農家1戸当たりの世帯員数である。
表V−1全就業人口に占める農業就業人口の割合
| |
日本 |
アメリカ |
フランス |
ドイツ |
イギリス |
| 1961年 |
31.8 |
6.4 |
21.3 |
14.4 |
3.9 |
| 1975年 |
15.4 |
3.9 |
11.1 |
7.8 |
2.7 |
| 1994年 |
5.2 |
2.0 |
4.3 |
4.0 |
1.8 |
| 資料:FAO“Production Yearbook” |
| 注:農業就業人口には林業、狩猟業、水産業を含む。 |
(2)高齢化が進む農業労働力
(「平成7年度版農業白書」)
(高齢化が進む農業労働力)
まず、農業就業人口に占める65歳以上の者の割合(高齢者比率)から、農業労働力の高齢化の進行状況をみると、昭和40年には13%であったが、平成7年には46%と半数近くになっている(図V−2)。このような急速な高齢化の背景としては、農業労働力の他産業への流出が若年層中心であったこと、農業機械の普及により高齢まで農作業が可能になったこと、平均寿命が延びたこと、少子化が進んだこと等があげられる。ちなみに、新たに農業就業人口となる若年層は激減しており、例えば、新規学卒就農者(農家子弟の新規学卒就業者のなかで、主に自営農業に従事した者)は、39年に6万6千人であったのが、30年後の6年には2千人と約30分の1になっている。
高齢化の進行を他産業と比べてみると、非農林業全体の高齢者比率は、定年制がある雇用者の割合が高いことから、5%程度とほぼ横ばいで推移している。また、定年制等によるリタイアが少ない自営業主で
前ページ 目次へ 次ページ