[12]氷盤群と構造物の干渉に対する氷盤形状の影響
豊田真、中山秀邦、山ロー、林昌杢、松沢孝俊、加藤洋治(東大)、加藤一行、足立明弥(IHI)
構造物と流氷群の衝突に対する水盤形状の影響を調査するため、ポリプロピレン製の模擬矩形水盤、模擬円形水盤及びそれらの種々の混合比での氷群中での構造物曳引実験を行った。円形氷盤の量が増えると氷盤の衝突による力が横方向にも伝わるようになるため、氷盤の横方向移動量が増え、構造物への氷荷重が減少した(下図左)。計算においても力の伝わる方向を表すパラメータ(C−angle)を新たに導入して、良好な結果を得た(下図右)。
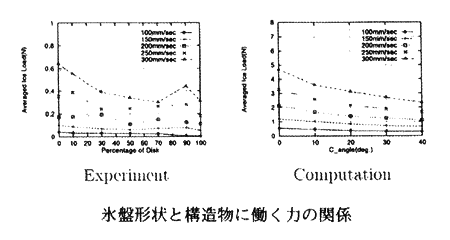
[13]多方向不規則波中を航行する船舶の応答の実験的時間領域解析法
(第1報)−線形応答解析法について−
前田久明(東大生研)、林昌奎(東大生研)、奥山淳一郎(コマツ)、武田信玄(東大生研)
時間領域で船体の応答を解析する方法としてC.C.法とC.I.法が知られている。本論文ではこの2手法により多方向不規則波中での船体応答を数値計算しその結果を比較検討した。その結果、C.C.法、C.I.法ともに十分な精度で時間領域応答解析を行うことができたが、C.C.法はアルゴリズムは簡単であるが多方向不親則波中での解析ではC.I.法がより実用的であることがわかった。
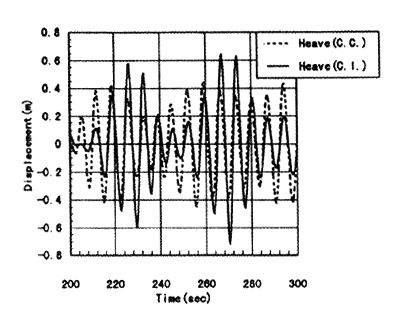
[14]大洋を航行する船舶の甲板冠水の予測
万順涛(九大大院)、新開明二(九大)
乾舷の大きさに第一義的に支配される甲板冠水の発生特性について、その発生持統時間推定の観点から調査を行った。提案した甲板冠水の平均発生持続時間推定法によれば、甲板冠水の長期発生時間割合を推定する際に、短期超過確率をパラメータとして含む必要がないために、甲板冠水率の解釈が容易であり、本推定法による甲板冠水の予測が船舶設計の立場から便利であることを確認した。また、実船の航海状態に近いcaseを想定して、5自由度の船体運動計算に基づく数値計算を行ってこの推定法の汎用性と有効性を確認した。
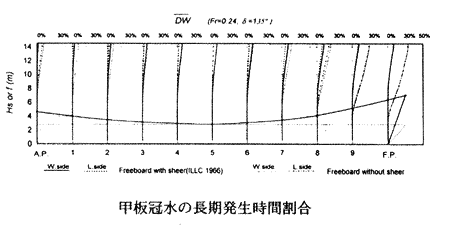
[15]波のリアルタイムシミュレーション法の開発(英文)
野原勉、山本郁夫、松浦正己(三菱重工)
本研究はリアルタイムで多方向波発生が可能となるシステムハードウェア構成と高速演算法を開発し、波シミュレータおよび造波装置に適用し、効果を検証した。本方法はダブルサメーション法ベ―スの波合成法、エネルギー等分割法による非繰り返しスペクトル演算法の開発と独自のシステム構成により高精度、高速演算を可能とした。本方法は造波装置の波発生ロジックに活用され、さらに数値シミュレータとしての用途も大きい。
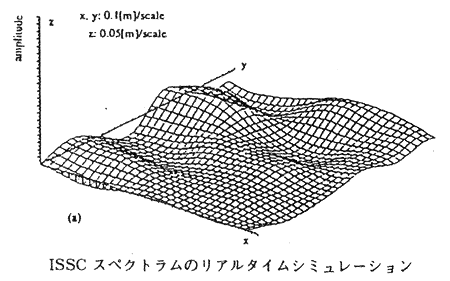
前ページ 目次へ 次ページ