これらは締結される部品の設計上の条件によって主として選択される。すなわちシリンダヘッドの場合はBまたはC、連接棒大端ボルトの場合はAまたはB、主軸受冠ボルトの場合はBまたはCが多く用いられる。いずれの場合も締付け状態においてボルト側には引張力が接手側には圧縮力がかかる。これを模擬化すると補・2図のように表現することができる。

補・2図
ここでAのばねはボルトの弾性をあらわしておりこの場合引張りばねとなる。またBは接手側の弾性をあらわし、この場合は圧縮ばねとなる。
この場合の作用力Fと撓み量δの関係は

で与えられる。
ここでAはボルトの断面積または接手側の締結によって影響を受ける等価断面積、Fはボルトの締付力、Eはボルトまたは接手側の材料の縦弾性係数(ヤング率)でボルト側は殆どの場合、鉄鋼製であるのでこの場合炭素鋼、合金鋼などその化学成分および熱処理の如何に拘わらずEの値はほぼ一定で約21,000?f/mm2(206Gpa)である。それに対して接手側の材質は鋼の場合や鋳鉄などさまざまで鋳鉄の場合も普通鋳鉄(片状黒鉛鋳鉄または鼠鋳鉄)、ミーハナイト鋳鉄、バミキュラ鋳鉄、ノジュラ鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄またはダクタイル鋳鉄)などによって9,000〜18,000?f/mm2(88〜176Gpa)と大幅に変化する。
| ボルト側のバネ常数は | 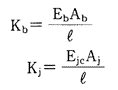 |
| 接手側のバネ常数は |
ここでボルト側の断面積はAb=πdb^2/4で与えられるが相手側の等価断面積はボルト側のように単純にはいかず、等価円筒または等価円錐などにおきかえて計算する。等価円筒におきかえた一例としてVD12230による接手側の等価円筒の計算式を示す。(記号は補・2図参照)
前ページ 目次へ 次ページ