
3.ビオトープの組織化の段階
わゆる“食う一食われる(食物連鎖)の関係だけではなく、直接・間接に表2に示したような多面的な関係をもち、それに支えられて生存してきたのである。別の言い方をすれば、全ての野生生物はその場所で必然的に形成される“生物群集”の一員としてのみ、生存できるのである。
したがって絶滅が心配されるような動植物の保護が問題になる場合でも、単にその生物を、一見類似している環境をもつ場所に移植あるいは捕獲して移転させればよいというのではなく、本来の生息環境の質的・量的な特性と、昔から共存してきた生物群集についての多面的な調査と考察をおこなった上で、対応策を決めなくてはならない。それは、生態学的にもかなり高度な(総合的な)知識と経験を必要とすることなので、是非その分野の専門家の参加が必要である。
しかし、出発が特定生物種期待型の事業でも、目的とする生物が復活し、その生息が長く続くようであれば、当然多様性に富んだ生息環境が発達する。山口市の一の坂川の治水事業に関連しておこなわれたゲンジボタルの生息環境保全の事業は、都市河川でおこなわれたこの種の事業のすぐれた事例といえるだろう。
なお、このタイプのビオトープ整備に関連して、野生生物の“餌付け”についてふれておく必要がある。
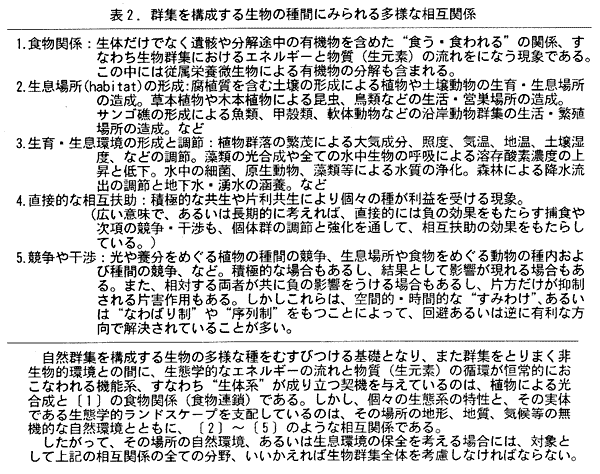
前ページ 目次へ 次ページ
|

|