|
5.3 津波の影響評価
図5-2(1)〜5-2(10)と 図5-3(1)〜5-3(10)は、それぞれ実験CaseAと実験CaseBの各地点における津波波高の時間変化を示したものである。図の横軸の時間は津波を発生させたときを0時として示し、縦軸の津波波高変化はレンジ基準を±160cmとして赤線で示した。なおレンジ基準内に収まらない大きな津波が襲来した地点では、レンジを変更して青線で示した。
CaseAの津波波高をみると、一番大きいのが紀伊水道にある測定地点であり、次いで大阪湾、播磨灘へと続き、内海に入るほど波高は減衰している。海域毎に津波波高の特徴が読み取れる。紀伊水道では、数時間に渡って大きな津波が続き、波長は短い。ゲート操作により津波を与えた紀伊水道の地点では110cm強の津波が発生し、その津波が内海側に伝播し和歌山県の御坊の地点では400cm近くの大きな津波となり、鳴門海峡側の福良浦の地点でも260cm強の津波が測定されている。大阪湾地点での津波は、発生から約1時間後に到達し、洲本で約60cm、大阪で約90cmの津波波高となっている。播磨灘地点での津波は、発生から約1.5時間後に到達し、津波波高は30〜60cm程度である。なお播磨灘での津波波高は、第1波目よりも第2波目、第3波目の方が大きい地点もみられ、波長も少し長くなっている。備讃瀬戸地点での津波は、発生から約2時間後に到達し、燧灘、広島湾地点では波長が長く、うねりのようにみえる。
次にCaseBの津波波高をみると、一番大きいのが豊後水道にある測定地点であり、次いで周防灘、伊予灘へと続き、内海に入るほど波高は減衰している。豊後水道では、半日以上に渡って大きな津波が続いている。ゲート操作により津波を与えた豊後水道の地点では約60cmの津波が発生し、その津波が内海側に伝播し大分県の佐伯の地点では160cm近くの大きな津波となっている。また愛媛県の八幡浜の地点でも約150cmの津波が測定されている。伊予灘地点での津波は、発生から約1.5〜2時間後に到達し、松山で約30cmの津波波高となっている。周防灘における津波の到達時間は、姫島で発生から約1.5時間後、宇島で約3時間後であり場所的に大きく異なっている。これは、海底地形や海岸地形の影響により津波の伝わる速度が異なったためだと推測される。広島湾、燧灘地点での津波は、発生から約3時間後に到達し、呉では約60cmの津波波高となっている。豊後水道から入ってくる津波は、神戸や大阪の地点においても僅かではあるが確認することができる。
| 図5-2(1) |
主要港湾における津波波高の変化
(CaseA: 紀伊水道から津波発生) |
|
(拡大画面:150KB)
|
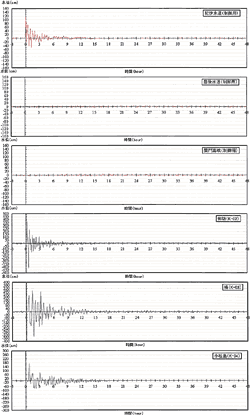 |
| 図5-2(2) |
主要港湾における津波波高の変化
(CaseA: 紀伊水道から津波発生) |
|
(拡大画面:147KB)
|
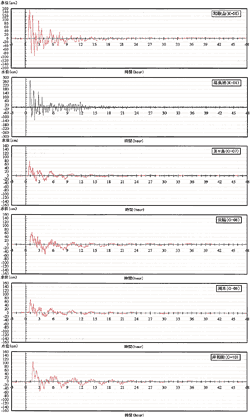 |
| 図5-2(3) |
主要港湾における津波波高の変化
(CaseA: 紀伊水道から津波発生) |
|
(拡大画面:137KB)
|
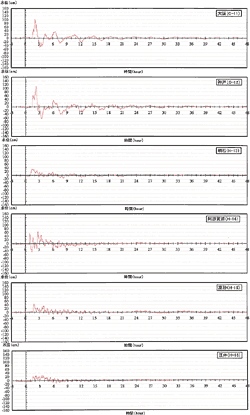 |
| 図5-2(4) |
主要港湾における津波波高の変化
(CaseA: 紀伊水道から津波発生) |
|
(拡大画面:134KB)
|
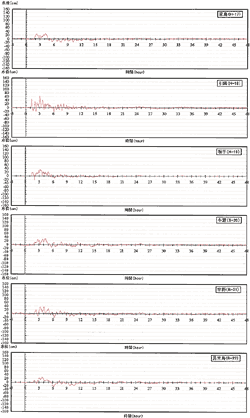 |
| 図5-2(5) |
主要港湾における津波波高の変化
(CaseA: 紀伊水道から津波発生) |
|
(拡大画面:133KB)
|
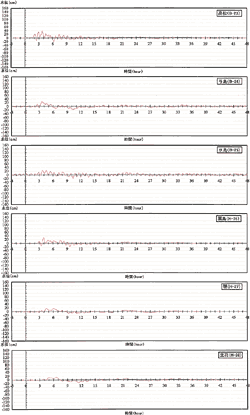 |
|