|
3.2 異常潮位時における潮汐変化
実験Case1の各地点における潮汐の時間変化を 図3-4(1)〜3-4(10)に、実験Case3の各地点における潮汐の時間変化を 図3-5(1)〜3-5(10)に示す。 Case1の潮汐変化をみると、異常潮位を発生させた直後に水位波形は乱れている。この異常潮位発生後の水位波形の乱れは、大阪湾奥部、広島湾奥部、別府湾、豊後水道の地点において少し大きいが、異常潮位発生前と発生後の潮汐振幅の大きさをみると、全ての地点において殆ど同じ大きさであり顕著な違いはみられない。また、全ての地点において水位が約30cm上昇し、異常潮位の状態で潮汐が重なっている。
Case3の潮汐波形をみると、異常潮位発生期間は瀬戸内海の西側で水位レベルが高く、瀬戸内海全体で水位勾配がついている。このような水位勾配がつくと西側から東側へ貫くような海水の流れが発生し、海水の物質輸送能力や海水交換速度にも大きく影響することが推論される。
次に、潮汐状態を定量的に評価するため 図3-6に示したA、B、Cの区間におけるデータを用いて調和解析を行った。調和解析の結果を 表3-2(1)〜3-2(3)に示す。表に示した位相は、紀伊水道の田辺を基準に整理している。 異常潮位発生期間の区間Bのコンスタント項値(表ではConst.と表示)をみると、Case1では30cm前後、Case2では50cm前後であり、調和解析の結果からも場所的な違いはみられない。一方、Case3のコンスタント項値は、豊後水道、周防灘、伊予灘の海域で30cm前後、広島湾の海域で27cm前後、燧灘の海域で17〜25cm、備讃瀬戸の海域で6〜17cm、播磨灘の海域で5cm前後、大阪湾の海域で1cm前後の値となっている。もし、異常潮位の発生原因が黒潮流路の変動であるならば、異常潮位の影響はCase3で示したように瀬戸内海の東側より西側の方が大きいと推論される。
図3-7に、調和解析より得られた区間Bのコンスタント項値の分布を示す。図にはCase1における区間Aの値もプロットしている。
図3-6 調和解析に用いたデータ区間
|
(拡大画面:37KB)
|
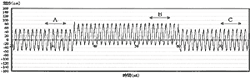 |
| 図3-4(1) |
主要港湾における異常潮位時の潮汐変化(Case1: 水位偏差30cm) |
|
(拡大画面:199KB)
|
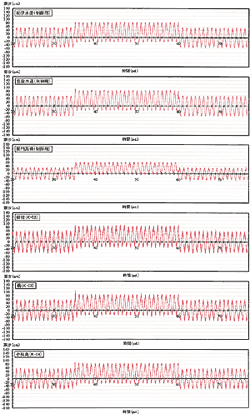 |
| 図3-4(2) |
主要港湾における異常潮位時の潮汐変化(Case1: 水位偏差30cm) |
|
(拡大画面:189KB)
|
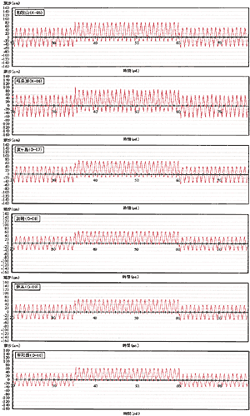 |
| 図3-4(3) |
主要港湾における異常潮位時の潮汐変化(Case1: 水位偏差30cm) |
|
(拡大画面:278KB)
|
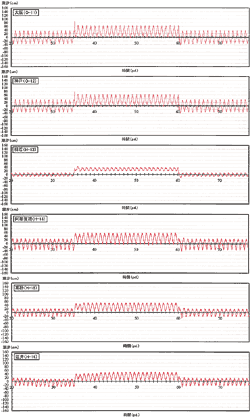 |
| 図3-4(4) |
主要港湾における異常潮位時の潮汐変化(Case1: 水位偏差30cm) |
|
(拡大画面:189KB)
|
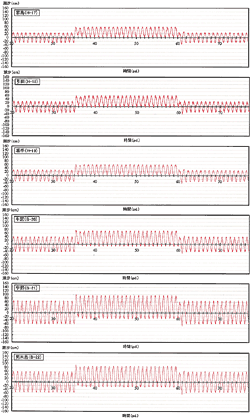 |
| 図3-4(5) |
主要港湾における異常潮位時の潮汐変化(Case1: 水位偏差30cm) |
|
(拡大画面:258KB)
|
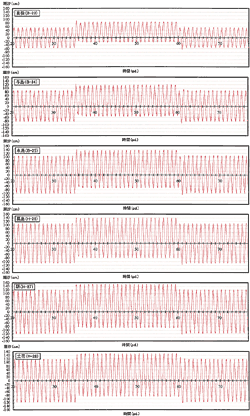 |
|