|
3. 主要港湾における異常潮位時の潮汐測定と災害度合の解明実験
気象庁では異常潮を「津波、高潮のように直接的な原因がはっきりしており予測可能な現象による潮位異常を除く潮位の異常」としており、そのうち比較的長期間(1〜2週間)継続し、かつ広範囲に出現するものを異常潮位と定義している。異常潮位の原因は、ある気圧配置が継続することや黒潮流路の変動などが考えられているが、いまだ明らかではない。
潮位の高まる夏から秋にかけての大潮期に異常潮位が発生すると、浸水などの被害が生じる。瀬戸内海の広島では、この異常潮位による被害が近年、度々報道されている。
ここでは水理模型内に異常潮位を発生させて、主要港湾における異常潮位の影響を評価することにした。
水理模型内における異常潮位の発生方法は、図3-1に示すように紀伊水道、豊後水道、関門海峡の基準水位(M2潮汐の平均値)を操作して行った。
表3-1、図3-2は、異常潮位の実験条件および実験設定を示したものである。実験では、平均潮であるM2潮汐を与えた中で異常潮位を発生させた。
Case1では水位偏差30cm(基準水位から30cm[模型では1.9mm]水位上昇)が25潮汐周期間続く現象を、Case2では水位偏差50cm(基準水位から50cm[模型では3.1mm]水位上昇)が25潮汐周期間続く現象を扱い、紀伊水道、豊後水道、関門海峡の全てにおいて与えた。Case3は豊後水道のみ水位偏差30cmを25潮汐周期間与えた。
図3-1 水理模型内における異常潮位の発生方法
表3-1 異常潮位の実験条件
|
紀伊水道の水位偏差量 |
豊後水道の水位偏差量 |
関門海峡の水位偏差量 |
| Case1 |
30cm
|
30cm
|
30cm
|
| Case2 |
50cm
|
50cm
|
50cm
|
| Case3 |
なし
|
30cm
|
なし
|
|
異常潮位の影響を評価するために主要港湾55地点において潮汐の測定を行った。
潮汐の測定は、図3-2に示すように異常潮位を発生させる15潮汐周期前から開始し、異常潮位期間も含めて57潮汐周期間行った。潮汐データは、A/D変換器を介してサンプリング間隔1秒でWindowsマシンに収録した。
測定した主要港湾の位置を 図3-3に示す。また、その時の水位計設置状況を 写真3-1(1)〜3-1(3)に示す。なお使用した水位計(電子工業製VC-201型)は、検出器先端につけられた針状電極を常時水面下で一定の水深に保持させる触針型のもので、ドリフトも少なく0.1mmまで測定可能である。
図3-2 異常潮位の実験設定(pd.: 潮汐周期)
|
(拡大画面:31KB)
|
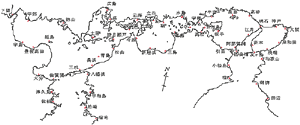 |
|