|
6. コミュニケーションの重要性
1979年ころから,日本の学校では「校内暴力」,「いじめ」「登校拒否」,「荒れ」,「切れる子ども」,「学級崩壊」など様々な問題が起ってくる。大脳活動の型の変化の要因として,子どもの遊びが鬼ごっこ・かくれんぼなどの動的なものから,テレビなど,静的なものに変化したことと,テレビの視聴時間が長くなったという2点が考えられるものの,このことと日本の学校で起こる様々な問題を単純に結びつけることはできません。しかし,日本の子どもたちの遊びの内容とテレビの視聴時間の変化という2点に潜むもの,またはこの2点を結ぶ線の意味について見逃してはならない大変重要なことが分かってきます。
栃木県のさつき幼児園では,先生と園児が「わぁーわぁー,きゃーきゃー」いいながら取っ組み合いをする「じゃれつき遊び」をカリキュラムとして取り入れています。その遊びの効果を調べるために,一年間園に密着し,GO/NO-GO課題による大脳活動の型を追ってみるとGO/NO-GO課題の成績は,幼児であるにもかかわらず成績は小学2・3年生の成績でした。これは人間同士のスキンシップにその効用があることが推察されました24)。それと類似した例として,1970年オハイオ大学で行われた実験が挙げられます。両群に毎日,高コレストロールの餌を与え,一群には何もしないが,もう一群はヒトと一緒に遊んだり抱擁したりする時間を与えたところ,その群のウサギは,何もしない群よりも高脂血症になる率が約60%減少することが報告されています。そしてこの効果についてNeremは,ヒトとウサギとの社会心理学的要因(sociopsychological factors)とコメントしています35)。
さらに,米国の精神科医であるSpiegellは,2年以内に死亡すると予想された女性の乳癌患者(86名)を2分し,一方は今までの治療方針である放射線療法と投薬,そして残りは放射線療法と投薬プラス週に一回のグループセラピーといった,人と人とのふれ合いを意味するコミュニケーションをノルマとして加えました(図10)。
| 図10: |
乳がん患者の生存率からみた心理療法の効果について。(David. Joan, B.: Effect of psychosocial treatment on survival of patients with metastatic breast cancer. The Lancet, 14: 888-891, 1989) |
その結果,後者のグループは前者に比べ2倍以上も生き延びたということを報告します36)。さらに,Spiegellは癌患者の夫婦或いは,エイズ患者のパートナーのどちらか一人が亡くなると,生き残ったもう一人の寿命が非常に短いことや,関わるコミュニティをたくさん持っているお年寄りが長生きしているといった研究結果から,人と人とのふれ合いが病を癒すという非常に重要な意味を持ち同時に,社会的な疎外感,孤立感が肉体的・精神的に非常に危険であることを警告します37)。この様に,人と人とが関わる人間の集団,例えばそれは傷ついた者同士が安心して身を寄せあえる場所であったり,孤独感を癒し,本来の人間性を取り戻す場所には,病を治すという何らかの治癒能力があることが推察されます。そして,「癒す」という英語heal(ヒール)の語源は,「全体化」のwhole(ホール)でto make whole, to bring togetherと同じ意味を示すといわれています。つまり,「癒す」ということは,コミュニティなどの人と人との集団・集まりを示唆します。昔の人は,人と人とが集いふれ合うことで実は,癒し癒されていることをすでに知っていたと思われます39)。
1996年に日本学校保健会が総数26,545人にのぼる大規模なアンケート調査を実施しました。この調査項目中の3項目,・昨日,テレビやビデオを何時間見ましたか,・昨日,テレビゲームを何時間しましたか,・昨日,読書や音楽鑑賞など室内遊びを何時間しましたか,を合わせると,小・中・高生の1日の平均時間が約5時間弱でした31)。2000年,2002年に行われた長野市の小学校4年生の調査では,睡眠時間が9時間30分に対して,テレビ・テレビゲームの時間は4時間30分でした42),43)。これは日本の家庭が,家庭の機能を果たさなくなっていることを意味します。子どもが家に帰り就寝するまで,親子間でのふれ合いやコミュニケーションがほとんどないことになります。1971年にHarlowは,サルを一匹だけ3ヶ月間,隔離すると,そのサルは社会適応ができなくなるという実験を行なっています。6ヶ月間この実験を継続すると,サルは自己防衛できなくなり,12ヶ月間継続すると,手足を噛みきるほど,自傷行為をすることが報告されています。このサルを正常にもどすためにはリハビリとして,トレーニングされたメスザルと一緒に遊ばせるそうですが,完全には元に戻らないことが報告されています44),45),46)。現在の日本の子どもが,テレビ・テレビゲームによって1日の約1/5である5時間、人と人とがふれ合うコミュニケーションをしないでいると,5年間で約1年の期間の隔離という,このサルの実験と重なってきます。サルを直接人間にあてはめることはできませんが,日本の子どもにもこのサルと同じような事態が起こっているかもしれません。この他にも人と人とのふれ合い,コミュニケーションが,不幸なことに著しく欠如した事例も報告されています。1799年フランス東部で野生の動物に育てられたと思われる,推定12歳の子どもは,人間らしい生活をすることが非常に困難であったそうです47)。また1912年,インドの東部で狼に育てれたとされる,アマラという推定8歳の少女は,最後まで3歳くらいの知能しか持つことができなかったそうです48)。さらに,1970年,米国,ロサンゼルス近郊の地下室に,生まれてから13年間幽閉されていたジーニという少女が救出されますが,彼女もまた同様に,言葉がままならず,人間らしい生活は極めて困難であったこと49)等が報告されています。
動的な遊びから静的な遊びへの移行は,日本の子ども達に運動不足と大脳活動の発達の遅れをもたらしたと考えられています25),26),27),28),29)。脳にとってスポーツや運動することは大変重要です。運動しなくなると,脳にも大きな影響を及ぼすことが動物実験によって報告されています。図11はHeinという研究者の猫の実験風景です。
Heinは二匹の子描を一日3時間,壁にしま模様のついた円柱のドラムの中に入れ,一匹は自分で歩いて回れるようにし,もう一匹は歩けないように台の上に乗せ,二匹を一本の棒の端にそれぞれ固定し,その棒の中央に支柱をおき,二匹が左右対称に移動するようにします。受動的に育った猫は,自分で歩くという自発的で能動運動的な描よりも,大脳皮質連合野に関連する視覚行動がひどく悪いことが判明し,能動的運動が脳発達に大きく関与していることが示唆されます52)。図12はRosenzweigの実験風景です。
| 図11: |
能動的に動く子猫(A)と受動的に動く子猫(P)
(Held, Heinの論文から) |
| 図12: |
ラットの異なった環境。(A: 標準環境 B: 刺激の乏しい環境 C: 刺激の豊富な環境)(立花隆:脳を鍛えれる。新潮社,p85。) |
Aは標準環境。Bは刺激の乏しい環境。Cは刺激の豊富な環境である。十匹程で,広く刺激の豊かなC環境で育ったラットは,一匹だけで,狭く刺激の乏しいB環境で育ったラットや3匹で標準的なA環境で育てたラットに比べ,大脳皮質での重量や神経細胞や学習課程に有意な違いが出たことが突き止められます53)。図13は図11と類似した条件で実験を行ない,大脳皮質のニューロンによる樹状突起の変化を調べたものです。
| 図13: |
3つの環境の違いによる樹状突起の枝別れ数・量の違い。EC: 10匹程度の豊かな環境 SS: 3匹程度の標準的な環境 IC: 1匹だけの貧しい環境(Volkmar, R., Greenough, T.: Rearing Complexity affects brancing of dendrites in visual cortex cortex of the rat. Science. 176: 1445-1447. 1972) |
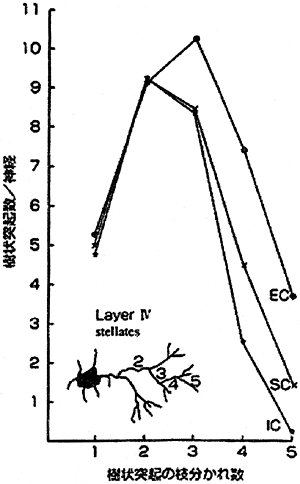
刺激の豊富な環境で育ったグループは,3次以降のニューロンによる樹状突起の枝分かれが,他のグループよりも多くなっていることが分かります54)。ヒトにおいても,一日の歩数と会話数の関係を調べてみると,親密なパートナー関係を持つ者以外では,男女共に歩数が増加すると会話数も増加するといった,有意な正の相関関係が見出されました。もう少し詳しく調べていかなくてはなりませんが,スポーツや運動をしなくなるということは,コミュニティへの参加から成る人と人との会話やふれ合いをなくしていることが推察されます55)。また脳では,スポーツや運動時には,3次元という空間と,時系列からなる時間との認識の中で,自己と他者を合わせた,インタラクティブな行動の制御をしていかなくてはなりません。現在のロボット学の現状では,これらの限りない多数の認識と制御をどのようにバランスよく構築していくかがポイントのようです。例えば,ヒューマノイド・ロボットであるホンダ社製の「ASIMO」やソニー社製の「SDR-3X」は滑らかな二足歩行を実現していますが,ヒトの脳とそっくりのシステムをロボットに組み込もうとすると,脳一千億個のニューロン_数千個のシナプス=数十兆のパラメータを制御しなくてはなりません。しかし,このようなことは,現在の機械工学では無理なのです6)。このように,スポーツ・運動・会話という,人と人とがふれ合うコミュニケーションは,脳内の神経回路をフルに活用し,互いに連係させ合いながら情動・運動・感覚・記憶・学習・認知・思考といった情報を選択・保持・整理・統合し,目的情報の生成と制御をほぼ同時に行なっていると推察されています。運動・スポーツや会話中の脳の複雑なシステム過程を考えれば,コミュニティに参加せず,運動・スポーツからも遠ざかり,話も聞かず話もせずといったコミュニケーション不足は,脳が楽をしている状態にあるとも予想されます。
ヒトも運動しなければ体力は失われます。走ったり歩いたりしなければ足も当然衰えていくでしょう。骨折した腕や足に治療のためにギブスをすると,動かすという刺激がなくなり,数週間で骨も筋肉も細くなりますが,前頭前野の機能にも同様の事が予想されます。日本の1969年と1979年の子どもたちによる大脳活動の発達の遅れは,遊びのスタイルの変化によって,運動量や,人と人とのふれ合いが少なくなったために,この前頭前野の部分をあまり使わなくなったことが考えられます。脳の前頭前野は,運動や他人とのコミュニケーションという刺激を受けながら,過去の記憶を情報として蓄え,意味のあるものを選択し,それらを整理・統合しながら目的情報の生成・制御を行ない,各種感覚器官を通じ,これらの情報をオンラインに載せて操作していると考えれば,この運動や他人とのコミュニケーションの刺激が減少することは,ヒトが前頭前野にある高次機能を使わずに済ませていることがあると予想されます。このような状況には,現代化という便利な社会が大きく関わっているように思えます。ひと昔前は,村じゅう総出で田んぼを耕し,田植えをして稲刈りをしていました。しかし,現代化にともない便利な耕耘機や田植機・稲刈機の登場によって,何でも一人でこなせるようになり,厄介で面倒な労働と人間関係から解放されますが,それは同時に,運動や人と人とのふれ合いの機会を奪ったのかもしれません。
日本の子どもたちも,以前は大勢で群をなし,野山を駆け回り,友達とぶつかり合い,川で泥んこになって遊んでいました。彼らはその中で注意・集中することを学び,運動・感覚機能を養ってきたはずです。また,泣いたり,笑ったり,怒ったり,叫んだりしながら感情のカタルシスを行い,驚いたり,寂しがったり,傷ついたりする中で人の心の温かさ,友情や愛情や可能性といったものを学んでいました。お互いの存在を確認し,自分自身の存在をも実感として確認しながら,生きる意志と希望を育んでいったと思われる。こうしたことすべてが,実は前頭前野にとっては適切な刺激なのである。日本の子どもの群れ社会の減退は,喧嘩の仕方や仲直りの仕方,人はどのようにしたら痛み,悲しみ,また喜ぶのかといった人間の根源的なことを学習し前頭前野を発達させる絶好の機会を奪ってしまっていると予想されます57)。こうした人間関係を学習できず,前頭前野が適切な成長を遂げられないために,ときどき突拍子もない悲惨な事件が小・中学校で起っているのかもしれません。以上のような事を踏まえて考えていくと,今の日本社会に必要なものは,そこにいると何となく温かい気持にさせられる場所,何か厳しい局面に遭遇しても皆で力を合わせ,それを乗り切ることのできるような,笑いと思いやりと愛情のある,家族のようなコミュニティではないでしょうか。そして,コミュニケーションと運動が楽しめる家族,家庭,学級,学校,社会を取り戻し,創造していくことが大切なのではないかと思います。
参考文献
1)甘利俊一,外山敬介. 脳料学大辞典. 朝倉書店,岩波新書: pp1-357,2000.
2)Brodman, K.Nuro Ergebnisse uberdie vergleichende histologische Lokalisation der Grosshirnrinde mit besonderer Berucksichtigung des Stirnhirns. Anat. Anz.(Suppl.)41: 157-216,1912
3)Macmillan, M. An Odd King of Fame: Stories of Phineas Gage. Cambridge, MIT Press, pp1-47,200
4)立花隆,前頭葉を鍛える,講談社: pp83-110, 1989
5)Luria, R.Higher cortical functions in man. Consultants Bureau New York; pp218-295, 1966
6)茂木健一郎,脳の謎に挑む,サイエンス社: pp2-25, 2003
7)Baddeley, A. Working memory. Oxford University Press. 1986
8)Walker, A.E.A cytoarchitectural study of the prefrontal area of themacaque monkey. J.Comp. Neurol, 73:59-86, 1940
9)Sasaki, K, Gemba, H.Electrical activity in the prefrontal cortex specific to no-go reaction of conditioned hand movement with colour discrimination in the monkey. Exp Brain Res, 64, 603-606,1986
10)Brodman, K.Vergleichende Lokalisationsleher der Grobhirnrinde in ihren Prinzipien dargestellt auf Grund des Zellenbaues. Barth, Leipzig. pp127-197,1909
11)Sasaki, K. Gemba, H. Nambu, A. Matsuzaki, R.: Activity of the prefrontal cortex on no-go decision and motor suppression In: Motor and Cognitive Function of the prefrontal Cortex, (Eds.)A-M. Tierry et al, Springer- Verlag, Berlin Heidelberg, pp139-159, 1994
12)Jueptner, M.Stephan, M.Frith, d.Brooks, J.Frackowia, S.Passingham, E.Anatomy of motor learning. I.Frontal cortex and attention to action. Neurophysiol. 77, 1313-1324,1997
13)Ungerleider, g.Courtney, M.Haxby, V.A neural system for human visual working memory. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 95, 883-890,1998
14)Owen, M.Stern, E.Look, B.Tracey, I.Rosen, R.Petrides M.Functional organization of spatial and nonspatial working memory processing within the human lateral frontal cortex. Proc.Natl. Acad. Sci. USA. 95: 7721-7726, 1998
15)Sawaguchi, T., Goldman-Rakic, P.S.The role of D1-dopamine receptor in working memory: local injections of dopamine antagonists into the prefrontal cortex of rhesus monkeys performing an oculomotor delayed-response task. J.Neurophysiol.71.515-528,1994
16)Felleman, D.J.and VanEssen, D.C.Distributed hierarchical processing in the primate cerebral cortex. Cerebral Cortec, 1, 1-47, 1991
17)Godman-Rakic, C:Cellular basis of working memory. Neuron, 14, 477-485,1995
18)正木健雄,森山剛一. 人間の高次神経活動の型に関する研究,東京理科大学紀要,第4号,69-81, 1971
19)西條修光,森山剛一,熨斗謙一,熊野晃三,村本和世,阿部茂明,正木健雄. 子どもの大脳活動の変化に関する研究,日本体育大学紀要,第16号,61-68, 1981
20,21)Teplov, B.M. Problems in the study of general type of higher nervous activity in man and animals, Pavlov's, Typology, Pergamon, Press, pp3-153, 1964
22)クラスノゴルスキー,子供の高次神経活動,世界書院,204-243, 1964
23)ルリヤ,言語と精神発達,明治図書,139-171, 1969
24)西條修光,寺沢宏次,正木健雄. 幼児における大脳活動の発達−高次神経活動の型から−,日本体育大学紀要,25-30, 1984
25)寺沢宏次,西條修光,柳沢秋孝,篠原菊紀,根本賢一,正木健雄. GO/NO-GO実験による子どもの大脳発達パターンの調査−日本の'69, '79, '98と中国の子供の'84の大脳活動の型から−,生理人類学会誌,第5号,2, 47-54, 2000
26)寺沢宏次,賈志勇. 中日儿童高級神経活動類型的研究,北京体育学院学報,34期,87-94, 1986
27)寺沢宏次,西條修光,柳沢秋孝,篠原菊紀,根本賢一,正木健雄. 中国の子どものGO/NO-GO課題による大脳活動のパターンについて,文理シナジー学会誌,5-10, 2002
28)寺沢宏次,西條修光,柳沢秋孝,篠原菊紀,根本賢一,正木健雄. アメリカのGO/NO-GO課題と生活調査について,日本体育学会第58回大会,261-268, 2003
29)寺沢宏次: 子どもの脳に生きる力を,オフィスエム,16-226, 2000
30)Terasawa, K. Saijo, O. Yanagisawa, A. Shinohara, K. Nemoto, K. Masaki, T. Change in cerebral activity in children-Japan 1969, 1979, 1998 and China 1984- Second international conference on psychophysiology in ergonomics, pp94-95, 1998
31)学校保健会. 児童生徒の健康状態サーベランス事業報告,日本学校保健会,1996
32)小川浩貴,寺沢宏次,西條修光,柳沢秋孝,篠原菊紀,根本賢一,正木健雄. go/no-go実験による日本の子どもの大脳活動の変化について,文理シナジー学会誌,5, 1:14-27, 2003
33)寺沢宏次. 子どもの遊びの重要性−子どもの大脳活動の加齢的推移について−,感覚統合障害研究,第7号,1, 2, 13-23, 1999
34)Terasawa, K.Saijo, O.Yanagisawa, A.Shinohara, K.Nemoto, K.Masaki, T.GO/NO-GO experiment to study cerebral development patterns in Japanese and Chinese children Nagano Journal of Physical Education and Sports, NO.11, 1-7, 2000
35)Robert, M.Nerem, L.Fredric, C.Social environment as a factor in diet-induced atherosclerosis Science, 208, 27, 1980
36)David, S.Joan, B.Effect of psychosocial treatment on survival of patients with metastatic breast cancer, The Lancet, 14, 888-891, 1989
37)David, Rhonda M.Imagery and hypnosis in the treatment of cancer patients, Oncology, 1179-1195,1997
38)佐藤光房,遺された親たち. あすなろ社,1992
39)Moyers, B.Ed.Healing and the mind, Doubleday, New York, 87-114, 1993
40)Levine, S., Coe, C., Wiener, SG: Psychoneuroendocrinology of stress, A phychobiological perspective, in Brush FR, Levine S, Phychoendocrinology. New York, Academic Press, 1989
41)アン・モア,デビット・ジェセル. 犯罪に向かう脳,原書房,1997
42)寺沢宏次,西條修光,柳沢秋孝,篠原菊紀,根本賢一,正木健雄. 学級崩壊の改善についての検討−コミュニケーションと体育学的なアプローチについて−,文理シナジー学会誌,5,
1, 11-16, 2001
43)寺沢宏次,西條修光,平野吉直,柳沢秋孝,篠原菊紀,根本賢一,正木健雄. GO/NO-GO課題からみた子どもの春季雪上キャンプ活動の効果について,文理シナジー学会誌,7(2), 7-12, 2003
44)河合雅男: 子どもと自然,岩波新書,1990
45)Harlow, HF.Suomi, s.: Social recovery by isolation- reared monkeys, Proc. Nat.Acad. Sci. USA, 68, 7, 1534-1538, 1971
46)Harlow, HF.Suomi, s.: Production of depressbehaviors in young monkeys, J Autism and Childhood schizophrenia, 1,3, 246-255, 1971
47)Itad. アヴェロンの野生児,福村出版,1975
48)Arnold, G. 狼にそだてられた子,家政教育社,pp17-116, 1967
49)Russ, R. 隔離された少女の記録,晶文社,1995
50)本庄巖. 脳からみた言語,中山書店,1997
51)体育科学辞典,大修館書店,pp540-776, 1975
52)Hein A. Held R.Dissociation of the visual placing response into elicited and guided components. Science, 158, 390-392, 1967
53)Rosenzweig R, Benett L, Diamond C. Brain changes in response to experience. Sci Amer 226, 22-30, 1972
54)Volkmar R, Greenough T. Rearing complexity affects branching of dendrites in the visual cortex of the rat. Science, 176, 1445-1447, 1972
55)小野直也,関谷北斗ほか,運動とコミュニケーションとの関係,文理シナジー第16回大会大会号,p-, 2004(5月に発表予定)
56)宮村実晴,最新運動生理学,真興交易医書出版,pp335-395, 1996
57)野垣義行,日本の子どもの歴史,第一法規. 79-211, 1974
|