|
全国剣詩舞群舞コンクール決勝大会優勝チーム一覧表
昭和六十年度
〈剣舞の部〉
(兵庫)
小野 尊由
八木 保博
瀧 吉治
〈詩舞の部〉
(兵庫)
小野真智子
原 京子
大持恵美子
米倉 啓子
石原 明子
昭和六十一年度
〈剣舞の部〉
(愛知)
安藤 裕嗣
安藤 由記
堺 友紀
〈詩舞の部〉
(愛知)
杉浦 裕美
天野 利香
中村 里抄
今井喜久子
大日方里美
昭和六十二年度
〈剣舞の部〉
(愛知)
入倉 幸一
城所 紀彰
長谷川勝生
〈詩舞の部〉
(愛知)
亀井 美乃
安藤 裕嗣
堺 友紀
亀井 秀明
安藤 由記
昭和六十三年度
〈剣舞の部〉
(愛知)
広田 光次
村田 栄一
滝川 知昭
〈詩舞の部〉
(岡山)
田中小枝子
岸本 晴美
秋山 愛子
中尾 章子
川口由紀子
平成元年度
〈剣舞の部〉
(大阪)
加司 和博
西村 朗子
山田 満稀
〈詩舞の部〉
(兵庫)
石原 明子
小西 悦子
酒井 玉美
松本 房子
松本 桂子
平成二年度
〈剣舞の部〉
(愛知)
森下 裕紹
伊藤 由康
伊藤 修司
〈詩舞の部〉
(愛知)
入倉 幸一
城所 紀彰
長谷川勝生
鈴木 一人
永井 基靖
平成三年度
〈剣舞の部〉
(愛知)
杉浦 裕美
建部 司
大日方里美
〈詩舞の部〉
(岡山)
藤上 桂子
田中 佳子
中島 祥子
宇野 智美
片山 陽子
平成四年度
〈剣舞の部〉
(愛知)
熊谷 公江
中神 友佳
中野 琴子
〈詩舞の部〉
(愛知)
建部 司
大岡 史帆
山本 智美
石渡 千紘
岡本菜穂子
平成五年度
〈剣舞の部〉
(愛知)
林 季永子
山口加奈子
尾崎 里恵
〈詩舞の部〉
(兵庫)
長坂 紗織
長坂恵理子
関 みのり
荒谷早智子
淡谷 亮太
平成七年度
〈剣舞の部〉
(愛知)
近藤 聡司
近藤 敦司
淡谷 亮太
〈詩舞の部〉
(愛知)
森下 裕紹
伊藤 由康
伊藤 修司
中神 友佳
中野 琴子
平成九年度
〈剣舞の部〉
(大阪)
大道 学美
辨天 繁和
多田 和晃
〈詩舞の部〉
(愛知)
蟹江 功子
佐々木京子
大野 晶子
長坂 理絵
鈴木 宏実
平成十一年度
〈剣舞の部〉
(愛知)
伊藤 明
伊藤 武
亀田 功治
〈詩舞の部〉
(兵庫)
小野 藍子
田辺富士子
田辺 小泉
田辺 文
原 優子
平成十三年度
〈剣舞の部〉
(愛知)
大岡 史帆
長坂 紗織
荒谷早智子
〈詩舞の部〉
(愛知)
長澤 仁美
松本 幸子
神藤 沙紀
松本 典子
阿部 沙織
平成十五年度
〈剣舞の部〉
(愛知)
大野 晶子
鈴木 宏実
長坂 理絵
〈詩舞の部〉
(愛知)
入倉 仁美
山本 薫
山本 直子
川野 佳代
石川 公江
☆剣舞
(幼年・少年の部)
1 四十七士 (大塩平八郎)
2 不識庵機山を撃つの図に題す (頼 山陽)
3 小楠公の墓を弔う (杉 聴 雨)
(青年・一般の部)
1 逸題 (篠原 国幹)
2 山中鹿之助 (山田 済斎)
3 九月十三夜陣中の作 (上杉 謙信)
4 越中覧古 (李 白)
5 和歌・敷島の (本居 宣長)
☆詩舞
(幼年・少年の部)
1 九段の桜 (本宮 三香)
2 春暁 (孟 浩 然)
3 短歌・ふるさとの (石川  木)
(青年・一般の部)
1 余生 (良 寛)
2 春簾雨窓 (頼 鴨  ) 3 海を望む (藤井 竹外)
4 折楊柳 (楊 巨 源)
5 和歌・天の風 (阿倍仲麻呂)
月刊『吟剣時舞』ご購読のお願い
月刊誌『吟剣詩舞』は、指導者および一般愛好者の皆さんに不可欠の吟剣詩舞道界の幅広い情報誌として、また、教養誌として発行されています。
購読料は年間四、〇〇〇円(送料込)です。お申し込みは、財団法人日本吟剣詩舞振興会事務局『吟剣詩舞』係あて、購読料を添えてお申し込み下さい。
どなたでも購読できます。どうぞ、お気軽にお申し込み下さい。
詩歌は人の心の表現であり、すぐれた詩歌は人類文化の遺産である。われわれの先達は、この詩歌を吟じ、その吟により舞うことを考え、芸としての向上進歩を目ざして精進努力を重ね、吟詠・剣舞・詩舞というわが国独自の高雅な芸道を育てあげた。
吟剣詩舞道は礼と節を、その心とする。詩歌に親しんで情操を高め、日本民族の心を探究しながら自己の陶冶を志向するこの芸道こそ、わが国の精神文化の高揚に不可欠のものである。
われわれは、この価値ある吟剣詩舞道を受け継いだことに大きな誇りをもつと同時に、各人の研鑽と相互の協力によってますます斯道を隆盛に導く責任を果たさなければならない。しかも、その実践は、この芸道の心、すなわち礼と節の上にたたなければならない。その軌範として、この憲章を制定する。
昭和五十年一月十一日
財団法人 日本吟剣詩舞振興会
会長 笹川良一
ほか 役員一同
一、基本姿勢
吟剣詩舞道を行なう者は、礼と節とを行動の軌範とし、日々、芸の研鑽と品性の陶冶に努める。
二、指導者の心構え
吟剣詩舞道を指導する者は、みずから師たるにふさわしい人格、識見を備え、指導全般にあたっては権威をもって臨む。
三、師に対する心構え
吟剣詩舞道を学ぶ者は子弟の礼節をわきまえ、秩序を堅持する。
四、分家・独立
吟剣詩舞道を行なう者が分家・独立する場合は、その組織を代表する者の許しを得る。
五、他流との関係
吟剣詩舞道を行なう者は他流の名誉を傷つけ、秩序を乱すような言動は厳に慎しむ。
六、吟剣詩舞道の普及向上
吟剣詩舞道を行なう者は、大衆性と芸術性とを併せもつ斯道の今日像を正しく伝え、特に青少年層における吟剣詩舞道の普及向上に努める。
七、吟剣詩舞道の目標と相互の協力
吟剣詩舞道を行なう者は、相互に協調、互譲の精神をもって斯道の普及振興に協力し、本会の認める姉妹団体とも動物有機体的団結をもって日本の伝統に基づく国家社会の正しい発展に寄与する。
| (拡大画面:238KB) |
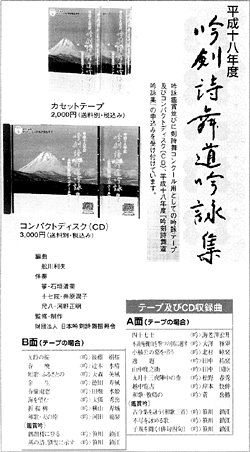 |
|
|
|
平成十八年度全国剣詩舞コンクール指定吟題
《剣舞》
幼年・少年の部
1、四十七士 (大塩平八郎)
2、不識庵機山を撃つの図に題す (頼 山 陽)
3、小楠公の墓を弔う (杉 聴 雨)
青年・一般の部
4、逸題 (篠原 国幹)
5、山中鹿之助 (山田 済斎)
6、九月十三夜陣中の作 (上杉 謙信)
7、越中覧古 (李 白)
8、和歌・敷島の (本居 宣長)
《詩舞》
幼年・少年の部
9、九段の桜 (本宮 三香)
10、春暁 (孟 浩 然)
11、短歌・ふるさとの (石川  木) 青年・一般の部
12、余生 (良 寛)
13、春簾雨窓 (頼 鴨  ) 14、海を望む (藤井 竹外)
15、折楊柳 (楊 巨 源)
16、和歌・天の原 (阿倍仲麻呂)
| (拡大画面:173KB) |
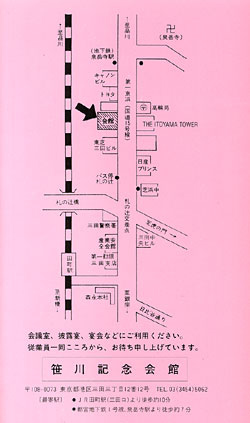 |
|
|
|
|