|
4.4 越波流量とうちあげ高の計算結果
松合地区を示した図4-4-1の黄色の地点(20m間隔で10点:天端高TP4.7〜6.5m)について越波とうちあげ高を計算した。
| 図4-4-1 |
越波とうちあげ高の計算位置
(上:平面図、下:縦断面図) |
| (拡大画面:51KB) |
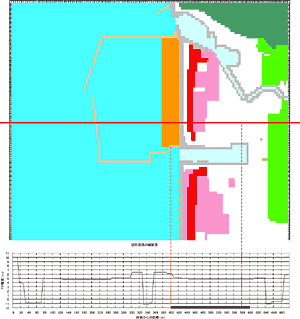 |
|
図4-4-2 松合地区の沖〜岸方向の断面図の例
| (拡大画面:13KB) |
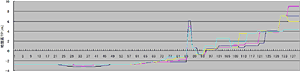 |
|
沖〜岸方向の断面図の例を図4.2に示す。松合地区の前面には干潟が広がっているので、海底勾配は1/200に満たないくらい非常に緩やかである。したがって干潮時ならば護岸に打ち寄せる海水はないが、満潮時あるいはそれに高潮が加わった場合に問題となる。
越波やうちあげ高の計算式では、1/10〜1/30程度の海底勾配を想定しているが、こういう場所ではその条件を満たさない。しかしながら潮位が高い時は直接護岸まで打ち寄せる水があって、数mの水深の海域が広がるので計算は可能である。
図4-4-3 不知火町〜八代市周辺の水深図と波浪推算出力点●
図4.1の黄色で示した10地点を左側(東側)から1〜10と番号を振って、その偶数番について(40m毎に)、図4.4と図4.5にうちあげ高と越波流量の計算結果を示した。
道路兼用の堤防の天端は仲西船溜を乗り越すために西に向かって少しずつ高くなっており、2番から10番へは1.4m高くなっている。
この海域は干潟が多く浅いため、あえて浅海変形計算を行わず、波高はピーク直前の5時まで松合の海岸線に正対する南東寄りの波向であるため、波浪推算結果で示した八代海の最北部NO.1の波高・周期をそのまま与えた。
天文潮位は八代港の値を、潮位偏差は高潮計算結果を用いた。
うちあげ高は波高のピークよりもやや遅れ、それより潮位が高くなっている時期に最大となっている。
越波は波高のピークに合わせて最大になっている。天端高が高いところでは低いところよりも越波量が少なくなっている。
|