|
4.3 松合地区の波浪
宇城市不知火町松合地区周辺の地形図を図4-3-1に示す。松合地区は八代海の北東端にあるため、東側約4kmは水深5m未満あるいは干潟で、南東側1.5km対岸は干拓地である。海面が開けていてフェッチが大きい方向は南西方向である。したがって、浸水への影響の大きい規模の越波やうちあげ高を考慮する場合、高波が想定される方向としては、波浪推算による波高変化がピーク時で波向が南西方向であることを合わせて考慮すると南西方向となる。
図4-3-1 不知火町松合地区周辺図(○で囲まれた部分が松合地区)
| (国土地理院25000万分の1地図画像を地形図表示ソフトKashmirで加工) |
松合地区では一部の護岸外側に沖側に突出した漁港防波堤があるため、越波が考えられるのは防波堤の東側である。ただここに到達する波は防波堤の影になるため、回折や屈折を考えなければならない。そこで沖合から南西方向からの波浪を与えるために、松合の沖合と護岸近くの波高変化を、事前にエネルギー平衡方程式による浅海変形計算を行って評価した。松合沖合の推算波浪のピーク付近の周期が6秒前後であることを考慮し、有義波高2m・周期6秒の場合の浅海変形計算を行った結果を図4-3-2に示す。
| 図4-3-2 |
松合周辺の波浪の浅海変形計算結果
(波高2m,周期6秒,波向SW) |
| (拡大画面:41KB) |
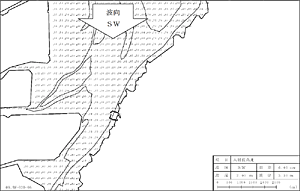 |
|
浅海変形計算結果によると、計算領域入力地点(浅海変形計算出発点)との波高比は、防波堤の影響を受けないところで0.28、防波堤の影になるところで0.15なので、3.1節で得られた松合沖合の推算波高に、この護岸前と沖合との波高比の比0.15/0.28=0.54を乗じた値を松合地区護岸前面の波高とする。波高ピーク時以外の時間帯では、波高が下がり周期が短くなり回折係数が小さくなり、護岸前と沖合の波高比はこれよりも小さくなると考えられるため、危険側に考えて同じ値をそのまま使う。また、護岸前の波向も危険側に考えて護岸に直角の方向とする。これによって、ピーク前後以外は波高は高めに評価される。
|