|
4・4 接地工事要領
船舶における接地はアース又はグランドともいわれ、船舶に装備されている電気機器や無線機器等と船体とを同電位にすることであり、人体に対する危険防止や火災防止あるいは静電気対策等のほか、GMDSS機器の場合には、電気的ノイズを防止するための接地が重要となってくる。
このノイズ対策としての接地は、感電防止や静電気対策あるいは雷対策等のための接地とは異なり、単純に接地すればよいというものではなく、ノイズの性質や侵入経路及び誘導のメカニズム等をよく見極めて、効率的に減少し除去するよう施工する必要がある。
このノイズの種類や除去対策についは、第3章3・3・4・(3)項に詳説してあるので、同項を 参照されたい。
接地接続は、金属器機の場合に取付けボルトを利用して金属船体に接地する自然接地方法と、機器(またはケーブル)と金属船体間を接地線または接地銅体を用いて行われなければならない。(表4・9参照)
| 表4・9 |
接地導体の大きさ及び接地接続(lEC 92-401: 1980) |
| 導電部導体断面積 |
銅製接地接続導体の最小断面積 |
| 3mm2以下 |
導電部導体断面積の100%。ただし、より線の場合最小1.5mm2、その他の場合最小3mm2。 |
| 3mm2を超え125mm2以下 |
導電部導体断面積の50%。(最小3mm2) |
| 125mm2を超えるもの |
64mm2 |
|
接地銅板は、厚さ0.3〜1.0mm、幅25〜60mmのものがメーカーより支給されるのでそれを使用する。
(1)GMDSS関連の各機器については、メーカーにより接地方法が指示されている場合にはその方法で行う。
(2)機器の取付けは、必ず船体構造部若しくは船体付の取付け金物に取付け、接地は機器取付けボルトかあるいは専用の接地用金物を設けて、これに専用接地線で接続する。(図4・84参照)
また、機器の箱体は、操作のため必ず人体と接触するので、感電防止上からも接地は完全でなければならない。
(3)壁面等、絶縁物上に機器を取付ける場合には、接地用金物を鉄構造部に溶接し、これに専用接地線で接続する。(図4・85参照)
(イ)インマルサット船内装置メインユニットの接地例を図4・86に示す。
図4・84
図4・85
図4・86 インマルサット船内装置メインユニットの接地(例)
(ロ)本体(MF/HF設備)の接地例を図4・87に示す。
装置本体のアース銅板をアースボルトに取付ける。
図4・87 本体(MF/HF無線設備)の接地
|
(拡大画面:29KB)
|
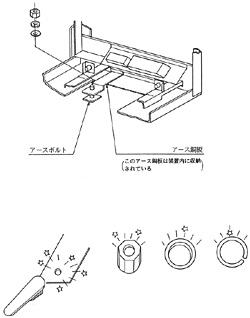 |
|
注)アース板・アースボルトの接触面のさびとペンキは落とすこと。
|
(4)接地用金物は、他の電子機器と共用しないこと。(図4・88参照)
図4・88
(5)FRP船や木造船では、必ず接地板に接地すること。この場合、船体に取付けられている接地銅板までの接地導線としては少なくとも幅100mm以上の銅板を使って、接地銅板から機器付近まで配線することが必要である。また、他接地銅板は定尺(1,200mm×365mm)の4分の1程度以上の大きさが必要で、無線機器専用とすること。
(6)接地線は、他の電子機器と共用はしないこと。
|