|
7. 船体・機関計画保全検査の方法(案)
7.1 船体計画保全検査の方法(案)の検討
前章までの調査結果を踏まえ、船体計画保全検査の方法案を作成した。
この際、15年度調査において要検討事項として掲げていた点については、概略次のようにまとめ、今回作成した方法案に盛り込むこととした。なお、これらの考え方の詳細は、次章の検査の方法の解説案を 参照されたい。
(1)適用対象船舶
建造後15年未満の内航旅客船であって、普通構造のものを対象とした。すなわち、軽構造船、双胴船等、特殊な構造の船舶は対象外とした。なお、受検者のニーズを考慮して、航行区域、総トン数、船長、速力に基づく対象船舶の限定は行わないこととした。
(2)対象とする検査
入渠を省略できる検査は、特1中検査以外の第1種中間検査(ただし、新造後初めての第1種中間検査を除く。)とした。すなわち、定期検査及び特1中検査においては、現状の検査官の立会による入渠検査方式を適用する。
(3)対象とする検査項目
入渠時でないと視認できない船底、船側外板、舵、錨、錨鎖、喫水線下の弁等をすべて含むこととした。
(4)船体計画保全検査方式の承認基準
機関計画保全検査方式に準じ、具体的な承認基準案を規定した。この際、現行の機関計画保全検査で必ずしも明確でない点を整理、明確化した。
なお、昨年度調査において、新方式導入後当分の間は、定期検査及び特1中検査における入渠を含め、5年間に4回以上の入渠が行われること(入渠間隔は18ヶ月を超えないこと)を標準とするとの考え方を示していた。しかしながら、今回実施した旅客船事業者へのアンケート結果等から、事業者は2年間隔での入渠を希望していること、また、機関整備の必要性等からそれ以上の延長を不用意に目指すことは想定しづらいことなども踏まえ、利便性・弾力性に欠ける制度設計を避けるため、上記のような制限は設定しないこととした。
(5)検査の実施方法等
定期的検査時等において検査官により事業者の自主点検記録の確認等を行うことにより、検査を実施することとした。
なお、昨年度調査において、定期的検査時以外の時期に入渠する場合は、「前回の定期的検査時において臨時検査を指定する」等の案を示していたが、優良・適切な保守管理能力を有する事業者の自主管理に委ねるという計画保全検査制度の趣旨が不明確となるとともに、事業者の利便性を損なうことになるため、当該運用は盛り込まないこととした。なお、「必要に応じ、船舶安全法第12条根拠の立入検査を実施する」ことについては、検査の方法上明示しなくても、必要があれば、随時実施することは可能。
船体計画保全検査の方法案の検討の過程で明らかとなった現行機関計画保全検査の方法における要改善事項の解消のため、機関計画保全検査の方法の改正案を併せて作成した。
改正の考え方の詳細は、次章の検査の方法の解説案を 参照されたい。
添付資料として、現行の機関計画保全検査の方法、同改正案、船体計画保全検査の方法案を対照表形式で示す。
計画保全検査(船体/機関)対照表
|
(拡大画面:583KB)
|
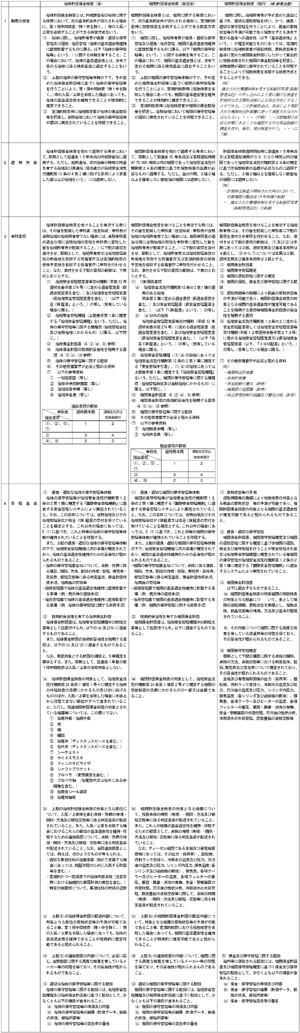 |
|
(拡大画面:427KB)
|
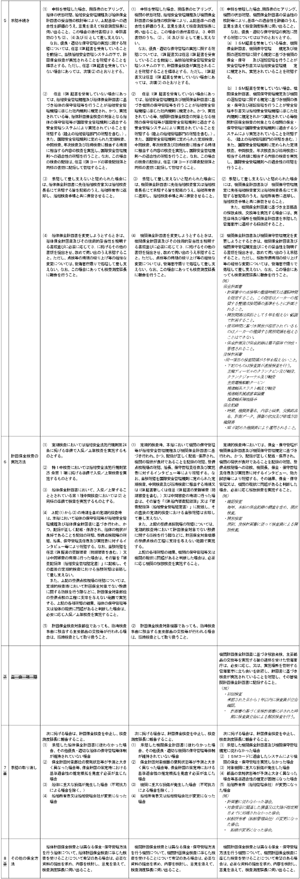 |
|