|
はしがき
本報告書は、日本財団の平成16年度助成事業「船舶関係諸基準に関する調査研究」の一環としてRR-R3原子燃料物質の海上輸送の安全性に関する調査検討会において実施した「原子炉解体廃棄物海上輸送時の安全基準の検討(その1)」の結果をとりまとめたものである。
RR--R3原子燃料物質の海上輸送の安全性に関する調査検討会 委員名簿(敬称略、順不同)
委員長 有冨正憲(東京工業大学)
委員 木倉宏成(東京工業大学) 遠藤久芳(海上技術安全研究所)
小田野直光(海上技術安全研究所) 時繁哲治(日本海事協会)
尾崎幸男(電力中央研究所) 本庄三郎(日本海事検定協会)
林 昭宏(電気事業連合会) 石倉 武(原子力発電技術機構)
柴田 寛 (核燃料サイクル開発機構) 横田浩明(三井造船)
丸岡邦男(三菱重工業) 北村 欧(三菱重工業)
鈴木 浩(三菱総合研究所) 広瀬 誠(原燃輸送)
志村重孝(オ・シー・エル) 三浦広志(上組)
(河野 晃(原燃船舶)) 青木健作(原燃船舶)
(石井光雄(日本原子力発電)) 苅込 敏(日本原子力発電)
林 俊明(東京電力) 藤原啓司(東京電力)
須田昭一(中部電力) (加藤眞也(関西電力))
森本 恵次(関西電力)
関係官庁 (峰本健正(検査測度課)) 高橋 治(検査測度課)
(小芝輝好(検査測度課)) 小柳康一(検査測度課)
(藤田建雄(検査測度課)) 後野和彦(検査測度課)
斉藤敏夫(経済産業省 原子力保安院)
(神志那正幸(総合政策局 技術安全課) 甲斐健太郎(総合政策局 技術安全課)
事務局 前中 浩(日本造船研究協会)
注:( )内は前任者を示す
1. はじめに
国際原子力機関(IAEA)で策定された放射性物質安全輸送規則(TS-R-1)は、危険物輸送のモデル規則である「危険物輸送に関する国連勧告」(オレンジブック)に取り入れられ、さらに輸送モードごとに国際海事機関(IMO)、国際民間航空機関(ICAO)等による検討を経て、国際機関別の輸送規則として発行されている。海上輸送の場合はSOLAS条約に定められた国際海上危険物規定(IMDGコード)がその役割を担っている。我が国は、使用済燃料、高レベル放射性廃棄物及び原子燃料物質等を船舶により輸送する「輸送国」であるが、危険物船舶運送及び貯蔵規則にIMDGコードを取り入れることにより国際整合を図りつつ、海上輸送の安全確保を図っている。
英国、米国、仏国及び独国において原子炉解体に伴う放射性廃棄物の安全輸送に係る法規制のあり方について検討が進められており、IAEAの場で輸送規則の改定案が提示される可能性が高い。一方、我が国では、これまで原子炉解体に伴う放射性廃棄物の海上輸送の安全性に係る法規制や技術基準のあり方について議論されていない。
このような背景の下に、(社)日本造船研究協会は平成16年度から「原子燃料物質の海上輸送の安全性に関する調査検討会(RR-R3)」を組織し、平成16年度と平成17年度の2年間の計画で、将来実施することが計画されている原子炉解体に伴う放射性物質の海上輸送の安全性に関して、IAEAやIMOへの輸送規則の改定案を策定し、改定案の対処方針策を整理するとともに海上輸送の安全性を確立するために必要な技術基準のあり方を検討して、海上輸送の安全確保に関する技術基準の作成に資する技術調査研究を実施している。
本報告書は、下記の2つの課題から構成されている。
(1)解体廃棄物輸送の法規制の検討
はじめに、我が国の原子炉の解体で生じる放射性廃棄物について、現状考えられている仕様を明らかにするとともに、具体例として日本原子力発電(株)東海原子力発電所の解体放射性廃棄物の仕様を調べた。これらの廃棄物のうちから、解体スケジュール等を考慮して、当面の検討対象としてL1廃棄物を選定した。次に、国際原子力機関(IAEA)輸送規則及び輸送モード規則である国際海事機関(IMO)の国際海上危険物規定(IMDGコード)、照射済燃料などの(INF)コード、並びに、それらが取り入れられた我が国の輸送関連規則について、解体廃棄物輸送に係るものを摘出し、これらで規定された条項について、改定の動向とこれまでの対応についてまとめた。最後に、解体廃棄物輸送に関連する国内外の輸送関係規則について、解体廃棄物の安全かつ合理的な輸送を実現するための課題を摘出し、改定等の提案をまとめた。
(2)解体廃棄物輸送時の事故シナリオ及び環境影響評価の検討
解体廃棄物輸送時の安全要件に関する技術基準の作成の基礎データを取得するため、はじめに我が国で想定される解体放射性廃棄物の海上輸送時の様態に基づき、それらを包絡する保守的な仮定に基づき事故シナリオを作成した。次に、作成した事故シナリオに基づき、妥当と考えられる輸送物の状態、海象・気象、地理的条件等を設定して環境影響評価を行い、一般公衆等の被ばく量を算定した。その結果、極めて保守的な仮定に基づいても、一般公衆に与える放射線学上のリスクは無視できるほど小さいことがわかった。
実施スケジュールは下記の表のとおりである。
表1 実施スケジュール
2.1 解体廃棄物について
2.1.1 原子炉解体廃棄物仕様
2.1.1.1 軽水型原子力発電所解体廃棄物
(1)解体廃棄物
原子力発電所の廃止措置とは、図2.1.1-1に示すように運転終了した原子力発電所を放射線管理を要しない状態とするためのプロセスとその管理である。我が国では、廃止措置の方式としては安全貯蔵後に解体撤去することを考えており、安全貯蔵期間としては5〜10年を想定している。
原子力発電所を解体撤去する際には解体廃棄物が発生するが、その廃棄物は次のように分類される。
・低レベル放射性廃棄物(放射性物質として扱う必要があるもの)
・放射性物質として扱う必要のない物(クリアランスレベル以下のもの)
・放射性廃棄物でない廃棄物
さらに、低レベル放射性廃棄物は次のように区分されている(図2.1.1-2参照)。
・放射能レベルの比較的高い低レベル*廃棄物:L1廃棄物
・放射能レベルの比較的低い低レベル*廃棄物:L2廃棄物
・放射能レベルの極めて低い低レベル*廃棄物:L3廃棄物
注*)「低レベル」は省略することがある。
なお、これらの呼称は埋設計画を検討する上で便宜的に用いられている仮称である。一般化した統一呼称は現在、(社)日本原子力学会等で検討中であるため、本報告書ではこれら仮称を用いることとする。
原子力発電所設備におけるこれらの廃棄物の発生場所を、BWR発電所について図2.1.1-3に、PWR発電所について図2.1.1-4に示す。
また、軽水炉型原子力発電所の解体における廃棄物の発生量の試算例を表2.1.1-1に示す。廃棄物のうち、放射性廃棄物として扱う必要のない廃棄物がほとんど(98〜99%)であり、比較的又は極めて放射能レベルの低い放射性廃棄物が2%程度以下、放射能レベルの比較的高い放射性廃棄物であるL1廃棄物が100〜200トン程度である。運転中に発生するものも含め、L1廃棄物に区分される放射性廃棄物の放射能レベルを表2.1.1-2に示す。
(2)解体廃棄物処分/輸送容器
解体廃棄物のうちの低レベル放射性廃棄物は原子力発電所から搬出され埋設サイトで処分される。このため、廃棄物の種類によっては処分容器が必要となり、また、原子力発電所から埋設サイトまでの輸送には輸送容器が必要である。
輸送容器としては、放射能レベルが比較的高い場合には遮へいを有するB型容器、比較的低い場合にはB型やA型の容器が用いられる。極めてレベルの低い場合には、L型輸送物としてフレキシブルコンテナの使用も可能である。これらの容器と必要数の概念を表2.1.1-3に示す。
なお、原子炉圧力容器や蒸気発生器のような大型機器を裁断せずそのまま輸送することや、配管やダクトを密封容器としてコンテナ等に充填して輸送することも考えられている。
図2.1.1-1 原子力発電所の廃止措置
| 出典:総合エネルギー調査会総合部会報告書(昭和60年) |
図2.1.1-2 発電所から発生する廃棄物の区分
図2.1.1-3 原子力発電所の解体で発生する廃棄物(BWR)
|
(拡大画面:87KB)
|
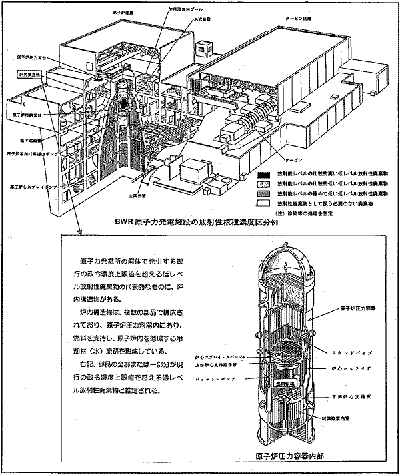 |
| (出典) |
原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会「現行の政令濃度上限値を超える低レベル放射性廃棄物処分の基本的考え方について」平成10年10月16日 |
|