|
―素敵な話の道しるべ(84)―
見られている私・見ている私
嘉悦大学短期大学部助教授 古閑 博美
服装への注目
幼稚園の教員資格を取得するために、教育実習に行ったときのことです。毎日着る洋服もおろそかにできないと、つぎのような服装プランを立てました。
(1)社会人としてふさわしい
(2)働きやすく動きやすい
(3)明色で安全性に配慮する
(4)清潔でオシャレ
実習生といっても、園児たちは「先生」と呼んでくれるわけですから、それにふさわしい服装が肝心です。働きやすく動きやすいとは、遊んだり抱きついてきたりする園児たちを躊躇なく受け止めたり指導の先生方の指示にすぐ対応したりできるように、明色で安全なとは、明るい気分で園児たちと接し、彼らと触れ合うさいに怪我をさせたりしないように色やデザイン、素材に配慮したものをいいます。清潔でオシャレとは、実用的観点もさることながら園児の目に映る自分の姿が好ましいようにと考えました。
ある日、お気に入りの、ブルーの縦縞が入ったワイシャツに同色のリボンを胸元に結んで園に行ったところ、翌日、何人かの女児が胸元にリボンを結んで登園してきたのには、本当に驚きました。彼女たちの観察眼や感性、真似る行為の積極性を見て「園児恐るべし。侮れず」と思った記憶は今も薄れることがありません。「園児たちは私(自分が接する相手)を見ている」と思った強烈な体験でした。
オシャレをしたいという気持ちのなかには、自分のためということもありますが、誰か特定の人に見られるのを想定していることが少なくありません。服装は、社会的記号としても自己表現するうえでもおろそかにできません。園児たちのためにオシャレし、彼らにとって好ましい自分でありたいと思いながら教育実習に通った日々を振り返ると、そんな私を素直に受けとめてくれた園児たちのことがいつも思い出されます。
「見られている自分」と「もうひとりの自分」
航空会社に入社し、客室乗員訓練生であったとき、教官が常に言っていたのは「お客様から見られていることを忘れないで」というものです。このことばは、化粧や髪型、服装といった外見を言うだけでなく、振る舞いやことば遣いなどをふくめてのことですが、最初耳にしたときは、乗員は女優でもモデルでもないのにと思ったり、見られている自分を意識せよなんて自意識過剰の人のすることではないかと思ったりしたものです。
「訓練生」の肩書きがとれて晴れて乗員になると、乗客をはじめ空港内を歩いているときにも不特定多数の人から見られている自分を意識するようになりました。とはいえ、「見られている私」を意識するとはどういうことか、その答えは簡単ではありませんでした。次第に、それを意識する自分がいなくなって自然な態度で振る舞い、そして、そのような自分を相手が自然に受け入れてくれるようなら、それはよい接客態度と言えるのではなかろうかと思うようになりました。
その昔、中学生になった私に、父は「自分を見るもうひとりの自分を持ちなさい」ということばを贈ってくれました。それは、何かをしようとしたり発言しようとしたりするときは一呼吸おいて落ち着いて行動しなさい、という意味であり、自分の言動を冷静に見るもうひとりの自分を持ちなさいという、粗忽者の娘に対する戒めのことばでした。
しかし、父の思いの込められたことばを右から左へと聞き流した結果は、そののちわが身に返ってくることになります。成長するにしたがい何度も挫折を経験しましたが、そのつど、このことばがよみがえり、反省とともに噛み締めたものです。自分を見つめるもうひとりの自分は甘かったり辛かったりいろいろですが、客観的に自分にささやきかける声を無視したりすると痛い目にあうのは今も変わりません。
学習時の態度
教壇に立つ人のなかにも、一日中、ジャージで過ごす人がいたり、学生との垣根を取っ払うといって短パンとTシャツで授業したりする人を見たこともあります。
『武士の娘』に明治期の六歳の女児が学習する風景が書かれています。この本は、外国人に日本を紹介する観点から執筆されました。
当時、女の子が漢籍を学ぶということは、ごく稀なことでありましたので、私が勉強したものは男の子むきのものばかりでした。最初に学んだものは、四書――即ち大学、中庸、論語、孟子でした。当時僅か六歳の私がこの難しい書物を理解できなかったことはいうまでもないことでございます。私の頭の中には、唯たくさんの言葉が一杯になっているばかりでした。もちろんこの言葉の蔭には立派な思想が秘められていたのでしょうが、当時の私には何の意味もありませんでした。時に、なまなか判ったような気がして、お師匠さまに意味をお尋ね致しますと、先生はきまって、「よく考えていれば、自然に言葉がほぐれて意味がわかってまいります」とか「百読自ら(おのずから)其の意を解す」とかお答えになりました。ある時「まだまだ幼いのですから、この書の深い意味を理解しようとなさるのは分を超えます」とおっしゃいました。(中略)このお師匠さまは四書を教えて下さるにも、仏教を説く時と全く同じに、恭しい態度をもってせられ、肉体の安逸ということを一切避けておられました。辞退なさりながらも、教授の間だけは、女中のすすめたお座布団に坐っておられました。これというのも、師は弟子より一段上に席をとらねば、師弟両方とも礼をなみすることとされていましたので、無理にお願いしていたわけでございます。お稽古の二時間のあいだ、お師匠さまは手と唇を動かす外は、身動き一つなさいませんでした。私もまた、畳の上に正しく坐ったまま、微動だもゆるされなかったものでございます。唯一度、私が体を動かしたことがありました。丁度、お稽古の最中でした。どうしたわけでしたか、落ち着かなかったものですから、ほんの少し体を傾けて、曲げていた膝を一寸ゆるめたのです。すると、お師匠さまのお顔にかすかな驚きの表情が浮び、やがて静かに本を閉じ、きびしい態度ながら、やさしく「お嬢さま、そんな気持ちで勉強はできません。お部屋にひきとって、お考えになられた方がよいと存じます」とおっしゃいました。
(『武士の娘』杉本鉞子著・大岩美代訳、三一〜三二頁、筑摩叢書九七、一九六七年)
時代が違う、と言えばそれまでですが、そう一言で片付けられないものをこの文章に感じるのです。動物には、「刷込み」という学習があることが知られています。これは「鳥類や哺乳類のごく早い時期に起こる特殊な学習」(大辞林)であり、一生持続します。「三つ子の魂百まで」(諺)といいますが、人間の目や耳、口、手など、身体が情報として入手するものは計り知れません。
誰のなかにも、なにものかに「見られている私」を意識する自分と、なにものかを「見ている私」を意識する自分がいます。どんなことばや態度に接するかは、その人の一生を左右する事柄となります。幼少時より、よい出会いが望まれるゆえんです。
写真・もとしろ保育園
環境にやさしい保育所給食
―平成十五年版環境白書を中心に―
武蔵丘短期大学学長 実践女子大学名誉教授 藤沢 良知
はじめに
最近の私達の生活は大量生産・大量消費、大量廃棄型社会となり、生活は便利になり、生活水準は向上しているものの、エネルギーや資源が大量消費され、廃棄物が増加し地球環境に大きな負荷を与えている。
当然、エネルギー消費が増大すると、二酸化炭素の増加につながり、また使用される物や資源は、最終的には廃棄物として、地球温暖化をはじめ地球環境に大きな影響を与えることになる。
また、食料ロスも大きい。供給される食料のうち、エネルギー計算で約四分の一に当たる量は食べられずに廃棄されている。
保育所給食は小規模とはいえ、大量の食品を扱うので環境にやさしい、食品購入、調理・廃棄物の処理、洗剤の使い方・リサイクル等のあり方が問われている。食育の視点からの幼児教育も大切である。
次に環境白書を中心に、環境にやさしい給食上の配慮等を考えてみたい。
一、新しいライフスタイル
最近は環境問題に対する一人ひとりの意識変化を背景に新しいライフスタイルが提案され実践され始めている。
新しいライフスタイルとは
(1)物の豊かさから心の豊かさへ
(2)地球環境は無限なものから有限なものへ
(3)商品は量から質へ
(4)環境に配慮した生活は、質素から、おしゃれで、かっこ良い
このような配慮が持続可能な社会の構築に向けた新しいライフスタイルとして、個々人の発想の転換が求められている。
図1は、国民生活に関する世論調査の結果で、昭和五〇年代中頃から、国民意識は物の豊かさから、心の豊かさを求めている人の割合が年々増加していることを示している。
図1 物の豊かさか心の豊かさか
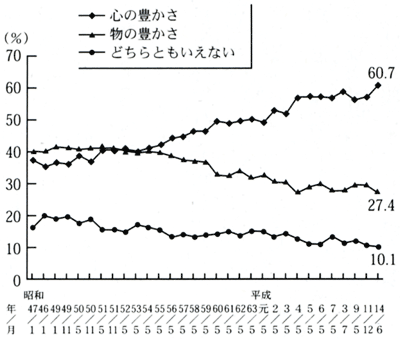 |
注:心の豊かさ:「物質的にある程度豊かになったので、これからは心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい」
物の豊かさ:「まだまだ物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたい」
出典:内閣府「国民生活に関する世論調査」
(平成14年6月)
|
二、シンプルライフで心の豊かさを
近頃は、シンプルライフという言葉が、ぜい沢で物質的に恵まれた生活に対して、心の豊かさを取り戻すためのライフスタイルとして広がりをみせている。具体的には
(1)単なる物の節約ではなく、吟味したものに囲まれて生活する。
(2)安いから買うのでなく、環境への配慮や長期間にわたって使用する可能性などを考えて購入する。
(3)修理やリサイクル等で、資源を大切にし手をかけた生活をする。
等の生活像が提案されている。こうしたライフスタイルは、必要な物だけを買い、長く使うといったことに加えて、日常生活全体からの環境負荷の低減を図るものである。
シンプルライフ志向のライフスタイルは、単なる節約や質素ではなく、時代に合った「おしゃれでかっこいい」といった観点からとらえていくことの大切さを白書は指摘している。
シンプルライフ志向の食生活では、給食の献立を考え、食品購入する時も、調理する時も、食べ物を大切にする心を持つとともに、地球環境にやさしいエコクッキング運動を積極的に進めたいものである。
三、保育所とエコ・クッキング
子どもの時から物を大切にする心を育て、限りある資源・エネルギーを効率的に活用し、使い捨て社会を見直すことが大切である。
例えば、最近プラスチック製品や容器・包装が増えているが「プラスチックって何?」「原料はどのようにして作られているの?」「燃やすとどうなるの?」「最後はどこに捨てられるの?」といったテーマからも、子どもたちの環境に対する意識を深めていくことができよう。
また、海に捨てられたプラスチックを、魚がえさと間違って飲んだり、体にまとわりついたりして海の魚も大きな被害を受けていることなど、身近なプラスチックの話題一つをとっても環境問題は大きな学習テーマである。
もとより幼児は、理解力が十分でないため多くは望めないが、調理保育等を通じて、料理の下ごしらえやつくり方の体験、盛りつけ、配膳、食事をそろって楽しく食べる、食後の片付けなどを体験させ、食品の名前を覚えたり、残食しない、環境にやさしいエコクッキングの心も身につくよう心掛けたいものである。
また、保育所に堆肥専用コンポストを設置し、残飯や厨芥で堆肥をつくり、自家菜園や花壇の肥料として活用するなどといったことも、幼児期のうちから体験させてあげたいものである。
四、スローフード運動
スローフード運動は、一九八六年イタリアのブラという町で始まった現代人の食生活を見直す運動である。この運動は
(1)消えゆくおそれのある伝統的な食材や料理、質の良い食品を守る。
(2)質の良い食材を提供する、中小の農業者を守る。
(3)子ども達を含め、消費者に“食”や“味”の教育をすすめる。
この三つを指針に掲げ、各地の食文化を尊重して将来に伝えていこうとする取り組みである。わが国でもスローフード運動に取り組む団体が設立され活動しているが、世界では三八か国、一二三都市で約七万人以上の会員を集めて活動しているNPO活動である。
わが国では、古くから地域の特色ある食材や文化を活かした郷土食があり、各地で自然を活かしたスローフード運動が実践されてきた。
しかし最近は食料品の海外依存度が高まりつつあることや、食材の季節性(旬)が希薄化し、全国的な食事や味の画一化が進んできている。
同時に野菜など旬を外して収穫するため、温室栽培やハウス栽培によるエネルギー消費の増大、工場で大量に作られた食材を遠くの消費地に輸送するため、環境負荷を高めているのが実態である。
これからも郷土食や地域の食材をいかに活かした保育所給食をすすめるか、献立づくりを工夫するとともに、地産地消といわれるように、地域で生産される野菜、果物、水産物など給食に取り入れる工夫が大切である。
五、フード・マイレージ
イギリスの消費者運動家ティム・ラングは食料の生産地から食卓までの距離に着目して、なるべく近くで採れる食料を食べる方が、輸送に伴う環境負荷が少なくなるという考えにたって、平成六年にフード・マイルという概念を提唱した。
この考えで輸入食料品についてフード・マイレージという指標を用いて試算すると、日本のフード・マイレージは四〇〇〇トン・kmであるのに対し、韓国は三二〇〇トン・km、アメリカは三〇〇トン・kmとなっており、人口一人当りでみると、日本の食料は韓国の約一・二倍、アメリカの約八倍の環境負荷を与えていることになる。
わが国は食料自給率がエネルギー比で計算すると四〇%で、六割もの食料を外国から輸入しているもので、環境負荷は他の国に比べて大きいのである。
近年、食料品や各種製品の生産・流通・消費・廃棄(リサイクル)までに使われるエネルギーや環境に与える負荷を客観的・定量的に評価するライフサイクル・アセスメントという手法の活用が進められるようになった。
私達が給食で使用する食材一つをとっても生産地はどこか、温室栽培か露地栽培か、地産地消といった環境にやさしい配慮がなされているかなど、ライフサイクルアセスメントの発想で給食をすすめたいものである。
図2 一人ひとりの取組の普及
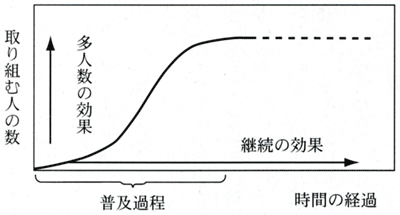 |
|
資料:環境省
|
|