|
(3)まとめ
後方散乱強度値から画像処理によって分類する方法及び後方散乱強度分布モデルから海底面の凹凸と底質を推定する方法の2つについて、論文・資料の収集及び整理を実施した。画像処理による分類法については、近年のリモートセンシング画像処理では、人工知能による学習型の分類が行われており、数多くの基礎データがあれば、海洋においても有効な手段である。
一方、後方散乱強度分布モデルを用いた底質と凹凸の推定は、近年、より複雑化されている。これは陸上のリモートセンシングでもそうであるが、実海域で収録された基礎データが蓄積され、解析技術が進むにつれて、より複雑なモデルとの組み合わせが必要となるからである。また陸上のリモートセンシングでは、異なる波長を用いた観測が一般的であるが、海洋においては、複数の周波数を用いて海底面を探査する機会があまり得られていない。図50は、海洋において数少ない周波数の違いによる海底の散乱特性の違いを示している。
|
図50.
|
周波数の違いによる画像の違い(同じ泥火山を捉えたもので同範囲の画像)
|
(a)100kHz
(b)12kHz
図は同じ泥火山を捉えたもので、周波数は100kHzと12kHzである。波長が異なるため、両者は全く違ったイメージとなる。このような複数の波長を用いた海底面探査は、海底面における散乱特性が異なるため、実海域におけるデータの蓄積が進めば、底質分類においても極めて有効な手段である。
2.2.1.2 衛星による地表探査と画像データの分類方法
衛星を用いた地表探査法とリモートセンシング画像データを用いた分類方法を紹介する。
(1)リモートセンシング
リモートセンシングとは、航空機や人工衛星から地球表面や大気で放射、散乱、反射した種々の電磁波を計測し、それを地球資源や地球環境の観測、評価、管理などに役立てる技術の総称であり、これを利用して、地質学、雪氷学などに利用されている。また常時雲に覆われている金星の観測にも利用されている。
リモートセンシングによる電磁波の観測から、地表あるいは海洋の対象物や現象を判読・解析できるのは、「すべての物体は、種類および環境条件が異なれば、異なる電磁波の反射または放射特性を有する」という物体の電磁波特性に基づいている。つまり、物体から反射または放射される電磁波の固有性に着目し、電磁波を観測して、物体の識別やその環境条件を把握する技術がリモートセンシングである。
図51はリモートセンシングによる観測概念図である。上空または宇宙から地球を観測するため、広域の情報を同時に、また人工衛星の場合は周期的に収集することができる。特に衛星を用いたリモートセンシングは、刻々と変化する全球的な現象の把握ができるため、今日では、地球環境の解明に不可欠な観測手段となっている。
図51. リモートセンシングの観測概念
リモートセンシングでは、さまざまな電磁波に感度をもつセンサーによる電磁波計測を観測手段としている。センサーは人間でいえば目であるが、人間の感覚は、電磁波の中でもごく一部の可視光領域の波長しか感じることができない。また、人間が視覚的に得ている情報は、主として観測対象の空間的な形状と分布に関するものである。これに対してリモートセンシングでは、可視光領域に限らず、いろいろな波長域の電磁波を利用しており、人間の目では認識できない地表や海面などのさまざまな現象の把握が可能となっている。
(1)レーダの特徴
(a)速度
レーダは電磁波(横波)を媒質として使用しており、ソナーは水中超音波(縦波;粗密波)を媒質として使用している。媒質の伝搬速度は、電磁波が約3×108m/sであり、水中音波は約1.5×103m/sである。したがって両者には2×105の差異がある。これは、レーダは極めて高いデータレートを実現できるのに対して、水中音波ではデータレートが極めて低いことの要因となっており、他方では、水中音波では実時間で様々な信号処理を行う時間的ゆとりを持つという結果となっている。
(b)偏波
音波と異なり、電波には偏波がある。偏波とは、電波が特定の振動方向を持っている状態を指す。電界の波が地面に対して水平方向に振動しているものを「水平偏波」、垂直方向に振動しているものを「垂直偏波」と呼ぶ。HHというのは地表面に対して、「水平に偏波したマイクロ波を」を発信し、後方散乱波の「水平偏波成分」のみを受信することを指す。またVVというのは、「垂直に偏波したマイクロ波を」を発信し、「垂直偏波成分」のみを受信することである。HVとVHは非常に類似しているので、通常同時には使用しない。HHまたはVVをライク偏波(平行偏波)と呼び、HVまたはVHをクロス偏波(直交偏波)と呼ぶ。単一波長のレーダにおいても、多偏波の観測を行うと、その偏波の散乱特性の差から地表のターゲットがさらに区別できるようになる。
(c)地表面における電磁波の相互作用
リモートセンシングは地表被覆物体と電磁波の相互作用を知り、間接的に地表の特性を知る技術である。地表にはさまざまな物体があり、それらの物体と電磁波の相互作用は極めて複雑であるが、その基本は反射、散乱、透過、吸収、放射である。
電磁波が媒質に入射とすると相互作用によって反射、散乱、透過、屈折、吸収が起こる。実際面では、土や構造物、湖水のように形状ならびに大きさの異なる多種多様な物体が対象となる。その相互作用は単純な場合もあり、また複雑な場合もある。さらに媒質との相互作用によって、入射電磁波は大きさ、方向、偏波、波長、位相などの影響を受ける。このような変化は大気中や地表物体中でも起こる。したがって、相互作用は媒質表面だけではなく、媒質の3次元的広がりにも関係したものである。
(d)特徴
レーダの長所には、以下がある。
・日照に独立
・雲や雨を透過
・植生や土壌に部分的に浸透
・能動的リモートセンシング・システム(自分で照射し、反射マイクロ波の位相と偏向を記録するシステム)
(2)電磁波の種類
リモートセンシングでは、通常、可視光から電磁波までの広範囲の波長の電磁波が、それぞれの目的に応じて使用されている。電磁波には、周波数(または波長)、伝搬方向、振幅および偏波面(偏向面)という4つの要素があり、波長が短いものから順にγ線、X線、紫外線、可視光線、赤外線、電波と呼ばれている。
図52は電磁波放射を波長、周波数の順に配列した電磁波スペクトルである。すべての放射に同一の反射、屈折の法則が適用できる。
図52. 電磁波の呼称とセンサー
(拡大画面:23KB) |
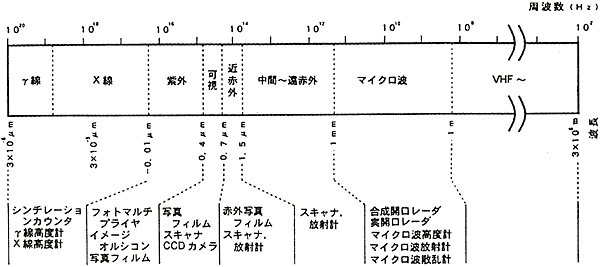 |
(a)γセン、X線
最も短波長側にあるγ線、X線は主に原子核と電子など電子軌道レベルの相互作用と関係した波長域である。この波長域の電磁波は、地下資源探査を目的として、放射線の1種であるγ線を航空機で観測する例以外用いられていない。
(b)紫外線
X線よりも少し波長の長い紫外線は、原子、分子との相互作用がその振る舞いの中心である。紫外線は大気中のオゾン(O3)に吸収されたり、酸化現象を促進したり、主として化学反応に関係する波長域である。アメリカのNASAでは紫外線強度を波長別に測定するセンサーを衛星に搭載し、オゾン層の長期観測を行っている。ただし、紫外線は大気中の透過率が低いため、一部の低高度の航空機を除き、地表観測を主目的とするリモートセンシングでは、ほとんど用いられていない。
(c)可視光線
紫外線に続く波長領域は、可視光線(波長0.4〜0.7μm)と呼ばれ、人間が視覚的に感ずることのできる電磁波の領域である。可視光線は、物質との光学的な相互作用および物質との化学的作用に大きな役割を演ずる。物質による光の反射、散乱や酸化物質の赤色化、葉緑素による青色・赤色光の吸収、水中の懸濁物質粒子による吸収、散乱などが可視光領域のリモートセンシングの中心的な情報である。
(d)赤外線
可視光線に隣接した長波長領域の電磁波を赤外線(波長0.7μm〜1mm)という。この中でとくに0.7〜1.3μm付近の電磁波を近赤外線と呼ぶ。近赤外線は主として水の分子と共鳴、吸収や葉中の植物細胞の微視的な構造との相互関係を示すものである。一般に植物の活性度が高いと近赤外線の反射が強くなるため、植生の調査に用いられる。
1.3〜3.0μm付近の電磁波は短波長赤外線と呼ばれ、観測波長帯としては可視光域にピークをもつ熱赤外放射の谷間に相当する。雪と雲の識別や、森林と草地の識別などに有用な波長域として知られている。
8.0〜14μm付近の電磁波は熱赤外と呼ばれる。般に常温の地表物体の熱放射は約10μmにピークをもっており、観測対象の温度を観測するのに、この波長領域が主な役割を果たすことからその名がある。
(e)マイクロ波
波長1mm〜1mの電磁波はマイクロ波と呼ばれている。この波長帯では10mm以上の波長でとくに大気による減衰が少なく、かつ雲や雨による減衰も小さいため、天候にかかわらず地表面を槻測することができる。マイクロ波センサーでは観測対象の周波数特性、偏波特性、後方散乱特性などを利用して、可視/近赤外センサーなどでは観測できないさまざまな物理量を測定することができる。マイクロ波には、波長によって表6に示すような呼称がつけられている。後述する合成開口レーダ(Synthetic Aperture Radar、以下SAR)は、このマイクロ波を用いたセンサーである。
表6. マイクロ波の呼称と波長、周波数領域
| バンド |
波長(mm) |
周波数(MHz) |
Ka
K
Ku
X
C
S
L
P |
7.5-11
11-16.7
16.7-24
24-37.5
37.5-75
75-150
150-300
300-1000 |
40000-26500
26500-18000
18000-12500
12500-8000
8000-4000
4000-2000
2000-1000
1000-300 |
|
Xバンドは、航空機搭載SARで、陸地調査に広く使われている。ほとんどの表面は粗くなり、人工物とか植生からの影響は、画像上ではっきり区別できない。Lバンドは、航空機及び衛星搭載SARで、地質学者が最もよく使っている。広範囲の表面の粗さの検出に有用である。Pバンドは、地質学的にはまだ応用されていないが、非常に乾いた砂の層のような表面物質を浸透する。植生からの体積散乱の増加が考えられている。
|