|
5・4・3 整備記録
「衛星航法装置 整備記録 様式:電装GPS」は、整備後の記録用として当協会が独自に作成したものである。船舶検査の方法等が制定された場合は、それに従うものとするが、それまではこの様式:電装GPSを使用してもよい。
衛星航法装置 整備記録
| ※測定困難な事項の記載を要しない。 |
(社)日本船舶電装協会 |
補足説明
1: 電源装置の代替電源の確認は有る場合のみ実施する。
2: 第1種GPSはディファレンシャル機能が備わっていれば必ずしもディファレンシャル受信機の装備を要しない。
3: 測位精度の計算
以下の様に定義する。
<アンテナ位置(緯度経度)の実測値>
Xr: 緯度の実測値、分単位
Yr: 経度の実測値、分単位
N: 全測位回数
<GPS受信機の(緯度経度)測位置>
Xn: 緯度の測位値、分単位 nは1からNまで
Yn: 経度の測位値、分単位 nは1からNまで
Xa=(ΣXn)/N 緯度の平均測位値、分単位 nは1からNまで
Ya=(ΣYn)/N 経度の平均測位値、分単位 nは1からNまで
ΔXn=(Xn-Xr)×1852 緯度の測位誤差、m単位 nは1からNまで
ΔYn=(Yn-Yr)×1852×cos(Xn×π/180)経度の測位誤差、m単位 nは1からNまで
但しこのXnのみ単位は度である。
とすると
直距離の測位誤差ΔLnは
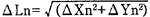 、m単位 nは1からNまで
ΔXa=(ΣΔXn)/N 緯度の平均測位誤差、m単位 nは1からNまで
ΔYa=(ΣΔXn)/N 経度の平均測位誤差、m単位 nは1からNまで
とすると
測位精度2drms(2 distance rout mean squared)は
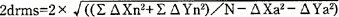 nは1からNまで
で計算される。 (計算式はNK測位精度証明試験基準に準ずる)
4: 測位精度判定基準
2種類の判定基準がある。
・良好測位確率:100回以上の測位データの個々の直距離の測位誤差ΔLnを計算し、測位精度判定基準以内に入っているデータの回数Gと全測定回数Nとの比率を求める。
95%以上であれば良好と判定。
・2drms: 前項注3の計算式より求めた95%誤差円の大きさが
GPSの場合は100m以内
DGPSの場合は10m以内
であれば良好と判定。
原則的には両方共満足していることを確認する。
但し、以下の場合にはその一方を省略できる。
明かに測位のばらつきが少ない場合は2drmsの計算を省略し、良好測位確率のみで判定しても差し支えない。
十分な精度をもって実測することができない場合は良好測位確率の意味が無いので、2dmsのみで判定しても差し支えない。
(社)日本船舶電装協会
第5章 練習問題
|