|
水田と水路の生きものを探ろう
(講師 守山 弘)
【講師紹介】
守山 弘
元 農水省農業環境技術研究所上席研究官、東京農業大学客員教授
主な経歴: |
1960年 |
東京教育大学理学部動物学科卒 |
1963年 |
同 化学科卒 |
1969年 |
東北大学大学院理学研究科博士課程修了 農林水産省蚕糸試験場研究員 |
1983年 |
農林水産省農業環境技術研究所研究室長 |
1995年 |
同 上席研究官 |
1998年 |
定年退職 ひきつづき同研究所非常勤研究員 |
2001年 |
独立行政法人 農業工学研究所非常勤研究員 東京農業大学客員教授 |
水田と水路の生きものを探ろう
水田の生き物の歴史
水田は生き物が豊富な場所である。その理由は日本の水辺がたどった歴史と関係がある。
水田は地形が平らで水が豊富な場所につくられる。日本は山が多いので、水田をつくるのに適した場所はおもに低地にある。しかし第三紀には、平らで水が豊富な環境は日本全体に広く存在していた。水田の生き物はこのころの水辺に棲んでいたものと共通している。
図1 |
大山田粘土層から産出した化石によって復元された大山田湖における食物連鎖
|
(琵琶湖自然史研究会『琵琶湖の自然史』282ページより引用)
(拡大画面:49KB) |
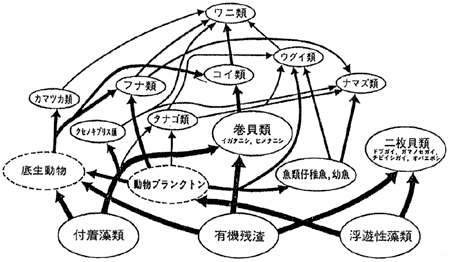 |
三重県上野市の近くの大山田の地層には、400万年前から320万年前にわたって存在した湖が眠っている。この湖は発見された場所にちなんで大山田湖と呼ばれている。大山田湖は琵琶湖の前身である。大山田湖から出土する化石をみると、タニシ、ドブガイ、コイ、フナ、ナマズ、タナゴなど、水田やため池の生物が多く含まれている(琵琶湖自然史研究会,1994、図1)。だから水田やため池の生物は第三紀のものと共通していることがわかる。
図2 河川の勾配
(水野・御勢『河川の生態学』より引用)
第四紀に入ると、日本はヒマラヤ山脈なみの大山脈になった。日本列島から海水を取り除いた山の高さは1万mを越すようになった。いっぽう日本列島の根本の幅は、太平洋側の深い場所(本州の日本海溝や南海トラフ)と日本海側の深い場所(日本海盆)のあいだで300〜400kmあるが、この幅はヒマラヤ山脈の幅(インド平原とチベット高原のあいだの幅)と同じである(貝塚・鎮西,1986)。山の高さが同じで根本の幅も同じだから日本はヒマラヤ山脈なみの大山脈ということができる。
図3 自然堤防と後背湿地
(貝塚ほか『日本の平野と海岸』46ページより引用)
ただヒマラヤ山脈との違いは、日本列島では、海水面が大山脈の七〜八合目付近にあり、陸地はそれより上になる点である。
当然そこを流れる川は急流になる。(図2)。この急流を日本海側では春に雪解け水が一度に流れ、太平洋側では梅雨明けから台風のシーズンにかけて大雨の水が流れ下るので、日本の川は洪水を起こしやすい。
第四紀になってからは火山も増え、大量の火山灰を生み出した。また第四紀になってから隆起した地質的に新しい山も、岩石が風化されやすいので多量の土砂の供給源となった。
その結果、川が洪水のたびに土砂を運び、広い氾濫原をつくった。洪水によって運ばれた土砂は河道の両脇に堆積して小高い場所をつくる。これを自然堤防という。土砂は河床にも溜って河床を高くする。そのため氾濫源の多くの場所は河床より低くなって湿地になる。これを後背湿地という(図3)。
第三紀の水辺に棲んでいたタニシ、ドブガイ、タナゴなどは、止水やゆるやかな流れでなければ生きられない。またコイ、フナ、ナマズなども稚魚の段階では流れがあると流されてしまう。これらの生き物は後背湿地を主な生活場所として生き延びたと考えられている。
氷河期には大陸から生物が移動してきた
第四紀には氷期が何度も地球を襲った。氷期には海水面が低下し、日本は大陸と陸つづきになった。そしてそのとき、大陸の生き物が移動してきた。
田圃で見かける緑と茶色の縞模様のカエルにトノサマガエルとダルマガエルがいる。トノサマガエルは南西日本から東北地方の日本海側にかけて広く分布するが、関東地方から仙台平野にかけては生息していない。ここに生息するこの型のカエルはダルマガエル(亜種トウキョウダルマガエル)である。またダルマガエルには東海から瀬戸内海沿岸にかけての地域に分布するグループがあり、こちらは亜種ダルマガエルと命名されている(図4)。
東日本のダルマガエルと西日本のダルマガエルが亜種の関係になっていることは、両地方のダルマガエルが交雑しなくなってから長い時間が経っていることを意味する。ダルマガエルは氷期に大陸から渡ってきたと考えられているので、その時期はたいへん古いということになる。
図4 各種カエルの分布
|
(前田憲男・松井正文『日本カエル図鑑』87,91,95ページより引用) |
(拡大画面:38KB) |
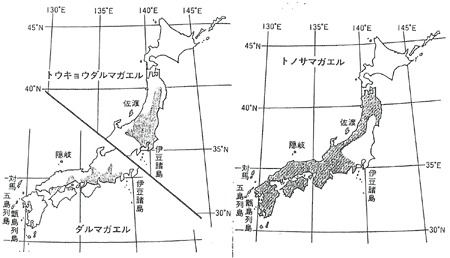 |
ところで水田に棲むカエルには、よく似た姿をしていながら分布域の違うカエルがほかにもある。ツチガエルとヌマガエルがそれで、ツチガエルが九州から東北北部まで広く分布しているのに対し、ヌマガエルは静岡以西にしか分布していない。この分布の仕方はダルマガエルとトノサマガエルのそれに似ている。ただトノサマガエルが日本海側を通って東北地方まで分布を広げているのに対し、ヌマガエルは温暖な気候を好むので静岡県以西にしか分布しない点が異なる。
Nishioka et al(1993)によると西日本のツチガエルと東日本のツチガエルは遺伝的に大きく離れていて、その離れた距離はトウキョウダルマガエルとダルマガエルの遺伝子距離(Nishioka et al,1992)よりも大きい。遺伝子距離は交雑しなくなってからの時間の長さと関係する。だからツチガエルは日本に入ってからの期間が長く、すでに東日本の個体群と西日本の個体群との間で亜種のレベルに達する分化が起こっているとみてよい。
これに対しヌマガエルの遺伝子距離は、台湾にすむ個体と日本にすむ個体の間では小さく(Nishioka and Sumida,1990)、トノサマガエルの遺伝子距離も、日本の個体と韓国の個体、北京の個体との間でこれと同じくらい小さい(Nishioka and Sumida,1992)。
これらのことから、ヌマガエルとトノサマガエルは、海外にすむ個体との間で交雑が行われなくなった後も、遺伝子分化がまだ起こっていないほど新しい時期に日本に入ってきたと考えられる。その時期は7万2千年前から1万年前まで続いた最終氷期(ウルム氷期)ということになる。
いっぽうツチガエルはダルマガエルと同様、亜種のレベルにまで分化するほどの古い時期に日本に入ってきたと想像できる。これに相当する氷期は24万年前から15万年前まで続いた氷期(ヨーロッパのリス氷期に当たる)である。
2つの氷期の間で起こった大きな出来事は、約8万年前に富士山が噴火し(貝塚・鎮西,1986)、西日本と東日本の間に富士・箱根火山帯ができたことである。富士山の噴火後に日本に入ってきたトノサマガエルやヌマガエルは、低地の水辺を住処にしていたのでこの火山帯を越えられず、関東平野には侵入できなかった。いっぽうダルマガエルやツチガエルは富士山が噴火する前に日本に入ってきたので、東日本にまで移動できた。そして日本に入ってきた時代の古さを反映し、ダルマガエルもツチガエルも国内で亜種のレベルにまで分化した。
ダルマガエルとトノサマガエル、ツチガエルとヌマガエルにみられる分布パターンの違いはこのように考えられる。
水田造成がもたらしたもの
約1万年前に最終氷期が終わると地球は温暖化しはじめ、海水面が上昇して日本は島になった。そして約6千年前には海水面は現在よりも数米も高くなり、河川の下流部は海になった。この時期を縄文海進期という。河川の下流部に侵入した海は上流から供給された土砂を受けとめ、平らな内海(干潟)をつくった。
縄文海進期が終り、海が退くと、いままで内海だった場所はつぎつぎと淡水の沼に変化していった。河川の上流部に逃げていた淡水魚たちは、この新たに出現した浅い止水環境に分布を広げたであろう。縄文晩期になると日本に稲作が導入される。縄文海退期が約5000年前、稲作導入が約2500年前のことだから、淡水生物にとって水田は自然環境に匹敵する史的時間を持つ環境だった。しかも稲作技術が日本に伝わったとき、水田はすでに淡水魚が生息できる構造になっていた。
例えば縄文晩期の福岡県板付遺跡では、住居・穴倉・墓地などのある微高地の西脇を幅2m,深さ1mの人工水路が走り、その西側に水田が拓かれている。また水路のなかには井堰と思われる杭列がみられ、水田の土手はその部分で折れ曲がって開口部となっている。この部分が水田の取排水口とみられる(図5;工楽,1991)。このような構造なら多くの魚が水路から水田に入ることができる。
水田遺構は弥生時代初期の青森県弘前市の砂沢遺跡から発見されているように、こうした構造はきわめて短期間のうちに本州北端まで広がっている。淡水魚が利用できるような水田は、稲作渡来の初期のころから日本全国でそろっていたのである。
図5 板付遺跡の先I期水田平面図
(山崎,1979)(工楽善通『水田の考古学』68ページより引用)
江戸時代になり、大河川にも堤防が築かれ、後背湿地が河川から切り離されて水田に作りかえられるようになると、水田のこの構造は、淡水魚の生存に重要な意味を持つことになった。下流域に棲む淡水魚は流されない仕組みの卵を産むとはいえ、孵化したばかりの稚仔魚は泳ぐ力が弱いため、産卵は後背湿地の池など流速の無い場所で行われる。堤防は河川と後背湿地の間の水の移動を制御したため、産卵場所への魚の移動を制限するおそれが出たのである。
しかし水田はいつも水を必要とするので、セットとして灌漑水路がつくられ、その出入口は必ず河川とつながっていた。
そのおかげで河川の後背湿地を産卵場所や稚魚の生活場所として使っていた第三紀型の淡水魚は、その場所を利用しつづけることができた。水田や水路では春になるとコイ、ギンブナ、ナマズなどが大きな川から入ってきて産卵をする。またドジョウ、メダカなどの小魚も水路から水田に入って産卵する。後背湿地での生活はこのような形で維持されているのである。
水田と水路を学習の場として活用するには
水田の生き物と人とのかかわりには長い歴史があり、水田の生き物は人とのかかわりのなかで生きてきた。水田の生き物は人がつくった環境で生きており、人の管理を必要とする。そして農村が滅ぶと多くの生き物も滅んでしまう。だからそれぞれの地域で生き物を保全するには、その地域の文化の保全と調和した形で保全する必要がある。
人の側からすれば、生き物と人とのかかわりの歴史は農村の環境が持つ財産である。この財産はそれを学ぶことにより知識が豊かになるという財産だから、教育機能を持った財産ということになる。そしてこの教育機能は地域の農業の発展や地域おこしに活用することができる。
生き物が昔のようにたくさん棲んでいたり、昔なつかしい風景や地域の文化がよく保全されていたりすると、その地域には都会の人がよく訪れる。そしてそこで自然と人のかかわりの歴史を学べるような仕組みができていれば、その人たちは何度もそこを訪れるようになるだろう。地域を訪れた人が喜んでくれると、地元の人は自信を持ってこの財産を活用するようになる。農村の環境は生涯学習の場、学校教育の総合学習の場として活用できるのである。
|