|
3. 宍道湖・中海における水質をはじめとする湖沼環境の改善
1)水質浄化の目的・目標
今後の湖を管理する上で重要なことは、水産としての利用を明確にすることである。そもそも両湖の環境基準は、「利用目的の適応性が水産2級(COD3mg/L以下・DO7.5mg/L以上)をクリヤーすることである」ということを再確認すべきである。水産利用を前提にすれば、目標は次の条件を満たすものでなければならない。
(1)汽水湖としての生態系回復が図られること
(2)漁業が安定的に繁栄する環境条件を確保すること
(3)干拓事業開始以前の状態に近い漁場環境の再生を行うこと
このようなことを念頭に置けば、具体的な目標となるのは、中海で春から秋にかけて長期間発生し、宍道湖では夏期を中心にする貧酵素水塊の解消以外にない。
貧酸素水塊の解消のためには、まず発生のメカニズムを理解することが大切である。そのメカニズム次のように整理できる。
貧酸素水塊は、湖底に堆積した有機物が水温の上昇とともに分解される過程で、供給される酸素量よりも消費される量が多くなり溶存酸素量が2.5mg/L以下になることから発生する。これを改善するためには、湖底に積堆する有機物を少なくすることと、湖底に供給する酸素量を多くすることである。
このメカニズムからすれば、考えられる対策を列挙すると次の通りとなる。
(1)湖に流入する有機物の量を削減すること
(2)湖の内部で生産される有機物の量を少なくすること
(3)湖底に酸素を供給すること(湖流の活発化)
(4)湖底に酸素を供給することの阻害要因を取り除くこと(塩分躍層の発生を防ぐこと)
(5)漁獲作業による湖底の攪拌を活発にすること
これらの対策について、水産振興をにらみながら優先順位をつけて実行をしていかねばならない。
2)水質改善のための対策
1. 汽水域としての特性・機能の回復(海水の交換条件の回復)
貧酸素水塊を解消するために、全ての事業が中止が決定になったいま、事業施設の取り扱いと関連する方法として、上記(3)、(4)に関連して次のことを行なう必要がある。
(1)森山・大海崎堤防の開削
(2)中浦水門の活用
(3)浅場造成、窪地の埋め戻し
今回の提言に当たっての根拠として行った、水質予測シミュレーションでは、(1)、(2)、(3)を組み合わせた形で行った。
(図中の中浦水門の潜り堤については、中浦水門の活用で代替している。)
その結果については別添(汽水湖研究第7号、平成14年度宍道湖中海環境修復シミュレーション)の通りとなった。ケース3が、現行の水運を確保した上で貧酸素水塊の解消に最も有効であることが明らかとなった。
2. 流域からの汚濁負荷の削減策
次の課題としては、汚濁負荷量及び内部生産量の削減があげられるが、とるべき方法は以下の通りである。
(1)流域の産業、土地利用の検討
宍道湖中海の流域を一元的にとらえ、土地利用にあたっては湖の水質を視野に入れた取り扱いを検討すること。(具体例でいえば、森林における森林整備協定の促進等がある)
(2)下排水対策の検討―公共下水道、農業集落排水などが考えられるが、施設の管理に問題が見られるところがあり、維持管理体制の見直し、適正な管理を行い、その効果を最大にする必要がある。
(3)工場等からの毒性・有害物質の排出規制、行政による規制体制の整備
このように従前からいわれている事項に付け加え、流入河川等の浄化対策についても検討が加えられるべきである。具体的にいうと霞ヶ浦等で検討されている事項について検討可能な事項は積極的に検討を開始する必要がある。
|
(1)流入河川の直接浄化対策
国は、流入河川の河口部等において、ヨシ原等を利用した植生浄化施設の整備を推進するとともに、沈殿池を含む湿地帯を利用した降雨初期の汚濁負荷の削減対策を推進する。
また、茨城県は、清明川等の流入河川の水質浄化を図るため、レキや植生帯などの浄化機能を活用した直接浄化施設等の整備を引き続き推進する。
さらに、土浦市は、ホテイアオイを活用した流入河川の水質浄化対策を推進する。
(2)堤脚水路の浄化対策
霞ヶ浦を取り巻く堤脚水路に薄層流水路を併設し、せせらぎなどが持つ浄化機能を利用して水質浄化を図る。
(3)生活排水汚濁水路の直接浄化対策
茨城県内の市町村においては、生活排水による水質汚濁が著しい水路についてその水質浄化を図るため、直接浄化施設の整備を推進する。
(4)生態系の持つ自然浄化機能を活用した浄化対策
流入河川においては、動植物の生息・生育環境や景観・空間利用などの河川環境に配慮した多自然型川づくりを、また、農業用水路やため池などの農業利水施設においては、その水辺空間を活用して農村地域の環境保全に対処するとともに、自然浄化機能を活用した水質浄化施設の整備を、地域生態系に配慮しながら推進する。
|
|
霞ヶ浦水質保全計画から
3. 湖内・湖岸対策
三番目の課題としては、湖内・湖岸の修復が課題となる。
(1)湖底の窪地の修復(これについては、前記シミュレーションに取り入れている。)
中海の東岸域に存在する浚渫後の窪地については、堤防の開削に伴う土砂を利用して、埋め戻しを行うこと。(開削による土砂は、中海干拓事業計画概要に記載されている堤防計画から計算すると、約34万m3程度となる)
(2)湖内・湖岸の植生の回復
湖岸域(開削しない堤防を含め)植生帯の回復をめざす。この植生帯については、舗装道路等からの有害物の湖内への流入の緩衝帯としても位置づける。
又、湖内で水生植物の回復を図る必要がある。
(3)水辺移行帯(エコトーン)の再生
潮の干満あるいは季節的な水位の変動によって陸域にも水域にもなる、いわゆる「水辺移行帯(エコトーン)」の再生、具体的には緩傾斜の湖岸の回復を図る必要がある。
4. 宍道湖・中海の水産振興対策
稚魚の放流等の振興対策を行うことは勿論であるが、当面急がれるのは水質を始めとする湖沼の環境改善を最優先することである。また、現状の漁業実態からして、中海と宍道湖ではその手法はおのずから異なってくるが、それぞれ列記すると次の通りとなる。
1)中海
1. 中海における水産振興の基本方向
本庄水域については堤防の開削を行う。
残水域については窪地の埋め戻しを行う。
浅場造成(漁場として最も有効なところ)
藻場の回復(光合成が可能な透明度の確保)
砂場ではコアマモ、岩場ではウミトラノオを指標植物にし回復させ、魚類の産卵場として管理していく。
中海の洪水対策として行なわれる湖岸工事にあたっては、自然湖岸の保全を最優先する。西・北岸の護岸工事の際に湧水源の確保に配慮する。
人工湖岸については、湖岸域の植生の改善を行うこと
以上のような対策を総合的に行い、漁業としての期待魚種(市場価値の高い魚介類)の資源回復を目指す。
指標となる期待魚種をあげると次の通りである。
サルボウ・バイガイ・アサリ・マガキ(養殖)
ガザミ・クルマエビ(現在放流)・アカアシエビ・カレイ類・ヒラメ・マダコ・ミズダコ・アナゴなど
2)宍道湖
1. シジミ、ワカサギ、シラウオの持続的な生産条件の整備を行うこと。
2. 未利用魚の活用 付加価値を高める―水産加工・販売を検討すること。
3. 天神川、剣先川、佐陀川その他流入河川の活用を検討すること。
5. まとめ
以上述べたように、中海・宍道湖地域の地域振興策にとって、最優先すべき課題は、両湖を含む周辺地域の環境再生である。
そのためには、次の事項を速やかに実施することを提言する。
(1)貧酸素水塊の解消のために堤防の開削、中浦水門の活用(潜堤として)、浚渫窪地の埋め戻しの実施
(2)湖岸、湖内の植生の回復のための事業の実施
(3)自然湖岸の復元事業の実施
(4)両湖の保全を念頭に置いた流域の一体的な管理
今回の提言にある事項を着実に実行するために、自然再生推進法の積極的な活用を行うべきである。同法に基づき、島根県が率先して関係機関等に呼びかけて「中海・宍道湖再生協議会」(仮称)を設置され、実施計画を得て、自然再生のための総合的、効果的かつ効率的な事業を推進されるよう提言する。
■参考 自然再生推進法の仕組み
|
(拡大画面:145KB)
|
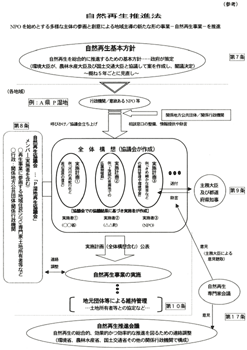 |
環境省ホームページから
|