|
宍道湖・中海水域の魚介類の現況
宍道湖生物研究会
越川敏樹
はじめに
宍道湖・中海水域の魚族については、1962年に京都大学の宮地伝三郎他による「中海干拓・淡水化事業に伴う魚族生態調査」によって、詳細に報告されている。その後は、そのような大規模かつ緻密な調査は行われていない。その間、本水域は広大な干拓と堤防構築の工事によって地形とそれに伴う水環境が大きく変えられた。同時に進行した周辺からの流入水の汚染も重なり、魚介類の生息状況は大きく変えられていった。
その間の調査は、断片的ではあるが、越川(1986)、須永(1990)、鳥取水産試験場(1996)などによってなされている。先の大規模な調査とは、同等に比較することはできないが、それらによって当水域の生態的な変化は明確に読み取ることができる。
本報では、最近5年間の本水域における魚介類の生息状況をまとめると同時に、干拓・堤防のなかった時代との比較をふまえながら、今後の課題を探ってみた。
1. 最近の生息状況
当水域の棲息魚族の確認は、専業漁師の漁獲物から確認することが合理的である。よって、本報では2001年3月から2003年3月までに宍道湖と中海の定置網と刺網の漁獲内容に基づいた。宍道湖:浜佐陀・秋鹿(松江市)・中海:大海崎・本庄(松江市)、論田(安来市)・入江(八束町)
図−1(1) 宍道湖・中海水域の概念図
|
(拡大画面:30KB)
|
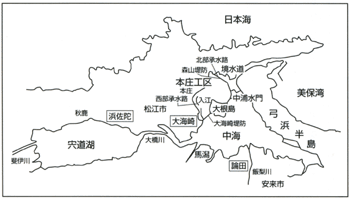 |
図−1(2) 中海北東部の域概念図
馬渡〜江島堤防(矢印)の位置
種類数の把握は、細かい網目のもんどりを取付けたます網が最も効果的である。その際、中海は周年を通して操業されるが、宍道湖の場合は操業期間が10月15日から翌年3月末日までの間(ワカサギ漁)に限られるので、刺網漁を主にし、時にます網の漁獲内容を基にした。刺網の利点は、漁獲される種類数が限られる反面、食性や特定な魚種の成長を調べる上で有効である。
結果、上の期間を通じて、45科77種の魚類、10種のエビ類、4種のカニ類、3種のイカ類、4種の貝類が漁獲された。貝類の採集は別の方法によってなされた。
表−1 宍道湖・中海水域の魚族(2001年3月〜2003年3月・漁獲)
◎多く出現、○少なく出現、(○)雨後など特定の条件下で出現 III多い、II普通、I少ない
| 科 |
標準和名 |
学名 |
分布 |
漁獲量 |
商取引
対象 |
備考 |
| 宍道湖 |
中海 |
| 1 |
あかえい |
アカエイ |
Dasyatis akajei |
○ |
◎ |
II |
○ |
|
| 2 |
からいわし |
カライワシ |
Elops machnata |
○ |
○ |
I |
|
新しく採集 |
| 3 |
このしろ |
コノシロ |
Konosirus punctatus |
◎ |
◎ |
III |
○ |
商取引は主に中海、増加 |
| 4 |
にしん |
サッパ |
Harengula zunasi |
◎ |
◎ |
III |
○ |
商取引は主に中海 |
| 5 |
かたくちいわし |
カタクチイワシ |
Engrauris japonica |
○ |
◎ |
II |
○ |
〃 |
| 6 |
さけ |
サケ |
Oncorhynchus keta |
○ |
○ |
I |
○ |
|
| 7 |
あゆ |
アユ |
Plecoglossus altiveris |
◎ |
◎ |
III |
○ |
増加傾向 |
| 8 |
わかさぎ |
ワカサギ |
Hypomesus olidus |
○ |
○ |
I |
○ |
激減 |
| 9 |
しらうお |
シラウオ |
Salanx microdon |
◎ |
○ |
II |
○ |
|
| 10 |
えそ |
マエソ |
Saurida undorosquamis |
|
○ |
I |
|
|
| 11 |
こい |
タイリクバラタナゴ |
Rodeus ocellatus |
○ |
(○) |
I |
|
|
| 12 |
こい |
ハス |
Opsariichthys uncirostris |
○ |
|
I |
|
減少 |
| 13 |
こい |
ホンモロコ |
Gnathoopogon elongatus |
○ |
|
I |
|
|
| 14 |
こい |
ウグイ |
Tribolodon hakonensis |
◎ |
◎ |
III |
○ |
商取引は主に中海 |
| 15 |
こい |
ワタカ |
Ischikauia sleenacheri |
○ |
|
II |
|
|
| 16 |
こい |
コイ |
Cyprinus carpio |
◎ |
(○) |
II |
○ |
|
| 17 |
こい |
フナ類 |
Carassius carassius |
◎ |
(○) |
III |
○ |
|
| 18 |
ごんずい |
ゴンズイ |
Plotosus anguillaris |
|
○ |
II |
|
増加気味 |
| 19 |
なまず |
ナマズ |
Silurus asotus |
○ |
(○) |
I |
|
|
| 20 |
うなぎ |
ウナギ |
Anguilla japonica |
◎ |
◎ |
II |
○ |
減少傾向 |
| 21 |
うみへび |
ダイナンウミヘビ |
Ophisurus macrorhynchus |
|
○ |
I |
|
新しく採集 |
| 22 |
だつ |
ダツ |
Ablennes anastomella |
○ |
○ |
II |
○ |
商取引は中海(卵巣) |
| 23 |
さより |
サヨリ |
Hemiramphus sajori |
○ |
◎ |
III |
○ |
|
| 24 |
いとよ |
イトヨ |
Gasterosteus aculeatus |
○ |
○ |
I |
|
激減 |
| 25 |
ようじうお |
ヨウジウオ |
Syngnathus schlegeli |
○ |
◎ |
I |
|
|
| 26 |
ようじうお |
タツノオトシゴ |
Hippocampus coronatus |
○ |
◎ |
I |
|
|
| 27 |
とうごろういわし |
トウゴロウイワシ |
Atherina bleekeri |
○ |
◎ |
II |
|
|
| 28 |
ぼら |
メナダ |
Liza haematochelia |
○ |
○ |
II |
○ |
|
| 29 |
ぼら |
セスジボラ |
Liza affinis |
◎ |
◎ |
II |
|
|
| 30 |
ぼら |
ボラ |
Mugil cephalus |
◎ |
◎ |
III |
○ |
減少傾向 |
| 31 |
かます |
アカカマス |
Syhyraena schlegeli |
|
○ |
III |
○ |
|
| 32 |
らいぎょ |
カムルチー |
Channa argus |
○ |
(○) |
I |
|
|
| 33 |
あじ |
マアジ |
Trachurus japonicus |
|
○ |
II |
○ |
減少傾向 |
| 34 |
あじ |
カンパチ |
Seriola purpurascens |
|
○ |
I |
|
新しく採集 |
| 35 |
ひいらぎ |
ヒイラギ |
Leiognathus nuchalis |
○ |
◎ |
III |
○ |
減少傾向 |
| 36 |
てんじくだい |
ネンブツダイ |
Apogon semilineatus |
|
○ |
I |
|
|
| 37 |
すずき |
スズキ |
Lateolabrax japonicus |
◎ |
◎ |
III |
○ |
増加傾向 |
| 38 |
すずき |
ヒラスズキ |
L. Latus |
○ |
○ |
I |
|
|
| 39 |
しまいさき |
シマイサキ |
Therapon axyrhynchus |
○ |
◎ |
I |
○ |
|
| 40 |
さんふぃっしゅ |
オオクチバス |
Micropterus salmoides |
○ |
(○) |
I |
|
中海は河川からの流出 |
| 41 |
さんふぃっしゅ |
ブルーギル |
Lepomis macrochirus |
○ |
(○) |
I |
|
中海は河川からの流出 |
| 42 |
たい |
クロダイ |
Mylio macrocephalus |
○ |
◎ |
II |
○ |
減少傾向 |
| 43 |
たい |
ヘダイ |
Rhabdosargus sarba |
|
○ |
I |
|
減少 |
| 44 |
くろさぎ |
クロサギ |
Gerres oyena |
|
○ |
I |
|
|
| 45 |
きす |
キス |
Sillago japonica |
|
○ |
I |
○ |
|
| 46 |
うみたなご |
ウミタナゴ |
Ditrema temmincki |
|
◎ |
II |
○ |
|
| 47 |
いそぎんぽ |
イソギンポ |
Blennius yatabei |
|
○ |
I |
|
|
| 48 |
いそぎんぽ |
トサカギンポ |
Omobranchus fasciolatoceps |
○ |
○ |
I |
|
|
| 49 |
にしきぎんぽ |
ギンポ |
Enedrias nebulosus |
○ |
◎ |
II |
○ |
激減 |
| 50 |
にしきぎんぽ |
ムスジガジ |
Ernogrammus exagrammus |
○ |
◎ |
I |
|
|
| 51 |
はぜ |
スジハゼ |
Gobius pflaumi |
|
○ |
I |
|
|
| 52 |
はぜ |
マハゼ |
Aconthogobius flavimanus |
◎ |
◎ |
III |
○ |
減少傾向 |
| 53 |
はぜ |
アシシロハゼ |
A. Lactipes |
◎ |
○ |
II |
|
|
| 54 |
はぜ |
ウロハゼ |
Glossogobius giuris |
○ |
◎ |
II |
○ |
増加傾向 |
| 55 |
はぜ |
ニクハゼ |
Chaenogobius heptacanthus |
|
◎ |
II |
○ |
減少傾向 |
| 56 |
はぜ |
ビリンゴ |
C. annularis |
|
◎ |
III |
○ |
減少傾向 |
| 57 |
はぜ |
ウキゴリ |
C. Urotaenia |
◎ |
◎ |
II |
○ |
商取引は幼魚 |
| 58 |
はぜ |
シンジコハゼ |
C. Sp. |
◎ |
|
II |
|
|
| 59 |
はぜ |
ドロメ |
Chasmichtys dolichognathus |
|
◎ |
I |
|
|
| 60 |
はぜ |
チチブ |
Trideniger obschurus |
|
◎ |
II |
○ |
|
| 61 |
はぜ |
ヌマチチブ |
T. kuroiwae |
◎ |
|
II |
|
|
| 62 |
はぜ |
シモフリシマハゼ |
T. trigonocephalus |
◎ |
◎ |
III |
○ |
商取引は中海 |
| 63 |
はぜ |
ミミズハゼ |
Lusiogobius guttatus |
○ |
◎ |
I |
|
|
| 64 |
はぜ |
シロウオ |
Leucopsarion petersi |
◎ |
◎ |
II |
○ |
|
| 65 |
はぜ |
タケノコネバル |
Sebastes oblongus |
|
○ |
I |
○ |
|
| 66 |
かさご |
クロソイ |
S. schlegeli |
○ |
◎ |
II |
○ |
減少傾向 |
| 67 |
こち |
マゴチ |
Platycephalus indicus |
○ |
◎ |
II |
○ |
|
| 68 |
かじか |
カジカ |
Cottus pollux |
◎ |
◎ |
I |
|
|
| 69 |
ひらめ |
ヒラメ |
Paralichthys olivaceus |
○ |
◎ |
I |
○ |
|
| 70 |
かれい |
イシガレイ |
Kareius bicoloratus |
○ |
◎ |
II |
○ |
|
| 71 |
かわはぎ |
カワハギ |
Stephanolepis cirrhifer |
|
○ |
I |
|
幼魚が漁獲 |
| 72 |
かわはぎ |
アミメハギ |
Rudaris ercodes |
|
○ |
I |
|
|
| 73 |
まふぐ |
トラフグ |
Fugu rubripes |
|
◎ |
II |
○ |
減少傾向 |
| 74 |
まふぐ |
シマフグ |
F. Xanthopterus |
|
○ |
I |
|
|
| 75 |
まふぐ |
クサフグ |
F. Niphobles |
○ |
◎ |
II |
○ |
商取引は中海 |
| 76 |
まふぐ |
コモンフグ |
F. Poecilonoteus |
|
○ |
I |
|
|
| 77 |
まふぐ |
ヒガンフグ |
F. Pardalis |
|
◎ |
II |
○ |
商取引は中海 |
|
<魚類以外>
| 科 |
標準和名 |
学名 |
分布 |
漁獲量 |
商取引対象 |
備考 |
| 宍道湖 |
中海 |
| 1 |
えび |
テナガエビ |
Macrobrachium nipponense |
◎ |
○ |
II |
○ |
激減 |
| 2 |
|
スジエビ |
Palaemon paucidens |
○ |
(○) |
II |
○ |
減少傾向 |
| 3 |
|
スジエビモドキ |
Palaemon serrifer |
(○) |
◎ |
III |
○ |
主に中海 |
| 4 |
|
シラタエビ |
Palaemon orientis |
○ |
◎ |
II |
○ |
減少傾向 |
| 5 |
|
ヨシエビ |
Netapenaeus ensis |
○ |
◎ |
II |
○ |
減少傾向 |
| 6 |
|
クマエビ |
Penaeus semisulcatus |
|
○ |
I |
○ |
|
| 7 |
|
エビジャコ |
Crangon affinis |
|
○ |
I |
|
|
| 8 |
|
アメリカザリガニ |
Procambarus clarkii |
○ |
(○) |
I |
|
|
| 9 |
|
アキアミ |
Acetes japonicus |
|
◎ |
II |
○ |
主に中海で商取引・減少 |
| 10 |
|
イサザアミ |
|
◎ |
◎ |
III |
○ |
主に中海で商取引 |
| 11 |
かに |
タイワンガザミ |
Portunus peltagicus |
○ |
◎ |
II |
○ |
激減 |
| 12 |
|
モクズガニ |
Eriocheir japonicus |
◎ |
◎ |
II |
○ |
減少傾向 |
| 13 |
|
ケフサイソガニ |
Hemigrapsus peniciltatus |
○ |
◎ |
II |
○ |
主に中海で商取引 |
| 14 |
|
マメコブシガニ |
Philyra pisum |
○ |
◎ |
I |
|
|
| 15 |
いか |
ジンドウイカ |
|
|
○ |
I |
○ |
幼体と未成体 |
| 16 |
|
アオリイカ |
Sepioteuthis lessoniana |
|
○ |
I |
○ |
幼体と未成体 |
| 17 |
|
コウイカ |
Sepia esuculenta |
|
○ |
II |
○ |
幼体と未成体 |
| 18 |
かい |
アカニシ |
Rapana thomasiana |
|
◎ |
II |
○ |
|
| 19 |
|
サルボウガイ |
Scapharca subcrenata |
|
○ |
I |
○ |
中海の一部に限定 |
| 20 |
|
ヤマトシジミ |
Corbicula japonica |
◎ |
○ |
III |
○ |
主に宍道湖 |
| 21 |
|
アサリ |
Tapes philippinarm |
|
◎ |
II |
○ |
主に中海 |
|
宍道湖と中海に広く分布する種は、50種(広塩性および両側回遊性魚類)、外海から中海まで進入する種で、宍道湖までは普通遡上しない魚に19種(海産魚類)、宍道湖を主な棲息域としており、中海には普通下らない種が8種であった。(主に淡水性魚類)
生息魚の季節的な変化は、冬の間は多くの種が比較的水温の高い外海に去っており、寒冷に対して耐性の強い魚が宍道湖・中海にとどまっている。主なものは、中海では、マハゼ、クロソイ、ワカサギ、シラウオ、ウグイと周年生息するシマハゼ類、チチブ類、ビリンゴなどのハゼ類で、宍道湖では、上のクロソイを除いたものにフナとアシシロハゼなどが加わる。もっとも、マハゼは宍道湖で越冬するものはわずかである。
宍道湖においては、2月初旬より外海から中海に進入した魚類が遡上してくる。最も早いものは、ボラの1歳魚が確認された。続いて中旬になると、スズキ1歳魚が姿を見せ初め、3月に入るとスズキとボラの2歳魚(大型)が確認された。3月の中旬になると、コノシロの1歳魚と2歳魚が同時に入り、やや遅れてサッパが続く。このように、早春より外海からの回遊魚の遡上があり、その後は順次他の種が加わってくる。また、水温が低下する11月中旬からは、上の遡上の順とは逆に中海に降下していく。
多くの魚種は上に述べたように移動するが、周年を通じてあまり移動しない種として、表−1の中ではチチブ、ヌマチチブ、シモフリシマハゼ、ドロメ、アシシロハゼ、ウロハゼなどのハゼ類とクロソイ、ヨウジウオ、タツノオトシゴなどがいる。
図−2 早春の宍道湖への魚の遡上時期
|
(拡大画面:33KB)
|
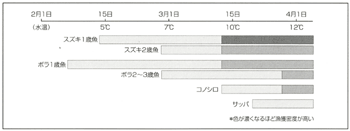 |
|