|
3)1998年(平成10年)の調査結果
本調査は、宍道湖全域の漁場で大量斃死が起きた昨年(1997年)から満1年であり、昨年の調査月日とほぼ同じ8月22日、23日に行った。なお宍道のシジミ漁場のシジミの生息状況を正確に把握するために、宍道湖東部の南岸に近いSt.12(嫁ヶ島)を調査地点に追加した。
(1)無機的生息環境(表9)
調査地点の漁場の底質は、渚沖50mまでは細砂・砂がほとんどで(St.2、8、9、10、12、13)、細砂・砂・シルトがSt.6、細砂・砂・detritusがSt.3、4、11、細砂・砂・シルト・detritusがSt.5、7であった。渚沖50m〜200mでは、底質が砂・細砂はSt.2、7、11、12、13で、細砂・砂・detritusはSt.1、3、4、8、10で、細砂・シルト・detritusはSt.5、6、シルト・detritusはSt.9であった。
200m以上沖の漁場は、底質が細砂・砂・detritusはSt.6、7、8、10、12、シルト・detritusはSt.1〜5、9、11、13であった。
表9. 1998年の調査地点の底質、水深、水温、塩素イオン濃度、漁場
(1998年8月22日、23日調査)
| 調査地点 |
水深(m) |
水温℃ |
塩素イオン濃度(pm) |
底質 |
漁場 |
| 表層 |
底層 |
表層 |
底層 |
St.1
(平田) |
a |
1.0 |
28.0 |
27.7 |
883 |
875 |
細砂 |
機械操業区 |
| b |
1.8 |
29.0 |
29.5 |
980 |
1,575 |
細砂・デトリタス |
〃 |
| c |
2.4 |
29.3 |
29.2 |
1,060 |
1,695 |
シルト・デトリタス |
〃 |
St.2
(斐川) |
a |
2.1 |
28.0 |
28.6 |
1,935 |
1,985 |
砂・細砂 |
機械操業区 |
| b |
2.6 |
28.0 |
28.7 |
1,975 |
2,390 |
砂 |
〃 |
| c |
3.5 |
28.0 |
28.7 |
1,850 |
1,935 |
シルト・デトリタス |
〃 |
St.3
(一畑口) |
a |
1.6 |
29.5 |
29.0 |
1,300 |
1,675 |
砂・細砂・デトリタス |
機械操業区 |
| b |
1.9 |
29.6 |
29.0 |
1,400 |
1,805 |
細砂・デトリタス |
〃 |
| c |
2.8 |
30.0 |
29.4 |
1,360 |
1,875 |
シルト・デトリタス |
〃 |
St.4
(伊野) |
a |
2.1 |
30.2 |
29.1 |
1,925 |
1,980 |
砂・デトリタス |
機械操業区 |
| b |
2.6 |
30.2 |
29.0 |
1,950 |
1,995 |
〃 |
〃 |
| c |
3.3 |
30.2 |
29.0 |
1,800 |
2,190 |
シルト・デトリタス |
〃 |
St.5
(白石) |
a |
1.7 |
28.5 |
28.0 |
1,900 |
1,950 |
細砂・シルト・デトリタス |
機械操業区 |
| b |
3.1 |
29.0 |
28.5 |
1,950 |
1,980 |
シルト・細砂・デトリタス |
〃 |
| c |
4.0 |
29.0 |
28.5 |
1,940 |
1,940 |
シルト・デトリタス |
〃 |
St.6
(津ノ森) |
a |
1.6 |
29.5 |
29.5 |
2,090 |
2,145 |
細砂・シルト |
機械操業区 |
| b |
2.8 |
29.6 |
29.2 |
2,075 |
2,125 |
細砂・シルト・デトリタス |
〃 |
| c |
3.9 |
29.6 |
29.0 |
2,015 |
2,050 |
砂・デトリタス |
〃 |
St.7
(来待) |
a |
2.1 |
29.0 |
28.5 |
2,200 |
2,200 |
砂・粗砂・デトリタス |
機械操業区 |
| b |
2.8 |
28.5 |
28.5 |
2,035 |
2,035 |
砂・粗砂 |
〃 |
| c |
3.3 |
28.5 |
28.5 |
2,070 |
2,150 |
砂・粗砂・デトリタス |
〃 |
St.8
(鳥ヶ崎) |
a |
1.2 |
28.0 |
28.0 |
2,100 |
2,100 |
細砂・砂 |
機械操業区 |
| b |
3.2 |
28.7 |
28.3 |
2,280 |
2,310 |
砂・粗砂・デトリタス |
〃 |
| c |
4.1 |
28.7 |
28.6 |
2,260 |
2,340 |
〃 |
〃 |
St.9
(長江) |
a |
1.9 |
29.5 |
29.5 |
2,170 |
2,185 |
細砂 |
機械操業区 |
| b |
3.6 |
29.6 |
29.5 |
2,165 |
2,200 |
シルト・デトリタス |
〃 |
| c |
4.0 |
29.8 |
29.2 |
2,175 |
2,200 |
〃 |
〃 |
St.10
(玉湯) |
a |
1.8 |
29.0 |
28.5 |
2,180 |
2,180 |
砂・粗砂 |
機械操業区 |
| b |
3.2 |
28.0 |
28.5 |
2,180 |
2,180 |
砂・粗砂・デトリタス |
〃 |
| c |
4.0 |
28.8 |
28.5 |
2,310 |
2,310 |
砂・デトリタス |
〃 |
St.11
(玉造) |
a |
1.8 |
28.5 |
28.3 |
2,310 |
2,310 |
細砂・砂・デトリタス |
手掻操業区 |
| b |
2.8 |
28.8 |
28.3 |
2,250 |
2,250 |
砂・粗砂 |
〃 |
| c |
4.2 |
29.0 |
28.6 |
2,250 |
2,350 |
シルト・デトリタス |
〃 |
St.12
(嫁ヶ島) |
a |
1.7 |
29.0 |
28.7 |
2,190 |
2,200 |
砂 |
手掻操業区 |
| b |
1.8 |
29.0 |
28.6 |
2,250 |
2,250 |
砂・粗砂 |
〃 |
| c |
3.7 |
29.1 |
28.7 |
2,260 |
2,290 |
細砂・砂・デトリタス |
〃 |
St.13
(松江温泉) |
a |
1.9 |
29.0 |
28.5 |
2,265 |
2,265 |
砂 |
手掻操業区 |
| b |
2.0 |
29.0 |
29.0 |
2,260 |
2,290 |
〃 |
〃 |
| c |
3.8 |
29.0 |
29.0 |
2,280 |
2,600 |
シルト・砂・デトリタス |
〃 |
|
a:岸より沖50mまで、 b:岸より50m〜200m、 c:岸より200m以上沖
水温は、表層水温28.0〜30.2℃、底層水温は27.5〜29.5℃で、表層水温と底層水温の差はほとんどなかった。
塩素イオン濃度は、St.1(平田)は875〜1695ppmで、渚沖50mまでの漁場は875〜883ppmと低く、底層は表層に比較してやや高濃度であった。St.2(斐川)は1850〜2390ppm、St.3(一畑口)は1300〜1875ppm、St.4(伊野)とSt.5(白石)は1925〜2190ppm、他の漁場は2035〜2280ppmであった。
殻長17〜30mmの漁獲対象貝の生息数は、最も生息数の多かったSt.13(松江温泉)の漁場で573個体/m2、前年比50%(以下括弧内%は前年比を示す)と減少していた。St.11(玉造)は353個体で前年とほぼ等しい。St.4(伊野)は192個体(50%)で前年の1/2、St.5(白石)は139個体(27%)、St.7(来待)は131個体(40%)、St.6(津ノ森)95個体(18%)、St.10(玉湯)81個体(30%)、St.9(長江)64個体(26%)と著しい減少がみられた。特に生息数の著しい減少がみられたSt.8(鳥ヶ崎)は43個体(11%)で前年の1/10、St.3(一畑口)は20個体(4%)で前年の1/23と激減していた。またSt.1(平田)も28個体(27%)で前年比1/3.7、St.2(斐川)は41個体(18%)で前年比1/5.6と著しく減少していた。漁場の殻長17〜<30mm漁獲対象貝の平均生息数は147個体(35%)で、前年と比較して約1/3の生息数であった。
表10. 1998年の漁場のヤマトシジミ生息数(1998年8月22日、23日調査)
スミス・マッキンタイヤ採泥器で採集、底平面積2500cm2前(500cm2×5本)当りの生息数、( )は1m2当りの生息数
| 調査地点名 |
水深(m) |
殻長(mm) |
| 2〜<5 |
5〜<8 |
8〜<15 |
15〜<17 |
17〜<30 |
計 |
St.1
(平田) |
a |
1.0 |
3 |
(12) |
6 |
(24) |
9 |
(36) |
18 |
(72) |
18 |
(72) |
54 |
(216) |
| b |
1.8 |
0 |
(0) |
1 |
(4) |
0 |
(0) |
0 |
(0) |
2 |
(8) |
3 |
(12) |
| c |
2.4 |
0 |
(0) |
0 |
(0) |
0 |
(0) |
0 |
(0) |
1 |
(4) |
1 |
(4) |
St.2
(斐川) |
a |
2.1 |
1 |
(4) |
14 |
(56) |
74 |
(296) |
12 |
(48) |
11 |
(44) |
112 |
(448) |
| b |
2.6 |
0 |
(0) |
8 |
(32) |
62 |
(248) |
17 |
(68) |
13 |
(52) |
100 |
(400) |
| c |
3.5 |
0 |
(0) |
1 |
(4) |
9 |
(36) |
3 |
(12) |
7 |
(28) |
20 |
(80) |
St.3
(一畑口) |
a |
1.6 |
3 |
(12) |
11 |
(44) |
25 |
(100) |
5 |
(20) |
8 |
(32) |
52 |
(208) |
| b |
1.9 |
7 |
(28) |
14 |
(56) |
15 |
(60) |
8 |
(32) |
7 |
(28) |
51 |
(204) |
| c |
2.8 |
0 |
(0) |
0 |
(0) |
1 |
(4) |
0 |
(0) |
0 |
(0) |
1 |
(4) |
St.4
(伊野) |
a |
2.1 |
3 |
(12) |
19 |
(76) |
50 |
(200) |
19 |
(76) |
19 |
(76) |
110 |
(440) |
| b |
2.6 |
9 |
(36) |
22 |
(88) |
51 |
(204) |
27 |
(108) |
55 |
(220) |
164 |
(656) |
| c |
3.3 |
1 |
(4) |
4 |
(16) |
72 |
(288) |
34 |
(136) |
70 |
(280) |
181 |
(724) |
St.5
(白石) |
a |
1.7 |
24 |
(96) |
29 |
(116) |
291 |
(1164) |
85 |
(340) |
79 |
(316) |
508 |
(2032) |
| b |
3.1 |
10 |
(40) |
14 |
(56) |
37 |
(148) |
1 |
(4) |
17 |
(68) |
79 |
(316) |
| c |
4.0 |
0 |
(0) |
13 |
(52) |
52 |
(208) |
8 |
(32) |
8 |
(32) |
81 |
(324) |
St.6
(津ノ森) |
a |
1.6 |
11 |
(44) |
28 |
(112) |
51 |
(204) |
20 |
(80) |
25 |
(100) |
135 |
(540) |
| b |
2.8 |
16 |
(64) |
27 |
(108) |
117 |
(468) |
15 |
(60) |
13 |
(52) |
188 |
(752) |
| c |
3.9 |
3 |
(12) |
18 |
(72) |
69 |
(276) |
11 |
(44) |
33 |
(132) |
134 |
(536) |
St.7
(来待) |
a |
2.1 |
28 |
(112) |
53 |
(212) |
365 |
(1460) |
93 |
(372) |
62 |
(248) |
601 |
(2404) |
| b |
2.8 |
23 |
(92) |
21 |
(84) |
134 |
(536) |
27 |
(108) |
15 |
(60) |
220 |
(880) |
| c |
3.3 |
24 |
(96) |
12 |
(48) |
144 |
(576) |
27 |
(108) |
21 |
(84) |
228 |
(912) |
St.8
(鳥ヶ崎) |
a |
1.2 |
103 |
(412) |
54 |
(216) |
254 |
(1016) |
66 |
(264) |
13 |
(52) |
490 |
(1960) |
| b |
3.2 |
39 |
(156) |
61 |
(244) |
327 |
(1308) |
21 |
(84) |
9 |
(36) |
457 |
(1828) |
| c |
4.1 |
52 |
(208) |
59 |
(236) |
294 |
(1176) |
15 |
(60) |
10 |
(40) |
430 |
(1720) |
St.9
(長江) |
a |
1.9 |
65 |
(260) |
8 |
(32) |
87 |
(348) |
39 |
(156) |
38 |
(152) |
237 |
(948) |
| b |
3.6 |
3 |
(12) |
7 |
(28) |
45 |
(180) |
12 |
(48) |
9 |
(36) |
76 |
(304) |
| c |
4.0 |
0 |
(0) |
4 |
(16) |
13 |
(52) |
2 |
(8) |
1 |
(4) |
20 |
(80) |
St.10
(玉湯) |
a |
1.8 |
45 |
(180) |
94 |
(376) |
674 |
(2696) |
48 |
(192) |
44 |
(176) |
905 |
(3620) |
| b |
3.2 |
26 |
(104) |
40 |
(160) |
136 |
(544) |
10 |
(40) |
17 |
(68) |
229 |
(916) |
| c |
4.0 |
4 |
(16) |
3 |
(12) |
6 |
(24) |
0 |
(0) |
0 |
(0) |
13 |
(52) |
St.11
(玉造) |
a |
1.8 |
125 |
(500) |
34 |
(136) |
277 |
(1108) |
85 |
(340) |
66 |
(264) |
587 |
(2348) |
| b |
2.8 |
39 |
(156) |
52 |
(208) |
392 |
(1568) |
148 |
(592) |
199 |
(796) |
830 |
(3320) |
| c |
4.2 |
0 |
(0) |
3 |
(12) |
3 |
(12) |
0 |
(0) |
0 |
(0) |
6 |
(24) |
St.12
(嫁ヶ島) |
a |
1.7 |
5 |
(20) |
54 |
(216) |
345 |
(1380) |
38 |
(152) |
41 |
(164) |
483 |
(1932) |
| b |
1.8 |
1 |
(4) |
50 |
(200) |
493 |
(1972) |
100 |
(400) |
59 |
(236) |
703 |
(2812) |
| c |
3.7 |
13 |
(52) |
63 |
(252) |
154 |
(616) |
29 |
(116) |
33 |
(132) |
292 |
(1168) |
St.13
(松江温泉) |
a |
1.9 |
69 |
(276) |
57 |
(228) |
686 |
(2744) |
196 |
(784) |
174 |
(696) |
1182 |
(4728) |
| b |
2.0 |
1 |
(4) |
77 |
(308) |
956 |
(3824) |
321 |
(1284) |
227 |
(908) |
1582 |
(6328) |
| c |
3.8 |
1 |
(4) |
32 |
(128) |
166 |
(664) |
25 |
(100) |
29 |
(116) |
253 |
(1012) |
|
a:岸より沖50mまで、 b:岸より沖50m〜200m、 c:岸より200m以上沖
殻長15〜<17mmの貝の生息数は、比較的生息数の多いSt.13(松江温泉)は1m2当り723個体(92%)、St.11(玉造)は311個体(100%)、St.12(嫁ヶ島)223個体、St.7(来待)196個体(100%)であった。昨年の生息数とほぼ同じ生息数であった漁場はSt.5(白石)125個体(100%)、St.9(長江)71個体(100%)、次いでSt.4(伊野)107個体(86%)であった。前年生息数に比較して著しい減少のみられた漁場は、St.3(一畑口)17個体(11%)で前年の1/9、St.6(津ノ森)61個体(32%)前年比1/3、St.2(斐川)43個体(45%)前年比1/2.2、St.10(玉湯)77個体(48%)前年比1/2、St.8(鳥ヶ崎)136個体(57%)前年比1/1.8、St.1(平田)24個体(67%)前年比1/1.5であった。漁場の平均生息数は163個体(70%)で前年と比較して30%生息数の減少がみられた。
殻長8〜<15mmの貝は、生息数の多いSt.13(松江温泉)は1m2当り2411個体で前年比1.1倍、St.12(嫁ヶ島)1323個体、St.8(鳥ヶ崎)1167個体で前年比2.3倍、St.10(玉湯)1088個体、4.3倍、St.11(玉造)896個体、1.5倍、St.7(来待)857個体、2.4倍、St.5(白石)507個体、5.1倍、St.6(津ノ森)316個体、1.4倍と、生息数は前年と比較して増加した。他方St.1(平田)は12個体(6%)、St.2(斐川)は193個体(59%)、St.3(一畑口)は55個体(14%)、St.9(長江)は193個体(69%)と、生息数は前年と比較して減少していた。以上の様に湖南の漁場では生息数の著しい増加がみられるが、宍道湖西岸域のSt.1、St.2、St.3はむしろ著しい減少を示した。湖北、宍道湖東部はSt.9(長江)の漁場を除き、生息数の増加傾向が認められた。
殻長5〜<8mmの幼貝の生息数は、St.11(玉造)の1m2当り847個体(前年比7倍)の生息数の増加がみられ、それ以外のすべての漁場で生息数が減少していた。St.12(嫁ヶ島)912個体、St.8(鳥ヶ崎)232個体(37%)、St.13(松江温泉)221個体(15%)、St.7(来待)115個体(37%)、St.6(津ノ森)97個体(60%)、St.5(白石)75個体(44%)、St.4(伊野)60個体(30%)、St.3(一畑口)33個体(22%)、St.2(斐川)31個体(15%)、St.9(長江)25個体(5%)、St.1(平田)9個体(18%)と生息数が減少していた。
殻長2〜5<mmの幼貝の生息数は、幼貝の生息状況と同様、St.11(玉造)の漁場でみられた生息数1m2当り1067個体(前年比4.9倍)以外の漁場では、生息数はすべて減少していた。St.8(鳥ヶ崎)は1m2当り259個体(35%)、St.7(来待)100個体(32%)、St.10(玉湯)100個体(35%)、St.13(松江温泉)95個体(6%)、St.9(長江)91個体(20%)、St.5(白石)45個体(41%)、St.6(津ノ森)40個体(11%)、St.12(嫁ヶ島)25個体、St.4(伊野)17個体(6%)、St.3(一畑口)13個体(5%)、St.1(平田)4個体(36%)、St.2(斐川)1個体(1.3%)であった。平均個数は1m2当り154個体(39%)で前年比1/2.5であった。
(3)シジミ漁場の水域別ヤマトシジミ生息状況(表10)
各漁場のヤマトシジミ生息状況を渚から沖にかけて、沖50mまで、沖50〜200m、200m以上沖の水域別に生息数をみた。
宍道湖西岸域のSt.1(平田)では、ヤマトシジミの生息数は渚沖50mの漁場に93%が生息し、それ以上沖にはほとんどみられなかった。St.2(斐川)は沖200mまでに91%が生息し、200m以上沖にはほとんど生息がみられなかった。St.3(一畑口)は、St.2と同様に沖200mまでの漁場に99%生息し、それ以上沖にはほとんどみられなかった。St.4(伊野)では、200m以上沖でも40%生息がみられ、渚沖50mまでの漁場より沖に多く生息していた。St.5(白石)は沖50mまでに76%、50m以上沖には24%の生息数であった。St.6(津ノ森)は200m以上沖でも約30%の生息があり、沖50m、沖50〜200mとの差は認められなかった。St.7(来待)は沖50mまでに57%、沖50〜200mに21%、200m以上沖に22%であった。St.8(鳥ヶ崎)は渚沖50mまで、沖50〜200m、200m以上沖にほぼ同じ様に生息していた。St.9(長江)は渚沖50mまでに71%、50〜200mに23%、200m以上沖は6%であった。St.10(玉湯)は渚沖200mまでに99%生息し、それ以上沖はほとんどみられなかった。St.11(玉造)はSt.10と同様渚沖200までに99%生息していた。St.12(嫁ヶ島)は渚沖50mまでに33%、沖50〜200mに47%、200m以上沖は20%の生息数がみられた。生息数の著しく多いSt.13(松江温泉)では渚沖50mまでに39%、沖50〜200mに52%、200m以上沖には8%であった。稚貝、幼貝の生息は成貝と比較して渚沖200mまでに多くみられた。
表11. 漁場のヤマトシジミ斃死数、斃死率(1998年8月22日、23日調査)
スミス・マッキンタイヤ採泥器で岸から沖50mまで、50〜200m、200m以上沖の漁場で各5本採集、底平面積7500cm2(500cm2×5本×3)当りの斃死数、( )は1m2当りの斃死数、斃死率(%)
| 調査地点名 |
殻長(mm) |
| 2〜<5 |
% |
5〜<8 |
% |
8〜<15 |
% |
15〜<17 |
% |
17〜<30 |
% |
計 |
% |
| St.1 |
(平田) |
1 |
(1) |
25 |
2 |
(3) |
22 |
6 |
(8) |
40 |
2 |
(3) |
10 |
12 |
(16) |
38 |
23 |
(31) |
28 |
| St.2 |
(斐川) |
1 |
(1) |
50 |
1 |
(1) |
4 |
14 |
(19) |
38 |
6 |
(8) |
16 |
1 |
(1) |
3 |
23 |
(31) |
9 |
| St.3 |
(一畑口) |
5 |
(7) |
33 |
33 |
(44) |
57 |
107 |
(143) |
72 |
28 |
(37) |
68 |
77 |
(103) |
84 |
250 |
(334) |
71 |
| St.4 |
(伊野) |
8 |
(11) |
38 |
14 |
(19) |
23 |
100 |
(133) |
37 |
64 |
(85) |
44 |
131 |
(175) |
48 |
317 |
(423) |
41 |
| St.5 |
(白石) |
1 |
(1) |
3 |
12 |
(16) |
18 |
94 |
(125) |
25 |
28 |
(37) |
23 |
24 |
(32) |
19 |
159 |
(212) |
19 |
| St.6 |
(津ノ森) |
42 |
(56) |
58 |
0 |
(0) |
0 |
11 |
(15) |
4 |
1 |
(1) |
2 |
3 |
(4) |
4 |
57 |
(76) |
11 |
| St.7 |
(来待) |
5 |
(7) |
6 |
7 |
(9) |
8 |
73 |
(97) |
10 |
33 |
(44) |
18 |
22 |
(29) |
18 |
140 |
(187) |
12 |
| St.8 |
(鳥ヶ崎) |
1 |
(1) |
1 |
10 |
(13) |
5 |
143 |
(191) |
14 |
73 |
(97) |
42 |
61 |
(81) |
66 |
288 |
(384) |
17 |
| St.9 |
(長江) |
0 |
(0) |
0 |
0 |
(0) |
0 |
13 |
(17) |
8 |
2 |
(3) |
4 |
7 |
(9) |
13 |
22 |
(29) |
6 |
| St.10 |
(玉湯) |
37 |
(49) |
33 |
97 |
(129) |
41 |
491 |
(655) |
38 |
34 |
(45) |
37 |
32 |
(43) |
34 |
691 |
(921) |
38 |
| St.11 |
(玉造) |
2 |
(3) |
1 |
9 |
(12) |
9 |
70 |
(93) |
9 |
13 |
(17) |
5 |
15 |
(20) |
5 |
109 |
(145) |
7 |
| St.12 |
(嫁ヶ島) |
0 |
(0) |
0 |
3 |
(4) |
2 |
92 |
(123) |
8 |
33 |
(44) |
17 |
23 |
(31) |
15 |
151 |
(202) |
9 |
| St.13 |
(松江温泉) |
0 |
(0) |
0 |
1 |
(1) |
1 |
88 |
(117) |
5 |
34 |
(45) |
6 |
21 |
(28) |
5 |
144 |
(192) |
5 |
|
表12. 1998年の漁場の水域別ヤマトシジミ斃死数と斃死率(1998年8月22日、23日調査)
スミス・マッキンタイヤ採泥器で採集、底平面積2500cm2(500cm2×5本)当りの斃死数、( )は1m2当りの斃死数、斃死率(%)
| 調査地点名 |
水深(m) |
殻長(mm) |
| 2〜<5 |
% |
5〜<8 |
% |
8〜<15 |
% |
15〜<17 |
% |
17〜<30 |
% |
計 |
% |
St.1
(平田) |
a |
1.0 |
1 |
(4) |
25 |
0 |
(0) |
0 |
4 |
(16) |
31 |
1 |
(4) |
5 |
1 |
(4) |
5 |
7 |
(28) |
11 |
| b |
1.8 |
0 |
(0) |
0 |
2 |
(8) |
67 |
2 |
(8) |
100 |
1 |
(4) |
100 |
6 |
(24) |
75 |
11 |
(44) |
79 |
| c |
2.4 |
0 |
(0) |
0 |
0 |
(0) |
0 |
0 |
(0) |
0 |
0 |
(0) |
0 |
5 |
(20) |
83 |
5 |
(20) |
83 |
St.2
(斐川) |
a |
2.1 |
1 |
(4) |
50 |
1 |
(4) |
7 |
10 |
(40) |
12 |
3 |
(12) |
20 |
0 |
(0) |
0 |
15 |
(60) |
12 |
| b |
2.6 |
0 |
(0) |
0 |
0 |
(0) |
0 |
3 |
(12) |
5 |
2 |
(8) |
11 |
0 |
(0) |
0 |
5 |
(20) |
5 |
| c |
3.5 |
0 |
(0) |
0 |
0 |
(0) |
0 |
1 |
(4) |
10 |
1 |
(4) |
25 |
1 |
(4) |
13 |
3 |
(12) |
13 |
St.3
(一畑口) |
a |
1.6 |
4 |
(16) |
57 |
30 |
(120) |
73 |
86 |
(344) |
77 |
12 |
(48) |
29 |
26 |
(104) |
74 |
158 |
(632) |
75 |
| b |
1.9 |
1 |
(4) |
13 |
2 |
(8) |
13 |
9 |
(36) |
38 |
12 |
(48) |
60 |
5 |
(20) |
42 |
29 |
(116) |
36 |
| c |
2.8 |
0 |
(0) |
0 |
1 |
(4) |
100 |
12 |
(48) |
92 |
4 |
(16) |
100 |
46 |
(184) |
100 |
63 |
(252) |
98 |
St.4
(伊野) |
a |
2.1 |
3 |
(12) |
50 |
4 |
(16) |
17 |
23 |
(92) |
34 |
11 |
(44) |
37 |
12 |
(48) |
39 |
53 |
(212) |
33 |
| b |
2.6 |
4 |
(16) |
31 |
7 |
(28) |
24 |
13 |
(52) |
20 |
21 |
(84) |
44 |
43 |
(172) |
44 |
88 |
(352) |
35 |
| c |
3.3 |
1 |
(4) |
50 |
3 |
(12) |
43 |
64 |
(256) |
47 |
32 |
(128) |
48 |
76 |
(304) |
52 |
176 |
(704) |
49 |
St.5
(白石) |
a |
1.7 |
0 |
(0) |
0 |
4 |
(16) |
12 |
34 |
(136) |
10 |
12 |
(48) |
12 |
11 |
(44) |
12 |
61 |
(244) |
11 |
| b |
3.1 |
1 |
(4) |
9 |
8 |
(32) |
36 |
51 |
(204) |
58 |
11 |
(44) |
92 |
13 |
(52) |
43 |
84 |
(336) |
52 |
| c |
4.0 |
0 |
(0) |
0 |
0 |
(0) |
0 |
9 |
(36) |
15 |
5 |
(20) |
38 |
0 |
(0) |
0 |
14 |
(56) |
15 |
St.6
(津ノ森) |
a |
1.6 |
0 |
(0) |
0 |
0 |
(0) |
0 |
0 |
(0) |
0 |
0 |
(0) |
0 |
0 |
(0) |
0 |
0 |
(0) |
0 |
| b |
2.8 |
42 |
(168) |
72 |
0 |
(0) |
0 |
10 |
(40) |
8 |
1 |
(4) |
94 |
2 |
(8) |
13 |
55 |
(220) |
23 |
| c |
3.9 |
0 |
(0) |
0 |
0 |
(0) |
0 |
1 |
(4) |
1 |
0 |
(0) |
0 |
1 |
(4) |
3 |
2 |
(8) |
1 |
St.7
(来待) |
a |
2.1 |
1 |
(4) |
3 |
2 |
(8) |
4 |
9 |
(36) |
2 |
1 |
(4) |
1 |
2 |
(8) |
3 |
15 |
(60) |
2 |
| b |
2.8 |
2 |
(8) |
8 |
1 |
(4) |
5 |
23 |
(92) |
15 |
14 |
(56) |
34 |
7 |
(28) |
32 |
47 |
(188) |
18 |
| c |
3.3 |
2 |
(8) |
8 |
4 |
(16) |
25 |
41 |
(164) |
22 |
18 |
(72) |
40 |
13 |
(52) |
38 |
78 |
(312) |
25 |
St.8
(鳥ヶ崎) |
a |
1.2 |
0 |
(0) |
0 |
1 |
(4) |
2 |
3 |
(12) |
1 |
4 |
(16) |
6 |
2 |
(8) |
13 |
10 |
(40) |
2 |
| b |
3.2 |
0 |
(0) |
0 |
3 |
(12) |
5 |
52 |
(208) |
14 |
23 |
(92) |
52 |
30 |
(120) |
77 |
108 |
(432) |
19 |
| c |
4.1 |
1 |
(4) |
2 |
6 |
(24) |
9 |
88 |
(352) |
23 |
46 |
(184) |
69 |
29 |
(116) |
74 |
170 |
(680) |
28 |
St.9
(長江) |
a |
1.9 |
0 |
(0) |
0 |
0 |
(0) |
0 |
1 |
(4) |
1 |
1 |
(4) |
3 |
4 |
(16) |
10 |
6 |
(24) |
2 |
| b |
3.6 |
0 |
(0) |
0 |
0 |
(0) |
0 |
11 |
(44) |
20 |
1 |
(4) |
8 |
3 |
(12) |
25 |
15 |
(60) |
16 |
| c |
4.0 |
0 |
(0) |
0 |
0 |
(0) |
0 |
1 |
(4) |
7 |
0 |
(0) |
0 |
0 |
(0) |
0 |
1 |
(4) |
5 |
St.10
(玉湯) |
a |
1.8 |
5 |
(20) |
10 |
8 |
(32) |
8 |
46 |
(184) |
6 |
8 |
(32) |
14 |
8 |
(32) |
15 |
75 |
(300) |
8 |
| b |
3.2 |
2 |
(8) |
7 |
41 |
(164) |
51 |
218 |
(872) |
62 |
19 |
(76) |
66 |
16 |
(64) |
48 |
296 |
(1184) |
56 |
| c |
4.0 |
30 |
(120) |
88 |
48 |
(192) |
94 |
227 |
(908) |
97 |
7 |
(28) |
100 |
8 |
(32) |
100 |
320 |
(1280) |
96 |
St.11
(玉造) |
a |
1.8 |
2 |
(8) |
2 |
5 |
(20) |
13 |
43 |
(172) |
13 |
9 |
(36) |
10 |
8 |
(32) |
11 |
67 |
(268) |
10 |
| b |
2.8 |
0 |
(0) |
0 |
0 |
(0) |
0 |
6 |
(24) |
2 |
3 |
(12) |
2 |
3 |
(12) |
1 |
12 |
(48) |
1 |
| c |
4.2 |
0 |
(0) |
0 |
4 |
(16) |
57 |
21 |
(84) |
88 |
1 |
(4) |
100 |
4 |
(16) |
100 |
30 |
(120) |
83 |
St.12
(嫁ヶ島) |
a |
1.7 |
0 |
(0) |
0 |
0 |
(0) |
0 |
26 |
(104) |
7 |
5 |
(20) |
12 |
5 |
(20) |
11 |
36 |
(144) |
7 |
| b |
1.8 |
0 |
(0) |
0 |
0 |
(0) |
0 |
30 |
(120) |
6 |
13 |
(52) |
12 |
6 |
(24) |
9 |
49 |
(196) |
7 |
| c |
3.7 |
0 |
(0) |
0 |
3 |
(12) |
5 |
36 |
(144) |
19 |
15 |
(60) |
34 |
12 |
(48) |
27 |
66 |
(264) |
18 |
St.13
(松江温泉) |
a |
1.9 |
0 |
(0) |
0 |
1 |
(4) |
2 |
45 |
(180) |
6 |
18 |
(72) |
8 |
8 |
(32) |
4 |
72 |
(288) |
6 |
| b |
2.0 |
0 |
(0) |
0 |
0 |
(0) |
0 |
43 |
(172) |
4 |
15 |
(60) |
4 |
13 |
(52) |
5 |
71 |
(284) |
4 |
| c |
3.8 |
0 |
(0) |
0 |
0 |
(0) |
0 |
0 |
(0) |
0 |
1 |
(4) |
4 |
0 |
(0) |
0 |
1 |
(4) |
0 |
|
a:岸より沖50mまで、 b:岸より沖50m〜200m、 c:岸より200m以上沖
|
表13.
|
1998年の漁場の水域別ヤマトシジミ斃死数と斃死状態(貝殻を開、閉)
(1998年8月22日、23日調査)
|
|
スミス・マッキンタイヤ採泥器で採集、底平面積2500cm2(500cm2×5本)当りの斃死数、( )は1m2当りの斃死数
|
|
(拡大画面:127KB)
|
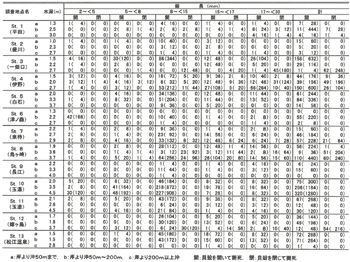 |
漁場のシジミの斃死率は、宍道湖西部のSt.1(平田)では平均28%で前年とほぼ同率で、渚沖50m以上沖では79〜83%の斃死率であった。斃死状態は貝殻を開いたもの、閉じたもの両方が認められた。St.2(斐川)は平均斃死率9%で、渚沖50m、50〜200m,200m以上沖の漁場も差がなかった。斃死状態はすべて貝殻を開いていた。St.3(一畑口)は平均斃死率71%と前年の斃死より高く、渚沖50mまでの漁場で75%、200m以上沖では98%の斃死がみられた。斃死状態は渚沖200mまでの漁場ではすべて貝殻を開いて、200m以上沖では、ほとんど貝殻を閉じて斃死していた。湖北のSt.4(伊野)の平均斃死率は41%で、渚沖50mまで33%、50〜200m35%、200m以上沖49%と、前年とほとんど同率であった。斃死状態は貝殻と開いたもの、閉じたもの両方の斃死がみられた。St.6(津ノ森)の漁場は、平均斃死率11%で、前年より低く、斃死貝はいずれも貝殻を開いて斃死していた。St.9(長江)は平均斃死率6%で、前年に比べて低く、斃死貝はすべて貝殻を開いて斃死していた。湖南のSt.5(白石)の平均斃死率は19%で、前年の56%に比較すると斃死数の減少がみられた。斃死はすべて貝殻を開いていた。St.7(来待)の平均斃死率は12%で、斃死数も1m2当り312個体で前年の1/6であった。斃死状態は、渚200mまではすべて貝殻を開いた状態、200m以上沖では貝殻を開いたもの、閉じたもの両方認められた。St.8(鳥ヶ崎)は平均斃死率17%、斃死680個体/m2で、前年の1/2であった。斃死状態は渚沖50mまでは貝殻を開いた状態、50m以上沖は貝殻を閉じたもの、開いたもの両方がみられた。St.10(玉湯)平均斃死率38%で斃死数も921個体/m2と多く、渚沖50〜200mは56%、200m以上沖は96%の斃死がみられた。斃死貝はすべて貝殻を開いていた。St.11(玉造)は平均斃死率7%で、斃死数も145個体/m2で、いずれも貝殻を開いて斃死していた。St.12(嫁ヶ島)は平均斃死率9%、斃死202個体/m2で、渚沖200mまではいずれも貝殼を開いて斃死し、200m以上沖は貝殼を閉じたもの、開いたものの両方がみられた。St.13(松江温泉)は平均斃死率5%で、斃死数192個体/m2と、前年に比較して低値であった。斃死状態はいずれも貝殼を開いて斃死していた。
以上の様に宍道湖のシジミ漁場のヤマトシジミ斃死は1998年もみられ、St.1(平田)、St.3(一畑口)、St.4(伊野)、St.10(玉湯)の漁場では昨年(1997年)と同様の大量斃死がみられた。他の漁場では大量斃死は軽減化していた。
|