|
4)中海における夏季の物質収支
貧酸素水塊が最も発達する7〜9月の3ヶ月を対象に、中海における環境修復策による水質改善効果を、窒素と酸素の物質循環図(図2.13)を作成し考察した。対象範囲は中浦水門以南〜大橋川入口に至る本庄工区を除く中海全域で、シミュレーション結果から3ケ月間の窒素循環および酸素循環を算出した。それによると、窒素、酸素循環ともに、昨年度の検討ケースと同等な水質改善効果が確認された。
窒素循環は、現況と比較して底泥からの溶出量が減少している様子が顕著に伺え、中浦水門から米子湾に至る浚渫窪地を埋め戻した効果が見受けられた。栄養塩が減少することに伴い、植物プランクトン等の現存量も減少し、中海全体の窒素循環も穏やかになっていることがわかった。一方、ホトトギスガイ現存量が増加しており、浅場造成による貝類資源の増加と、浚渫部分を埋め戻したことによる貧酸素水塊の軽減が効果として現れている。また、ホトトギスガイ現存量が増加に伴い、濾過量および排泄量が増加し、中海全体の浄化機能が向上していることがわかった。
次に酸素循環は、貧酸素水塊が発達する底層とそれ以外の上層とに分け、鉛直的な物質収支の違いについても考察した。現況と比較して底泥への酸素消費量が減少している様子が顕著に伺え、中浦水門から米子湾に至る浚渫窪地を埋め戻した効果が見受けられた。しかし、環境水中のDOが増加するものの、植物プランクトン等の現存量が減少するため、中海全体の酸素循環量としては減少していることがわかった。一方、浅場造成に伴いホトトギスガイの現存量が増加したため、DOが増加する結果となった。これは、窒素循環で示したように植物プランクトンを始めとする懸濁物量の減少に伴い、デトリタスの分解やプランクトンの呼吸で消費される酸素量が減少したためと考えられる。このように、浅場造成を実施し貝類資源量が増加することに伴い、水質浄化のみでなく貧酸素化の抑制にも役立つことが示唆された。
図2.13(1)シミュレーション結果から算出した中海の7〜9月の窒素循環
現存量の単位はton N、フラックスの単位はton N/day.
|
(拡大画面:101KB)
|
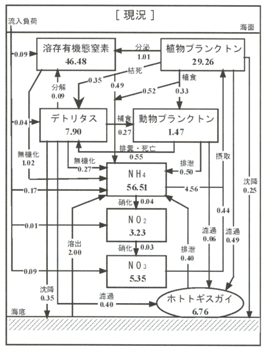 |
|
(拡大画面:97KB)
|
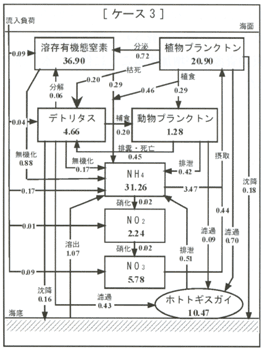 |
|
(拡大画面:102KB)
|
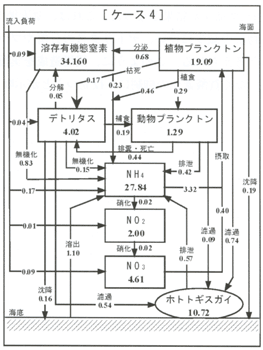 |
図2.13(2)シミュレーション結果から算出した中海の7〜9月の酸素循環
現存量の単位はton O2、フラックスの単位はton O2/day.
|
(拡大画面:84KB)
|
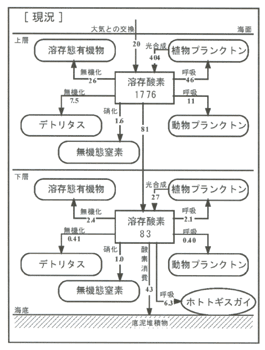 |
|
(拡大画面:82KB)
|
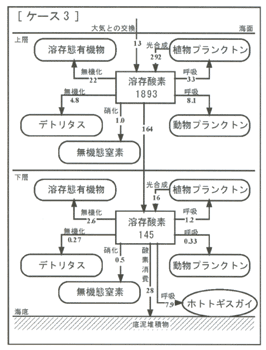 |
|
(拡大画面:85KB)
|
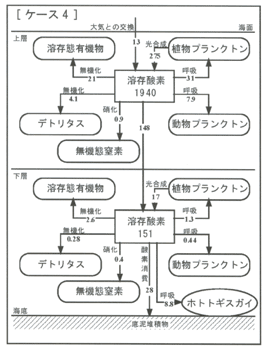 |
|