|
4)流動の変化(ケース3、4)
ここでは中海の流動、特に底層の流れに着目して、環境修復後の流動変化について検討した。ケース3および4における底層(計算の海底直上層)の流速ベクトルについて、昨年度と同様観測日の中から8月5日を選び、図2.7(1)に示した。
ケース3では中浦水門からの流量は減少している様子が伺え、昨年度と同様な変化を示すようになった。しかし、ケース4では中央閘門のみでも中浦水門からも流入してくる様子が伺えた。これは、計算では上げ潮時に全面開放、下げ潮時に全面閉鎖としているが、全面開放時に下層から逆流入があるものではないかと考えられ、今後の課題である。しかし、ケース1、2と比較しても、ケース3、4は昨年度と同様な流動変化となった。
5)塩分の変化(ケース3、4)
ここでは中海底層の塩分に着目して、環境修復後の塩分変化について検討した。ケース3および4における底層の塩分変化(検討ケース―現況)について、昨年度と同様観測日の中から8月5日を選び、図2.7(2)に示した。
ケース3では中浦水門を中央閘門のみとしたため、高塩分水が流入し難くなり、昨年度と同様な変化を示すようになった。しかし、ケース4では中央閘門のみでも中浦水門からも高塩分水が流入してくる様子が伺えた。しかし、ケース1、2と比較しても、ケース3、4は昨年度と同様な塩分変化となった。
6)DOの変化(ケース3、4)
ここでは中海底層の溶存酸素に着目して、環境修復後のDO変化について検討した。ケース3および4における底層のDO変化(検討ケース―現況)について、昨年度と同様観測日の中から8月5日を選び、図2.7(3)に示した。
ケース3では中浦水門を中央閘門のみとしたため、高酸素水が流入し難くなるため中浦水門南部で減少し、昨年度と同様な変化を示すようになった。ケース4では酸素消費を抑制した浚渫後窪地を中心とした米子湾方面でDOの増加が予測された。また、両ケースとも大海崎堤開削による本庄工区からの高酸素水の流入が予測され、ケース1、2と比較しても、ケース3、4は昨年度と同様なDO変化となった。
図2.7(1)基礎的な改善効果検討結果(ケース3、4の流動変化)
底層の流速ベクトル、1998年8月5日
|
(拡大画面:73KB)
|
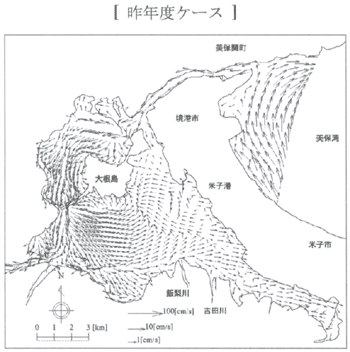 |
|
(拡大画面:69KB)
|
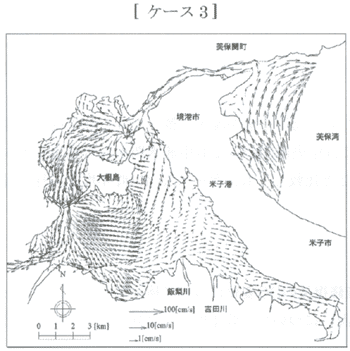 |
|
(拡大画面:87KB)
|
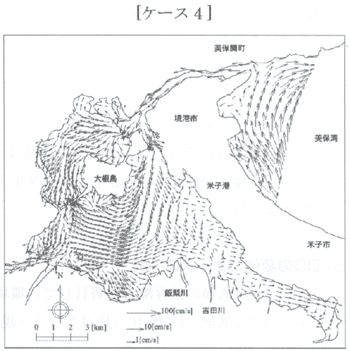 |
|