|
宍道湖・中海環境修復案検討シミュレーション
1. 概要
1.1 目的
宍道湖・中海の環境を改善するための様々な修復案が提案されている中で、平成13年度は貧酸素水塊を軽減するための3ケースの修復案について、改善効果を定量的に評価・検討するシミュレーション調査を行い、堤防開削による海水流入の浄化効果が示された。この結果を受けて平成14年度は、中浦水門における流量操作に着目した環境修復シミュレーションを実施することにより、更なる宍道湖・中海の環境改善効果を検討した。
1.2 作業項目
1)環境修復後の流動および水質シミュレーション
2)解析結果の可視化
1.3 作業内容
1)環境修復後の流動および水質シミュレーション
中浦水門の流量操作に関して、環境修復策を講じた場合の流動および水質シミュレーションを実施した。計算期間は、中海の貧酸素化が顕著な1998年5月〜10月の6ヶ月間としたが、基礎的な改善効果を検討するため、8月1ヶ月間の計算を先行して実施し、中浦水門の操作条件を決定した。昨年度実施したケース3(中浦水門に潜提設置+本庄工区の開削+米子湾窪地の埋め戻し+中海南西部に浅場造成)を基本ケースとし、中浦水門の潜提条件を水門操作の条件に設定しなおし、改善効果を検討した。基本的な条件は昨年度同様とし、環境修復策を講じた場合の流動変化および水質改善を予測した。現況解析結果と対比して流向・流速や海水交換量、水塊構造(水温・塩分)の変化を調べ、物理環境の改善効果を検討すると同時に、夏季に中海で広範囲に発達する貧酸素水塊の改善状況を検討した。
2)環境修復策の効果予測
流動と貧酸素水塊の予測結果は、CGを利用してわかりやすく可視化した。流況シミュレーションについては、漂流粒子の追跡により流れの変動を表現した。貧酸素水塊の挙動については、2ml/l(=2.8mg/L)以下の領域に着目して、その出現状況を表現した。
2. 環境修復後の流動および水質シミュレーション
2.1 計算条件
1)基本条件
基本条件は昨年度と同様、以下の通り。
|
・対象域:
|
宍道湖から中海を経て美保湾に至る南北約27km×東西44kmの汽水域。 水平格子は70〜500m(図2.1)。中浦水門付近は最小格子とする。 |
|
|
鉛直6層区分(表2.1)。 |
|
・解析期間:
|
貧酸素化が顕著な1998年5月1日〜1998年10月31日。 |
|
・解析期間: |
美保湾潮位や斐伊川流量および気象等の入力条件は、すべて実測データを使用し、計算期間の日々の変動を設定する。 |
表2.1 鉛直層区分
| 層番号 |
水深位置(m) |
厚さ(m) |
| 1 |
海面〜−1.5 |
1.5 |
| 2 |
−1.5〜−3 |
1.5 |
| 3 |
−3〜−4.5 |
1.5 |
| 4 |
−4.5〜−6 |
15. |
| 5 |
−6〜−8 |
2 |
| 6 |
−8〜海底 |
B−8 |
|
図2.1 宍道湖・中海水系の水平計算メッシュ(幅70〜500m)
|
(拡大画面:63KB)
|
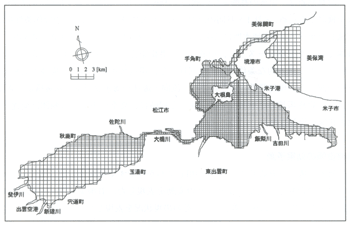 |
2)環境修復策
中浦水門の流量操作に関しての環境修復策として、以下に示す案を検討した。昨年度実施したケース3(図2.2:中浦水門に潜提設置+本庄工区の開削+米子湾窪地の埋め戻し+中海南西部に浅場造成)を基本ケースとし、中浦水門の潜提条件を以下の条件に変更した。
まず、基礎的な改善効果を検討するため、8月の1ヶ月間に絞りケース1と2の解析を実施した。しかし先述になるが、中央航路部を全面開放したケース1と2では、昨年度と同様の効果が得られなかったため、改定案としてケース3と4を設定した。なお、中浦水門付近の計算メッシュは中浦水門構造図(図2.3)を参考に、左右の水門部と航路部について3つに分割した。中浦水門の操作条件は以下の4ケース(図2.4)。
|
・ケース1: |
下段ゲートを常時閉めた状態(中央航路部は全面開放) |
|
・ケース2: |
上げ潮時は全面閉鎖、下げ潮時は全面開放(中央航路部は全面開放) |
|
・ケース3: |
ケース1と同様(中央航路部は中央閘門のみを全面開放) |
|
・ケース4: |
ケース2と同様(中央航路部は中央閘門のみを全面開放) |
図2.3 中浦水門構造図
|
(拡大画面:252KB)
|
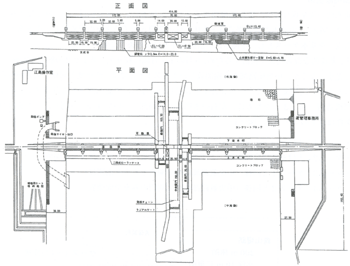 |
図2.4 中浦水門の計算条件(ケース1、2)
図2.4(続き) 中浦水門の計算条件(ケース3、4)
|