|
横型ドラム缶窯をつくり、竹炭をやく
横型ドラム缶窯を使うと、比較的簡単にわりとよい品質の竹炭をやくことができる。本窯に比べて炭化時間も8〜12時間と短く、半日でやき上がるのも大きな魅力。炭化操作の基本は他のやき方と変わらないが、気をつけておくべきことが幾つかある。細かい手順や必要な道具など基本的なことは『【アウトドア術】エコロジー炭やき指南』(創森社)を参照されたい。ここでは要点を中心に説明していくことにする。
●横型ドラム缶窯の二つのタイプ
横型ドラム缶窯には最もオーソドックスな、焚き口を外につけるタイプ(標準タイプ)と、焚き口をドラム缶の中に一体型として設置する、障壁のあるタイプ(改良タイプ)の2種類がある(41、43頁参照)。
改良タイプの利点は炭化操作の初めの段階の燃焼が楽に行えること、火がすぐに中に入っていくのであまり外からあおがなくてもよいことである。それに比べて標準タイプは点火の際にどんどんあおぐ必要があるが、最後の「ねらし」(精煉)がきくので比較的硬質の炭がやけるという利点がある。
障壁は収炭率を上げるために設置するもので、これがあると炭材が直接火に当たらないのであまり灰化せず、長いままで取り出せる。また、生火が炭材に直接当たるとボソボソのやわらかい炭になることが多いが、それも障壁によって防ぐことができる。
改良タイプはこの障壁が内蔵されているわけだが、標準タイプでも炭材を詰めたあとにドラム缶の大きさに切った障壁(41頁参照)を設置すれば同じようにやくことができる。ただ、障壁を入れるとたまに最後の「ねらし」がきかせにくいという難点があるので、高温でやき上げたい場合は障壁を使わないほうがうまくいく。
標準タイプのドラム缶窯。焚き口が外についている
改良タイプの炭材投入口
改良タイプで竹炭をやく
●炭材の準備
炭材として用いるのは3年生以上の竹。これをドラム缶に入る長さに玉切りし、竹割り鉈などで割り、節を簡単に取っておく。
かたい竹炭をつくりたいならば、肉厚の竹を用い、日光か煙でしっかり乾燥させておく。腐敗した竹を使うと炭化もうまく進行しないし、でき上がった炭もやわらかいものになってしまう。
ただ、肉厚の竹の場合はでき上がった炭の表面にでこぼこができることがあるので、それを防ぐためにもしっかりと事前に乾燥しておくことが大事となる。
割った竹をドラム缶に詰めるときには、できるだけ隙間なく、密に詰めることがポイント。節があると空隙ができてしまうので、できるだけ取り除いておく。
●窯の製作
標準タイプの場合
標準タイプには1本のドラム缶だけを使って窯をつくり上げる簡易タイプと、2本のドラム缶を使うしっかり密閉タイプがある。タイプの違いは蓋の違いによる。
簡易タイプは左の図のようにドラム缶の蓋から12〜15cmぐらいの所で切り取り、そのままそれを蓋として使うもの。蓋をはめ込むときには縁に角材などを当て、きちんとはまる場所に注意しながらげんのうで叩いてはめていく。ドラム缶が1個ですむのが最大のメリットだが、蓋をはめるときの作業が大変なことと、本体が変形してくると、なかなかうまくはまらなくなってしまうという難点がある。
しっかり密閉タイプはその蓋部分を改良したもので、蓋の丸い枠を残して前面をすべて切り取り、本体とする。蓋部分は別のドラム缶の丸い枠をつけて胴体のほうから切り取る。切り取ったあとは危なくないようきれいにバリを削っておくこと。
このタイプは本体、蓋とも枠が残っているので変形がないのが大きな利点。この二つの枠を合わせてバンドで挟み込み、ネジで締めて密閉する。
〔標準タイプの横型ドラム缶窯〕
| (拡大画面:67KB) |
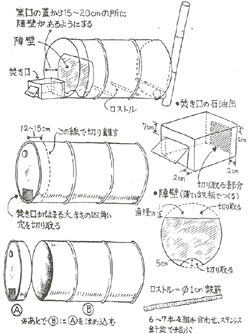 |
改良タイプの場合
改良タイプは東京都多摩市の高橋弘氏が考案したもので、口焚きや窯止めなどの操作のしやすさが特徴。製作には2本のドラム缶を使う。構造は図のとおりである。
この窯は前面が固定されており、上蓋をはずして炭材を入れ、できた炭も取り出す。煙突下部の煙を集める部分に水抜きがあり(図参照)、窯内部にも煙突にも水、タールがたまらない構造になっている。ただ、一旦下向きに煙道ができているので、この部分に屑炭などがたまらないよう、ロストル(火格子)に板をつけ、炭出し操作ごとにきれいに掃除することが必要。ここがふさがれてしまうと、煙は外に出ることができない。
煙突とロストルの関係
改良タイプは排煙口が底についているので問題ないが、標準タイプの場合、煙突の穴はすべての部分がロストルの下にくるようにする。煙突の穴(窯本体から煙が出ていく所)の一番上のラインまでしか煙はまわってこないので、その下は温度が上がらず炭化しないのだ。
ロストルは溶接しなくても、針金で交差部を結ぶだけでも十分用を足す。また、ロストルの網目は細かいほど詰め込み操作が楽にできる。
●煙突の取り付け
煙突は横づけ、下づけどちらでもよいが、煙突を通るうちに煙は冷却され水分が下にたまるので、その水分が抜けるような構造にしておくことが大事である。煙突の下に水分やタールがたまると煙が出にくくなるし、窯の下部にたまると窯の温度がなかなか上がらない原因となる。水抜きのためにT字形の煙突を使う方法もある。
煙突の下は地面に潜らせるが、タールがたまって水抜けが悪くなることもあるので、ときどき煙突の下を掘ってタールの膜を取り除くことができる構造になっているとよい。
T字形の煙突がなくてL字形を使う場合には、窯本体の地面に接する部分に何か所か穴を開けて水抜きとする。
煙突の角度は直角か少し寝かせ気味にする。竹は腐ってなけれま炭化がストップすることはそれほどないので、むしろ直角に立ててゆっくり炭化するようにしたほうがよい。
〔改良タイプの横型ドラム缶窯〕
| (拡大画面:76KB) |
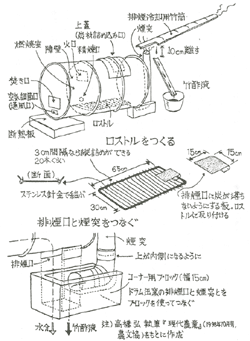 |
●炭材の詰め込み
炭材となる竹は肉の薄いものを下に、厚いものを上に入れる。炭化は原則として、上から始まり下に向かい、また、外側から始まり中心に向かう。肉厚のものはそれだけ炭化に時間がかかるので、初めに炭化が始まる上のほうに置いておくわけだ。できるだけ上と下の温度差を小さくして全体を一様に炭化させることが、良質の炭をやく重要なポイントである。ただ、ほとんど同じ厚みであれまそれほど神経質になることはない。
●口焚き
標準タイプの焚き口は一般的に石油缶(1斗缶)でつくってドラム缶にはめ込むが、この石油缶は熱を受けると上にかぶさった土の重みなどでたわんでしまうことが多い。周囲をレンガなどで補強するのも手だが、図(41頁)のように、石油缶の両側の蓋を少し残して切り取るとたわみにくくなる。もちろんその上にさらにレンガなどで補強すればもっと安心して使える。
改良タイプの焚き口は窯の中にある。窯が温まるまで火がつきにくいので、外でオキをつくって投入し、それから燃えやすいものを入れるとスムーズにいく。
改良タイプ・標準タイプとも初めはうちわなどで炭化室に火を送ってやることが必要。標準タイプで1〜2時間、改良タイプで1時間弱、炭材の乾燥具合や気候にもよるが、およそこれくらいの時間は燃材を入れながらあおぐつもりで。
やがて煙突から真っ白い煙が勢いよく出てくるようになればあおぐのをしばらくやめてみる。勢いが変わらないようだったら口焚きをやめてそのまま置き、煙の温度が75℃程度で、鼻をつんとつくにおいになれば、通風口だけにして窯口を閉じる。通風口の大きさはジュースの缶の大きさが目安。このときから竹酢液(ちくさくえき)も採り始める。
●炭化中の操作
一旦炭化が始まれば、そのままの状態で煙の勢いや温度が落ちないようにときどき見るだけでもよい。だが、前述したように上と下の温度差をできるだけ小さくして良質の竹炭をやこうとするなら、煙突口に板などを置いて煙の出る量を制限し、できるだけ窯の中で煙をぐるぐる循環させるようにしたい。
煙が熱媒体となって窯の中で炭化が進行するわけだから、すぐに煙を逃がすのはもったいない。ただし、あまり煙突を閉めすぎると、慣れないうちは炭化をストップさせてしまうこともあるが、煙の勢いが衰えないよう注意深く見守りながら、自分の勘を育てるつもりでできるだけ閉めてやきたいものだ。
出る煙の量を制限するとそれだけ炭化時間も長くなるので、いつごろ窯を止めるのか、スケジュールを考えながら煙突の閉め具合を加減する。
当初水気を含んで真っ白だった煙は5〜6時間もたつと次第に水分が抜け、茶色味を帯びてくる。においも辛く感じられるようになり、だんだん煙が薄くなってくる。炭化が終わりに近づくと、煙突の先の煙がだんだん透明になり、青色が濃くなってくる。においもエタンを含んだ、ちょっと甘い感じに変化してくる。この時点ではもう竹酢液の成分はほとんどなく、タール成分がほとんどで、採取装置が劣化してしまうので、竹酢液は採らないようにする。
●炭化終了ごろの操作(ねらし)・窯止め
炭化の始まりから最も早くて6時間、標準で8時時間、遅い場合(初めの口焚きがうまくいかなかったとき、または煙突をきつく閉めてやいたとき)で12時間以上で煙突口の先の煙が10cmぐらい透明になったら、ほとんど炭化が終了しているという合図。
ここで窯止めしても中はちゃんとした炭になっているが、ねらしをかけてキンキンのかたい竹炭をやく場合には、煙突から乾いた透明な熱気が吹き出てくるまで放置しておく。煙突に板などを置いて閉めてやいていた場合は、その板も取りはずして窯の温度が上がるようにする。このねらしの時間は1時間程度でよい。あまり長くやると炭が軽くなったり、燃えて表面がガサガサになってしまうので注意する。
窯を止めるときは窯口から閉じ、煙突から30分ほど煙を出してタールを逃がしたあとに煙突をふさぐようにする。煙突をふさぐにはロックウールや濡れ雑巾などの繊維を煙突口にかぶせ、その上にレンガなどの重しをのせるだけでよい。
●窯の冷却
焚き口と煙突口を閉じると窯の温度はどんどん下がっていく。時間があればゆっくりと冷ましたほうが、ヒビや割れの少ない炭が取り出せる。しかし、炭出しを早めたいときには、上の土をどけてドラム缶窯を裸にしたほうが早く冷える。
改良タイプの場合、上蓋と本体の隙間から空気が入らないように気をつけて上蓋の部分だけ土をどけてやる。およそ8時間で窯が冷え、取り出せる温度になる。
●炭出し
ドラム缶に手のひらを強く押し当て、熱くないようだったら炭を取り出してもよい。取り出すときは煙突口はふさいだまま、窯口(改良タイプの場合は上蓋)だけ開けて取り出す。煙突を開けると空気が中に入るため、まだ温かい炭に火がついてしまう危険があるからだ。
標準タイプの場合、障壁があればそれをまず取り除き、ロストルごと炭を取り出す。改良タイプの場合、上蓋をはずしてそこから少しずつ炭を取り出す。炭を取り出しながら、どの部分がよくやけて、どの部分があまりやけていないかなどをチエックし、窯のクセをつかむこと。取り出したあとは次の操作のために窯の中をきれいに掃除しておく。
理想的には、炭を取り出したら、すぐに次の炭材を詰めて火をつけたい。窯が空っぽだとドラム缶が劣化しやすくなるからだ。
取り出した炭はしばらく広げて冷ます。このときに火がつくことがあるので、水を必ず準備しておく。急に空気中の水分を吸うので、しばらく置いてから、炭の中の水分が安定したあとに袋などに詰めるようにする。 (広若 剛)
伏せやき法で穴を掘り、竹炭をやく
ある意味で最も難しいのが伏せやき法である。
スコップとトタン板、それに煙突さえあればどこでもできるが、ドラム缶窯のようにいつでもうまくいくとは限らない。
しかし、煙の状態、窯の状態を見ながらそのときどきの窯内の様子がどうなっているか、常に気を配りながら操作したあとに窯を開けるときのドキドキは他では味わえないものだ。それだけ自分の五感を総動員してやくので、でき上がりがうまくいってもいかなくても結構勉強になる。
ただし、炭化の進行を自分でコントロールするのはかなり経験を積まないと難しいので、標準的な大きさでやくときでも2日間は確保したい。以下、要点を中心に説明していく。
●穴を掘る
標準的な大きさの場合、風上を焚き口、風下を煙突側にして、幅1m×長さ2m×深さ30cm程度の穴を掘る。底は焚き口から煙突に向かって幾分上り勾配にして平らにならしておくと炭化がスムーズにいく。
側壁はスコップでできるだけ垂直に削り取る。これは燃材が上から下まで均一に詰められるようにするため。もし水分を多く含んだ土壌であれば、穴を掘ったあと、しばらく焚き火をして穴を乾燥させておいたほうがよい。
●基本構造をつくる
敷木
平らにならした底に敷木(しきぎ)を縦に2〜3列並べる。これは竹でもよいができれば肉厚の竹、またはレンガが望ましい。焚き口に近いほうはだんだん燃えてくるので、薄い竹だと焚き口がふさがってしまう。
この部分は土に接しているため完全には炭化しないので優良材を用いる必要はない。
焚き口と煙突
伏せやきで失敗する原因の主なものは焚き口あるいは煙突がふさがってガスの流れが悪くなり、炭化が途中でストップしてしまうことだ。逆に、眠っていたら窯の真ん中に穴が開いていてほとんど灰になってしまった、というのもある。
いずれにせよ窯と外部とのガス交換をするための穴がポイントなのだ。焚き口と煙突がふさがれないようになっていれば、伏せやきは80%は成功する。ではどうつくるのか。
焚き口部分はコンクリートブロックなど、熱に強い材料を使ってアーチ形にする。ブロック1個分の長さの焚き口にしておくと、あとで天井の土が落ちてきても焚き口がふさがれなくてすむ(図)。焚き口からすぐの所には根元部分の生の肉厚の竹など、燃焼に時間がかかるものを何列か置いておく。
煙突は直径12cm、長さ1mのものを用いる。煙突は10〜15度くらいの勾配をつけて壁に寝かせる。煙突の形に壁を少し削って煙突を安定させるとしっかりする。
大事なのは煙突の下部。図のように切り取るか、真っすぐ切って左右に開き、煙が入りやすいようにして底面に突き刺すようにする。敷木の高さより煙が入っていく穴が高くならないように気をつける(図)。逆だと下の炭材が炭化しにくい。
煙突を設置したら近くに炭材となる薄い竹を置き、まわりの土が落ち込んでこないように煙突の周囲に草を突っ込み、突いて固める。
ある程度の密度で固まったら、草は崩れずにそのまま炭化する。
〔伏せやき窯をつくるポイント〕
| (拡大画面:83KB) |
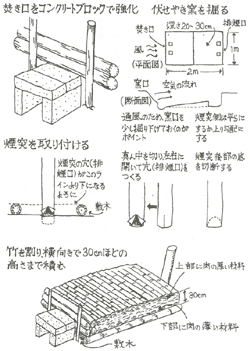 |
|