|
1. 竹の採取・調質法
(1)四年生以上の竹を選んで切る
炭材の調達は、まず竹林の間伐から始まる。むかしから番傘をさして歩けるくらいの隙間をつくるのが、竹林を間伐するときの目安とされている。竹林全体の風通しがよくなり、太陽の光が地表にさしこみ、微生物もよく繁殖し、おいしいタケノコが育つといわれている。
炭材用には四年生以上の竹がよいとされている。竹の生長は五年で止まるというのが定説で、それまでの期間は生長期とみなされる。外観からは生長しているような変化は確認できないが、竹は内部でしっかりと生長をつづけている。三年生未満の若竹は育ち盛りで、みずみずしく、含水率が高く、収縮率が大きく、変形率も高い。工芸作家はこの特性を巧みに利用して造形美を表現するが、炭やきには適さない。竹炭のばあいは、若竹・老竹を問わず、含水率の低い竹のほうが『割れ』の発生率も少なくなり収炭率も高くなる。
竹林で四年生以上の竹を見分けるには、節の部分の色と稈の太さ加減で判断する方法がある。節の部分が黒ずみ始めた竹、または根元に近い部分の稈の太さと稈丈全体の中央部に位置する稈の太さがほぼ同じくらいに生長した竹が、だいたい四年生以上の伐採適期の目安とされている。老竹になると、稈全体がアメ色を帯びてくる。
むかしは鋸(のこぎり)・手斧(ておの)を使って伐採していたが、最近は省力化と作業能率をよくするためにチェーンソーが伐採作業の主力となっている。切った竹の枝打ちには、庭木の剪定(せんてい)に使うハサミが便利である。
(2)長さ一メートルで裁断、綿紐で結束
伐採した炭材を竹林から窯場まで運ぶのは、林道にはいれる軽自動車が頼りだが、駐車場所までは人力で運ばなければならない。通常、五メートルくらいの長さに裁断すると運びやすいし、車にも積みやすい。最近は竹炭をやく女性も増えているので、体力に合わせて裁断寸法も短めに調整されている。
窯入れ前には、もう一度裁断し、竹割り・節取り・結束といった作業があるが、これらの作業もそれぞれに専用機があるので、これを導入すると作業が楽にはかどる。手作業で処理するばあいは、むかし竹細工をしたときの要領で、竹用鋸・鎌(かま)・手斧などが使われている。
裁断は窯の天井の高さなどを基準に一メートルくらい、または用途によって、それより短く裁断するばあいもある。竹割りも用途や竹の太さによって四分割・六分割されたり、筒状の形を活かすために縦割りされないこともある。
炭材を結束する理由は、束ねたほうが扱いやすく、作業能率がよくなることと、窯入れするときも隙間が少なくなり、収炭率も高まるからである。結束に使う紐の材質選びにも注意したい。機械で結束するばあい、紐の材質にはポリエチレン系の樹脂製が多いので、そのまま窯に入れて炭化すると、竹酢液に化学成分が混入するおそれがある。ビニール紐のばあいも同じだが、窯入れ時に紐だけ取りはずされることが多い。コンバインに付属しているイネ結束用の麻紐または綿紐がよい。
結束後、自然乾燥するばあい、その期間が二か月くらいなら麻紐でもよいが、それ以上の長期ストックになると、麻紐には腐朽菌やカビ菌がつき、切れやすくなる。綿紐は二年以上放置しても大丈夫という実験報告もある。
(3)自然乾燥では虫害に要注意
竹炭の品質は炭材に用いる竹の含水率の調整がポイントになる。伐採の適期は一年中でもつとも含水率の低い八月とされているが、それでも伐採後の自然乾燥で窯入れ時の適正含水率一五〜二〇パーセントに調質するには約六か月かかる。
自然乾燥中は雨に濡らさないことが条件で、必ず上屋根のあるところでおこなわれる。八月に切るもうひとつの理由は、この時期の竹には吸湿性を高める糖分やデンプンが少なく、乾燥しやすいこと、栄養分の少ない竹は虫にとっても魅力に乏しく、それだけ虫害が緩和されるというわけである。逆に糖分・デンプンが多いと、吸湿性が強くなり、含水率も上がり、乾燥を遅らせる。また、栄養分の豊富な竹はカビや虫の攻撃をうけやすくなる。
自然乾燥中の竹につく虫は、ヒラタケクイムシ・チビタケナガシンクイムシ・ニホンタケナガシンクイムシ・ベニカミキリなど約二五〇種類いるといわれている。用材に使う竹には防虫用の薬剤が使用されるが、炭材の竹には薬品は使えない。別掲のとおり、燻煙熱処理や乾燥焚きなどの調材作業によって、表面を燻竹にして忌避機能を強めたり、自然乾燥期間を短縮することが、虫害を避け、割れの少ない良質の竹炭をやくポイントである。
2. 簡易製炭法によるやき方
(1)土地さえあれば「伏せやき法」
伏せやき法は炭窯や炭化炉を使わず、地べたに穴を掘り、直(じか)に炭材を積み上げてやく、もっとも簡単な炭やき法である。作業の手順はつぎの要領でおこなう(図2−1)。
(1)湿気や石の多いところ、強風の吹き抜けるところなどは避けて場所を選ぶ。
(2)間口一メートル、奥行き二メートルくらいのスペースの地面に深さ二〇〜三〇センチの穴を掘る。
焚き口をブロックでつくり、煙突側を整え、曲がりつきの煙突を用意する。
(3)ロストル(火格子)の代わりに丸竹か棒切れを縦方向に二列に並べたのち、炭材を横方向に積み上げ、煙突を取りつける。
肉厚の薄い炭材、径の細い炭材は上部と下部に、中間には肉厚の厚い炭材を積む。
(4)枯れ草・枯れ葉・小枝・ワラなどを炭材の上にたっぷりと盛る。
(5)その上を古いムシロかトタン板で覆い、炭材が直に覆土に触れないようにして、最後に焚き口をのぞく全体を土で覆う。
(6)焚き口に燃材を入れ、それを燃やして着火させる。完全に着火してから焚き口を少しずつ閉めて炭化させる。
(7)煙突に竹酢液採取用の管を取りつけると、竹酢液が採取できる。
(8)煙の色が青くなり、さらに透明になってきたら焚き口をふさぎ、三〇分後には煙突口を閉じる。
(9)冷却してから覆土を取りのぞき、トタン板をはがし、やき上がった炭を取り出す。
(10)一晩、外気で冷ましてから梱包する。 この方法で炭をやくばあいの所要時間は、火入れするまでは二人で約二時間、着火後、炭出しまでは、炭材の量によって多少の差はあるが、だいたい八〜一〇時間である。
| (拡大画面:80KB) |
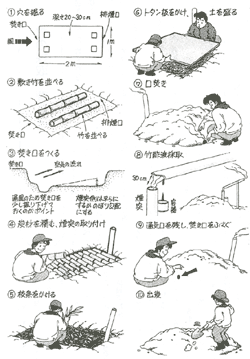 |
図2−1 伏せやき法
(2)どこでも使える移動炭化炉
炭やき場に設置される黒炭窯・白炭窯のほかに、場所を特定せずに、自由に移動して使える簡易炭化炉を用いた炭やきが各地でおこなわれている。
そのひとつに林野庁林業試験場(現在の森林総合研究所)で考案された通称『林試式移動炭化炉』がある。この炭化炉は、円形の炉壁部分を二つまたは三つに解体することができ、天井蓋・煙突も分離できる。解体後は同心円の炉壁を一つにまとめることができるので、比較的コンパクトになり、移動にも便利である。
炉の組み立て方・やき方は次のような手順でおこなう(図2−2・3)。
(1)よく乾燥した空き地で、火災の危険がなく、水の便がよく、周辺の住民に迷惑がかからない場所を選ぶ。
(2)場所が決まったら、整地して炉の最下段の円形壁の外側に排水溝を掘り、内側は円の中心から約三パーセントの勾配をもたせて炉底をつくる。
(3)円の中心に直径二〇センチのくぼみをつくり、炉の高さほどの長い乾燥した杭を四本ほど立て、炉底に敷木を放射状に並べる。
(4)炭材を下段から上段へ順に、縦方向に詰めこみ、最上段に上げ木(着火材)をのせる。
(5)上げ木に点火する。約一時間で火だねができるので、その時点で天井蓋をかぶせる。
初めは中央の煙突から白煙が出て、やがて約一時間経過すると着火し、下段の炉壁が熱くなる。
(6)下段に四本の煙突を金具で固定し、中央の煙突に蓋をしたとき、煙が勢いよく出ると着火は終了である。
(7)上下の炉壁のつなぎ目を砂や粘土で密閉する。煙突の下に容器を置くと竹酢液が採取できる。
(8)煙が青色に変わるまで、そのまま炭化をつづけ、通気口に火がみえるようになったら、煙突を交換し、煙の色がなると、順番に煙突をはずして、通気口を粘土でふさぐ。八か所の通気口を全部ふさいで消火し、冷めるのを待つ。
この炭やき法では、三〜四人で、同時に五〜六基を使って効率的な作業ができる。炭材の詰めこみから出炭までの所要時間は一〜二日である。
| (拡大画面:101KB) |
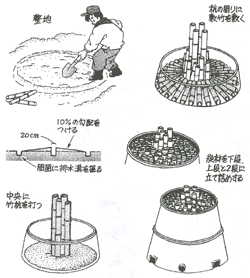 |
図2−2 移動炭化炉の整地から窯入れまで
| (拡大画面:85KB) |
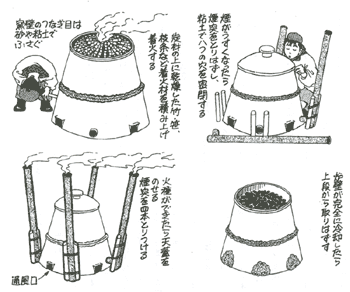 |
図2−3 移動炭化炉の着火から炭化終了まで
(3)意外にうまくいく「ドラム缶窯」
場所は庭先や空き地など、周囲の住民に迷惑をかけないところを選ぶ。炭やきをするときは、念のため所轄の消防署に『揚煙届』を提出しておくほうがよい。
ドラム缶は縦にして使うばあいと、横にして使うばあいがあるが、通常、次のように横型に据えつけて使うことが多い(図2−4)。
(1)ドラム缶の蓋の部分を切断してはずし、蓋に石油缶がはいる大きさの窓を切開する。焚き口となる石油缶は、底と蓋を抜いて、ドラム缶の蓋に二〜三センチはめこむ。ドラム缶の切断や熔接加工は素人にはムリなので、近くの鉄工所などに依頼する。
(2)ドラム缶の本体の底、つまり反対側の蓋に直径11センチの穴を開け、煙突と竹酢液採取装置を取りつける。石油缶や煙突の取りつけ部は、土のなかに埋めて密閉するので、熔接する必要はない。
(3)煙突は三つ口型で直径一〇センチ、長さ一メートルの市販品を用い、図のように取りつけると、ロストル(火格子)は使用しなくてもよい。曲がり煙突を使うと、炭化中に煙突に付着した液が缶内に逆流し、缶の底にたまるので、ロストルが必要になる。三つ口煙突を使うと、液は流れ落ちて外に排出されるので、排出口に容器を置くと竹酢液が効率よく採取できる。
(4)土を掘ってドラム缶を据え、杭を打ち、横木を組み、ドラム缶の側面に土を入れて缶全体を固定する。
(5)炭材は缶の奥行きに合わせて約八○センチに裁断し、隙間をつくらないように詰めこむ。肉厚の薄いものを下部に、厚めのものを上部に詰める。一度に七〇〜九〇キロの竹炭がやける。
蓋とドラム缶本体、また、焚き口と蓋の接続部は土で密閉する。ドラム缶本体の上にも土をかぶせる。冬季はよく乾燥させた土を使う。
(6)焚き口から燃材を入れて点火し、一〜二時間、口焚きすると、やがて着火する。
(7)着火したら焚き口をせばめて通風をおさえつつ炭化を進める。
(8)煙の色が青くなり、煙突口から約二〇センチ上部まで熱気が立ちのぼってきて、煙が出なくなったら、焚き口を閉める。これで炭化は終了する。
(9)ドラム缶のなかを冷やすために、上にかぶせた土を取りのぞく。
(10)蓋を開け、やき上がった炭を取り出す。
| (拡大画面:104KB) |
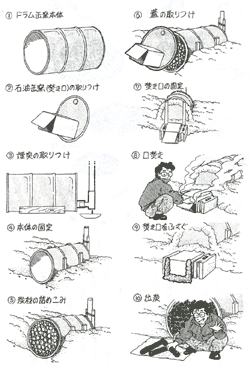 |
図2−4 ドラム缶を使った炭やき法
3. 簡易製炭法でやいた竹炭の使い方
竹炭と竹酢液の農業への利用例は、まだそれほど多くは報告されていないが、木炭・木酢液のばあいは、実用段階にはいって、すでに二〇数年になる。その範囲も水田・露地栽培・ハウス栽培・果実栽培・花卉(かき)栽培・茶の栽培などの利用へと広まっている。そして、土壌を改良して地力を高める効果、作物の生長・発根を促進させる効果、果実の糖分を増し、風味・色・ツヤをよくする効果などが実証され、いまでは減農薬・減化学肥料農法への重要なワンステップとして認知されるようになった。
(1)土壌改良効果
炭は昭和六十一(一九八六)年に政令三五四号で『地力増進法』の『土壌改良資材』に認定されている。竹炭・竹酢液の農業への有効利用についても、木炭・木酢液の実績に基づいて、そのまま踏襲され、各地で同じような効果が認められている。
多孔質の炭には微細な孔が無数にあいていて、そのすべてが外界に通じているので、水や空気を通しやすい。土壌に炭を粉状に砕いて入れると、土のなかの通気性がよくなり、透水性や保水性がよくなる。また、アンモニアガスなどとなって土から発散する窒素分を固定するはたらきもする。
竹炭の孔の表面には糸状菌、放線菌・バクテリアなどの有用な微生物が着生し、その微生物は土のなかの有機物を分解しながら、これを栄養分として増殖する。その結果、いっそう作物が育ちやすい土壌環境ができることになる。作物が育ちやすい土壌環境をつくることによって、作物そのものが丈夫になるので、それだけ農薬や化学肥料の使用量を減らすことができ、病虫害の発生も少なくなって、収穫量も確実に増加する。また、土のなかに残留している農薬や化学肥料の有害成分が吸着され、これも微生物によって分解される。
竹炭を土壌改良に使うばあい、製炭直後の新しいものより、一年くらい雨ざらしにしておいた炭のほうが早く効果があらわれる。竹炭はph値が約八・〇〜九・〇のアルカリ性を示すが、竹炭に含まれているミネラル成分は反応性が高く、イオン化しやすいので、一定の期間をおいて、反応性を弱めてから使ったほうが微生物が着生しやすくなる。ただし農薬や化学肥料の多用によってpH値が低くなっている土壌の酸性度の矯正には有効である。
(2)堆肥化期間の短縮
竹炭や竹酢液入りの堆肥をつくるばあい、特別な方法や技術を要するわけではなく、従来の堆肥の製法にしたがい、同じ要領でつくればよい。木炭・木酢液入りの堆肥の製法とも違いはない。
敷きワラ・木の葉・屎尿などの有機物と粉状に粉砕した竹炭を、だいたい二〜一対一の割合(容量比)で混ぜ、積んでおく、自然に発酵が進行する。 二〜三日後から有機物の糖分・デンプン質がバクテリアのエサとなって、分解が始まると、急速に発酵温度が上昇し、ときには八〇度くらいになることもある。温度が上がりすぎると、微生物が死ぬので、つねに五〇〜六〇度の範囲に保つように、適宜、切り返しをおこなうが、炭を入れると分解ガスを吸収するので、切り返しが不要となる。
堆肥に竹炭を混ぜることによって、有機物の分解が促進され、成熟までの時間が短縮される。多孔質の竹炭は微生物にとっても居心地のよいすみかとなるので、どんどん増殖し、活動も盛んになる。竹炭はアンモニアガスを吸着するので悪臭も防げる。炭の孔に吸着されたアンモニアガスは、そこに着生している微生物を増殖させ、発酵温度を八〇度以上に上昇させるので、耐熱バクテリアが発生する。この耐熱バクテリアはフザリウム菌やリゾクトニア菌など、立枯病原菌の発生を防ぐはたらきをする。
竹炭と竹酢液を加えた堆肥を施用すると、土のなかの微生物の増殖を助け、窒素分を固定するので、いっそう土になじみやすくなる。具体的な効果として、すでに苗立枯病などが発生しているばあい、育苗培土に容積比で三〜五パーセントの竹炭入り堆肥を混合し、定植前の一〜二週間前、耕耘土壌の容量に対して、容積比で〇・五パーセント程度、他の一般堆肥などといっしょに混合し、耕転すると、土壌・気象・作物などの条件により、多少の変動はあるが、顕著な改善効果が期待できる。
|