|
宍道湖・中海水域における魚類生態研究
〜コノシロ・サッパ・スズキの生態〜(その1)
宍道湖生物研究会
越川敏樹
はじめに
宍道湖・中海水域には、前者で80種、後者で100種程度の魚類の生息が確認されている。外海とつながる本水域にはさまざまな海洋性の魚種が来遊してくるので、本水域の生息魚種数をどの範囲まで含めるかは記載者の意図によるところが大きい。とは言っても、多くの魚種が生息する本水域は、高い生産性を持つとともに、多様性の面からも複雑な生態系を有しているといえる。
しかし、現在の本水域は多様性の面からみると、大きな問題を抱えている。現在の本水域における棲息魚種は、十数年前と比較して種類数においては大きな変化がないものの、個々の種を量的な面からみると大きく変化してきている。(2000、越川)
かつては、季節ごとにまとまった量で出現する魚種が多く、市場での季節感を提供していたが、現在はそのような魚は押し並べて激減傾向にあり、漁獲されて商取引される魚種は単純化している。減少の著しい魚種は、ワカサギをはじめヒイラギ・シラウオ・カタクチイワシ・マアジ(幼魚)、ビリンゴ・ウナギ・クロダイなど多種あり、漁業対象外の魚では、イトヨ・クルメサヨリ・トウゴロウイワシなどが相当する。
その結果として、増加もしくは減少の度合いが低くて、全体量の中に占める割合の高くなった魚種が相対的な優占魚種となってくる。それらの魚種としては、サッパ・コノシロ・スズキ・マハゼの4種が相当し、現在の本水域において優占的な地位を占めるにいたっている。以下、それらの4種を本水域の現在の優占種とみなすことができる。また、これらの4種の魚種は、相対的な増加だけでなく、生態的な面での変化も生じてきている。たとえば、これらの中の前3種は、美保湾〜中海〜宍道湖と季節的な回遊をし、水温の低下する冬季前には美保湾に戻るのが基本的なパターンであったが、現在は、越年して1月にも中海はもとより宍道湖においても滞留していることがある。マハゼにあっては、宍道湖で越冬して翌春そのまま生息する個体群も見られる。
よって、現在の宍道湖・中海水域の魚類生態を把握する上で、上記の優占的な4種の生態を捉えることは、当水域の魚類生態を把握する上での大きな手がかりになるものと判断した。また、そのことは、減少した魚種の原因の推定とともに、本水域の環境保全を考える上でも重要なことと思われる。
今回は、調査を開始して間がないことから、極めて初歩的な生態把握でしかないが、上記の3種は水温の上昇に伴って外海から中海に進入する時期にあたり、コノシロとサッパは産卵時期に入ることから、生態的に興味深い面を捉えることができた。そして、それは今後の本水域における魚類生態研究の基礎的な面も多いと思われる。
今回は、主に遊泳性の高い、サッパ・コノシロ・スズキの3種の生態面から得られた知見を記す。
1. 調査の方法
本庄工区内・論田・浜佐陀の3地点における漁獲内容に基づいて、サッパ・コノシロ・スズキの量を成魚(A)、未成魚(M)、幼魚(Y)を分類した上で大まかな量を定めた。
本庄工区の漁獲は、当地を拠点とするます網(小型定置網)漁を営む漁家の漁獲物を引き取る専門の鮮魚商の記録から上記の3種の量を抽出した。この場合、鮮魚商の取り扱い伝票をもとにした。当漁家は、本庄工区内の本庄町沖と西部承水路に3〜4基のます網を設置しており、ほぼ毎日網揚げをして漁獲物のほとんどを鮮魚商に出している。鮮魚商は、ほぼ全量を買い上げるが、大量に獲れすぎた場合は、その種の引き取りを制限することがある。コノシロがその対象になることがあった。
論田の場合は、専門漁師が毎朝出漁するます網漁の網揚げに月に2ないし3回立会い、漁獲内容から上記の3種の量を把握した。網を入れる場所は、岸から約200m沖に隣接して3基設置してあることが多かった。
浜佐陀では、月に2回日を決めて専門漁師に刺し網の設置を依頼し、漁獲物から上記の3種の量を確認した。多くの魚体の大きさに対応するように、網目の大きさは、スズキ用を3ないし4段階とワカサギ用やマハゼ用をそのときの状況によって複数張った。刺網で漁獲された魚は、食性調査用として、直ちに20パーセント程度の濃度のフォルマリンで固定した。尚、スズキなどの大型魚の場合は、内臓のみをフォルマリン液に漬けた。
2. 結果
(1)優占4種の出現と移動
春先の水温に伴って、多くの汽水性魚類が外海から中海・宍道湖に進入してくる。今回の報告は、その時期にあたる2001年4月から6月にかけての優占4種のうちの遊泳性の高いサッパ・コノシロ・スズキの出現状況を調べた。表−1は、本庄工区内のほぼ毎日のます網漁の内容をべースにして、論田のます網と浜佐陀の刺し網漁に同行した時の漁獲内容の記録とを時期を追って並べてある。
図−1 宍道湖・中海の概念図と調査地
<本庄工区>
3月末から5月下旬にかけてコノシロ(成魚)とスズキ(未成魚)が多く、5月下旬まで両種とも多くの量が漁獲された。サッパは前2種よりも約1ヵ月遅れて4月下旬より漁獲され以後6月いっぱい続いた。したがって、これらの3種がそろって多くとれた時期は、4月下旬から5月下旬までの約1ヵ月間であった。
<論田>
4月1日にコノシロ(成魚)が多獲されたが、それ以後成魚は、少量ずつの漁獲が続いた。時には、皆無であることもあった。期間中、成魚は少なかった。しかし、幼魚の場合は6月24日に初めて網に入ると、以降の網にはほとんどの場合多く漁獲された。スズキは、コノシロ同様に少なく、未成魚(セイゴ)と成魚(スズキ)はいつでも1桁台の匹数であった。しかし、今年生まれの幼魚が5月4日に初めて網に入ると、様相が変わってきた。初めに約1ヶ月間の幼魚の量は少なかったが、6月4日の網に100尾以上が入り、以後多獲が続いた。
サッパは、当初は少量ずつ毎回漁獲されていたが、5月20日にやや量が増え、以後多獲が続いた。本種の当年生まれの幼魚の出現は、スズキより約2ヵ月、またコノシロよりも約半月遅れて、7月8日(表を外れる)であった。
以上から、論田では幼魚の出現は、5月初旬のスズキに始まり、6月下旬のコノシロ、そして7月上旬のサッパと続いた。
<浜佐陀>
3月31日は、サッパとコノシロが少量漁獲され、スズキは皆無であった。しかし、門脇氏(当地の漁師)が数日前にしかけた網には数尾のスズキ(未成魚)がかかったので、宍道湖への遡上はすでに始まっているが量的には少ないと判断できる。
4月22日には、コノシロ・スズキともに多獲され、以後その状態が続いた。サッパは、上の2種に1ヶ月程度遅れて5月12日にやや多く獲れ、以後2回多獲された。本種は、上の2種に比べて、刺し網の場合漁獲される量に変動が大きい。(魚体のサイズと網目が合わないことがある)スズキの当歳魚は、5月27日に僅かに漁獲され、以後毎回極めて多くが網にかかった。コノシロの当歳魚は、8月29日の漁までは捕れなかった。これは、生息量は多くても、サッパと同様に網目が合わなかったことが原因と考えられる。
次に、上の3地点における上記3種の今年度の回遊のパターンを種別に整理すると、以下のようになる。
図−2 浜佐陀の刺網(上) 論田のます網(下)
(2)魚種ごとの回遊のパターン(4・5・6月)
《コノシロ》
本庄工区においては、調査開始の3月下旬にはすでに滞在しているが、宍道湖の浜佐陀では、この時期はまだ量的に少なく、約1ヵ月たった4月下旬から多く進入するようになる。中海南岸の論田では、4月初旬に多く入ったことから、本庄工区と同様にこのころすでに回遊しているが、その後は毎回極めて少量ずつしか漁獲されていない。そのことから、春先に外海から中海に入って来たコノシロの多くは、本庄工区を含む中海の北岸側を中心にしてそこで滞在し、水温の上昇とともに大挙して宍道湖に向かう。本種の本庄工区内における滞在は、5月下旬までが多く、それ以後は激減することから、多くの個体が宍道湖に向かうものと思われる。
表−1 3地点の漁獲内容 本庄工区内漁獲(ます網)
一部の群れは、南岸を回るが、その数は少ない。
当年生まれの幼魚の出現は、論田で6月下旬に全長5.5cmで初めて確認された。それ以後は、常時量的に多く漁獲された。複数の漁師からの聞き取りでは、中海においてそれ以前の幼稚魚の確認はなされておらず、孵化して間もない時期の生態は不明である。この点は、宍道湖においても同様であった。
成長は極めて早く、7月14日で全長5.5〜9.5cm(19尾)、7月29日で8.7〜12.3cm(15尾)、9月22日で15.7〜18.4cm(27尾)であった。
表−1 論田漁獲(ます網)
| 月日 |
4月1日 |
サッパ |
コノシロ |
スズキ |
| 水温 |
9.0℃ |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
| |
ステージ |
10 |
|
|
50 |
|
|
|
5 |
|
|
| 月日 |
4月14日 |
サッパ |
コノシロ |
スズキ |
| 水温 |
10.5℃ |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
| |
ステージ |
3 |
|
|
|
|
|
1 |
5 |
|
|
| 月日 |
5月4日 |
サッパ |
コノシロ |
スズキ |
| 水温 |
15.5℃ |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
| |
ステージ |
15 |
|
|
2 |
|
|
|
5 |
5 |
|
| 月日 |
5月20日 |
サッパ |
コノシロ |
スズキ |
| 水温 |
21.5℃ |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
| |
ステージ |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
| 月日 |
5月27日 |
サッパ |
コノシロ |
スズキ |
| 水温 |
22.0℃ |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
| |
ステージ |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 月日 |
6月4日 |
サッパ |
コノシロ |
スズキ |
| 水温 |
22.5℃ |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
| |
ステージ |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 月日 |
6月17日 |
サッパ |
コノシロ |
スズキ |
| 水温 |
23.0℃ |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
| |
ステージ |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
170 |
|
| 月日 |
6月24日 |
サッパ |
コノシロ |
スズキ |
| 水温 |
23.0℃ |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
| |
ステージ |
60 |
|
|
5 |
|
1 |
|
2 |
30 |
|
浜佐陀漁獲(刺網)
| 月日 |
3月31日 |
サッパ |
コノシロ |
スズキ |
| 水温 |
9.0℃ |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
| |
ステージ |
1 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
| 月日 |
4月22日 |
サッパ |
コノシロ |
スズキ |
| 水温 |
14.5℃ |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
| |
ステージ |
|
|
|
50 |
|
|
30 |
100 |
|
|
| 月日 |
5月5日 |
サッパ |
コノシロ |
スズキ |
| 水温 |
17.0℃ |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
| |
ステージ |
|
|
|
100 |
|
|
7 |
55 |
|
|
| 月日 |
5月12日 |
サッパ |
コノシロ |
スズキ |
| 水温 |
18.0℃ |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
| |
ステージ |
30 |
|
|
40 |
|
|
4 |
40 |
|
|
| 月日 |
5月26日 |
サッパ |
コノシロ |
スズキ |
| 水温 |
|
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
| |
ステージ |
100 |
|
|
100 |
100 |
|
|
100 |
l00 |
|
| 月日 |
6月7日 |
サッパ |
コノシロ |
スズキ |
| 水温 |
22.5℃ |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
| |
ステージ |
100 |
|
|
50 |
50 |
|
1 |
20 |
100 |
|
| 月日 |
6月23日 |
サッパ |
コノシロ |
スズキ |
| 水温 |
23.0℃ |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
A |
M |
Y |
| |
ステージ |
1 |
|
|
100 |
|
|
4 |
10 |
200 |
|
《スズキ》
コノシロと同様にほぼ同じ動きのパターンである。つまり、本庄工区で3月下旬よりすでに滞在し、4月下旬ごろから順次宍道湖に向かう。5月下旬以降は激減する。それに対して、宍道湖では中海からの遡上が活発になり、個体数が急増する。
中海南岸の論田では、コノシロ同様に毎回のように網に入っているが、その数は数尾程度と少ないことから、そもそも南岸域での個体数は北岸域や宍道湖と比較して少ないものと思われる。
当年生まれの幼魚の出現は、論田で5月初旬に確認されているが、量的には少なく、まとまって漁獲されるようになるのは、1ヵ月後の6月初旬であった。スズキの幼魚がコノシロの幼魚よりも1ヶ月程度早く回遊してくるのは、前者が冬生まれで外海から遡上する時期が、春生まれの後者より早いのは自然なことである。また、宍道湖では、5月下旬に初めて確認され、以後は常に多獲されており、棲息量は極めて多いと推定される。
表−2 3種の動き
優占3種の出現状況の模式図(2001年)
(拡大画面:50KB) |
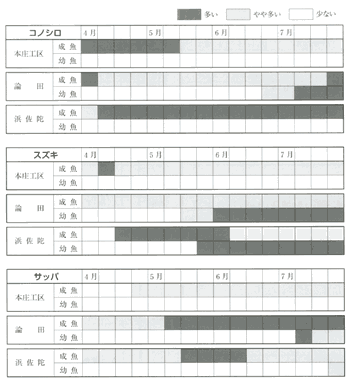 |
※ |
本庄工区の6月以降は未調査。浜佐陀は刺網漁なので幼魚の漁獲には不向きな面がある。 |
|