|
3.3 中海における夏季の物質収支
ここでは、貧酸素水塊が最も発達する7〜9月の3ヶ月間を対象に、中海における環境修復策による水質改善を窒素と酸素の物質収支に着目して考察した。対象範囲は中浦水門以南〜大橋川入口に至る本庄工区を除く中海全域で、シミュレーション結果から3ヶ月間の窒素循環および酸素循環を算出した。
まず、各修復ケースにおける窒素循環を図3.8に示した。現況とケース1を比較すると、底泥からの溶出量が減少している様子が顕著に伺え、中浦水門から米子湾に至る浚渫窪地を埋め戻した効果が見受けられた。栄養塩が減少することに伴い、植物プランクトン等の現存量も減少し、中海全体の窒素循環も穏やかになっていることがわかった。一方、ホトトギスガイ現存量が増加しているのは、浚渫部分を埋め戻したことにより貧酸素水塊が軽減されたためである。モデルでは、環境水中のDO濃度が1mg/Lを下回ると、貝類が斃死したと仮定して、現存量が半減し濾過や排泄等の代謝活動が停止するように設定されている。ケース1の同期間にDO濃度が1mg/L以下になる期間が少なくなったために、ホトトギスガイの現存量が現況と比較して増加したものと考えられる。しかし、ホトトギスガイの現存量が増加したものの、植物プランクトンを始めとする懸濁物質の現存量が減少したために、中海全域としての浄化機能は現況と同レベルのままであった。次に、現況とケース2を比較すると、ホトトギスガイの現存量が増加している様子が顕著に伺え、浅場造成に伴う貝類資源増加の効果が見受けられた。中海全体からみて造成面積としては僅かではあるが、貝類資源量が増加することに伴い、濾過量および排泄量が増加し、中海全体の浄化機能が向上していることがわかった。最後にケース3では、ケース1とケース2を複合した窒素循環を示している様子が伺えた。
次に、各修復ケースにおける酸素循環を図3.9に示した。酸素については、貧酸素水塊が発達する底層とそれ以外の上層とに分け、鉛直的な物質収支の違いについても考察した。現況とケース1を比較すると、底泥への酸素消費量が減少している様子が顕著に伺え、中浦水門から米子湾に至る浚渫窪地を埋め戻した効果が見受けられた。しかし、環境水中のDOが増加するものの、植物プランクトン等の現存量が減少するため、中海全体の酸素循環量としては減少していることがわかった。次に、現況とケース2を比較すると、浅場造成に伴いホトトギスガイの現存量が増加するため、ホトトギスガイによる呼吸消費が増加し中海のDOは減少すると思われたが、実際はDOが増加する結果となった。これは、窒素循環で示したように植物プランクトンを始めとする懸濁物量の減少に伴い、デトリタスの分解やプランクトンの呼吸で消費される酸素量が減少したためと考えられる。このように、浅場造成を実施し貝類資源量が増加することに伴い、水質浄化のみでなく貧酸素化の抑制にも役立つことが示唆された。最後にケース3では、ケース1とケース2を複合した酸素循環を示している様子が伺えた。
図3.8 |
シミュレーション結果から算出した中海の7〜9月の窒素循環 |
現存量の単位はton N、フラックスの単位はton N/day.
(拡大画面:133KB) |
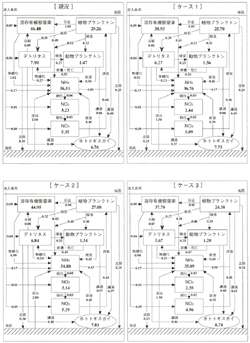 |
図3.9 |
シミュレーション結果から算出した中海の7〜9月の酸素循環 |
現存量の単位はton O2、フラックスの単位はton O2/day.
(拡大画面:124KB) |
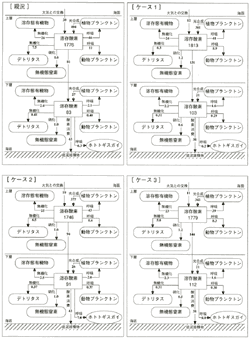 |
4. まとめ
宍道湖・中海の環境を改善するための様々な環境修復案が提案されている中で、夏季底層で形成される貧酸素水塊を軽減するための修復案について、改善効果を定量的に評価・検討するためのシミュレーション調査を行った。
まず、宍道湖・中海における流動および水温・塩分環境の季節的な変動特性を調べるため、1998年度対象にした流動シミュレーションを実施した。島根大学による実測データに基づいて、水温・塩分について解析結果の整合性を確認した。計算結果と観測値を比較すると、一部に若干の相違が認められたが、水塊変動の傾向、上下層間の勾配など合理的に再現された。
次に、宍道湖・中海における湖内の物質循環や貧酸素水塊の消長など、水質・生態系環境の特性を考慮するために、1998年度を対象にして水質・生態系シミュレーションを実施した。島根大学による実測データに基づいて、各水質項目について解析結果の整合性を確認した。観測値の時空間変動が激しく、決して十分な再現結果には至らなかったが、全体として観測値の季節変化の傾向をとらえることができた。溶存酸素については、表層および冬季の宍道湖底層では若干の相違が認められたが、成層期底層の貧酸素水塊は合理的に再現された。湖内の貧酸素水塊の分布状況に着目すると、中海では米子湾から6月上旬に貧酸素水塊が発生し、8〜10月にかけて中海全体に拡大、その後12月初旬まで米子湾付近に残っている様子が再現された。一方、宍道湖底層においても夏季は貧酸素化している様子が伺え、中海・宍道湖汽水系における酸素環境の季節変動が確認できた。
環境修復策として、貧酸素水の形成に関わる修復案を3ケース実施し、改善効果を検討した。現況解析と同じ条件設定で、環境修復策を講じた場合の流動変化および環境修復策による水質改善を予測した。環境イニシアティブ検討案複合によるケース1では、本庄工区の堤防を開削し、中浦水門に潜堤を設けたことによって、境水道〜森山堤を通り本庄工区に流入し、大海崎堤から中海に流入する進路に流れが変更した。潜堤の影響で中浦水門を通る流量が減るため、中海中央部から米子湾付近の水域では、高塩分水の影響が少なくなり、塩分は低下した。本庄工区においては、現況では穏やかな塩分変動であったが、森山堤を開削することによって美保湾の潮位変動の影響を強く受け、日々の塩分変動が激しくなった。一方、本庄工区と中海のほぼ全域でDOが増加し、中浦水門南部では減少した。
浅場造成を施したケース2では、浅場を造成した水域で流れが若干変化しているのが認められたが、その他の水域では大きな変化はなく、塩分変化も当該海域周辺に限定していた。一方、底層のDO変化は、浅場造成した周辺海域で最大3mg/L程度の増加がみられ、浅場造成による効果が現れていた。またケース3では、ケース1と2が複合した流れ場を形成している様子が伺えた。
シミュレーション結果から算出した夏季の窒素および酸素の物質収支からも、上述したような環境修復策による水質改善の効果が確認された。
本報告は、当研究所が2001年度日本財団助成を受け実施した「宍道湖・中海環境修復案検討シミュレーション」の中間報告を取りまとめたものです。このシミュレーションは(株)シーティーアイ社に研究所が示した条件下で委託した結果です。 |
|
|