|
4.5 自己反応性及び有機過酸化物分類フローチャートのスクリーニング化に関する研究
社団法人 日本海事検定協会
理化学分析センター
三菱化学 株式会社
科学技術研究センター
4.5.1 緒言
自己反応性物質及び有機過酸化物質(以下、SRS・OP)のクラス分類のスクリーニングについては、すでに幾つかの提案がある。輸送形態(輸送の可否、最大輸送量、包装形態等)を決定する「危険等級」のスクリーニング手法の開発は、現時点ではない。「物質の危険性評価の試験方法および判定基準」に従って危険等級性の分類を行う場合、キログラムオーダーの試験検体を必要としている。ファイン化学分野の製品群には、この試験検体量と同レベルが通常の流通規模である。このため、危険性のタイプ評価が実質できないケースがある。
危険等級のグラム以下の試料量でスクリーニングを行える方法を見出す事は、製造業者、荷主および輸送関係者にとって、有意義なものと言える。
4.5.2 調査研究課題の概要
本調査研究の課題を以下に記する。
4.5.2.1 目的
(1)SRS・OPの中で国連番号が存在する物質について、DSCデータを収集し、発熱量・分解速度などから爆轟性、爆燃性、更には熱爆発の有無で分けられている「危険等級B以上」と「危険等級C以下」との相関性を調べると共に当該試験の標準化をも定めることにある。
(2)上記(1)に平行して、選択した物質のガス発生量の理論計算及び知見に基づくデータの収集を行い、危険度タイプ分類の基準策定に供する。
4.5.3 SRS及びOP分類フローチャートのスクリーニング化に関する研究
まず「自己反応性物質の航空輸送に係る安全対策に関する調査報告書」(社団法人 日本化学工業協会H12.3)を参考に調査研究を行い、SRS・OPのスクリーニング手法の確立と判定基準案の策定を14年度の最終目標とした。
上記報告書には、SRS・OPの「危険等級B以上」と「危険等級C以下」を分類できるフローとして、以下の案が提案されている。各評価パラメータについては、後述する。
図1 危険等級の判定基準と判定順
| |
判定パラメータ |
危険等級 |
| 推定ガス発生量 |
DSC発熱パラメータ
Q×PH/(Tp-To) |
| 判定1 |
0.3 L/g以上 |
300以上300未満 |
B以上C以下 |
| 判定2 |
0.3 L/g未満 |
350以上350未満 |
B以上C以下 |
|
4.5.3.1 研究に供した試験試料
試験に供した試料を表1に示す。購入品と日本油脂(株)、東洋合成工業(株)からの提供品、合わせて15点を用いた。
表1 試験に用いた試料
| 試料No. |
試料名 |
|
純度 |
国連No. |
危険等級 |
| 1 |
ベンゾイルパーオキシド |
和光純薬 |
99.5 |
3102 |
B |
| 2 |
t-ブチル パーオキシ ベンゾエイト |
日本油脂 |
99%以上 |
3113 |
C |
| 3 |
2,2-アゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル) |
キシダ化学 |
95% |
3236 |
D |
| 4 |
2,2'-アゾビス(イソブチロニトリル) |
キシダ化学 |
98% |
3234 |
C |
| 5 |
アゾジカルボンアミド |
キシダ化学 |
97% |
3232 |
B |
| 6 |
2,2'-アゾビス(2-メチルブチロニトリル) |
キシダ化学 |
98% |
3236 |
D |
| 7 |
ベンゼンスルホニルヒドラジド |
キシダ化学 |
99%以上 |
3236 |
D |
| 8 |
アゾベンゼン |
キシダ化学 |
99%以上 |
|
|
| 9 |
4-ニトロソフェノール *1 |
Aldrich |
60% |
|
|
| 10 |
1-ジアゾ-2-ナフトール-4-スルホン酸 *2 |
Aldrich |
93% |
|
|
| 11 |
2-ジアゾ-1-ナフトール-5-スルホン酸ナトリウム塩 |
Aldrich |
99%以上 |
3226 |
D |
| 12 |
NAC-4 *3 |
東洋合成 |
99%以上 |
3224 |
C |
| 13 |
NAC-5 *4 |
東洋合成 |
99%以上 |
3224 |
C |
| 14 |
4NT-350 *5 |
東洋合成 |
99%以上 |
3224 |
C |
| 15 |
4NT-38P *6 |
東洋合成 |
99%以上 |
3224 |
C |
|
|
*1 |
純度が100%以上の時には、危険等級Dとなる |
*2 |
類似化合物 2-ジアゾ-1-ナフトール-4-スルホン酸は危険等級D |
*3 |
NAC-4 :2-ジアゾ-1-ナフトール-4-スルホクロライド |
*4 |
NAC-5 :2-ジアゾ-1-ナフトール-5-スルホクロライド |
*5 |
4NT-350:2,3,4,4'-テトラヒドロキシベンゾフェノン(22重量%)と6-ジアゾ-5,6-ジヒドロ-5-オキソ-ナフタレン-1-スルホン酸(78重量%)との(モノ〜テトラ)エステル |
*6 |
4NT-38P:2,3,4,4'-テトラヒドロキシベンゾフェノン(21重量%)と6-ジアゾ-5,6-ジヒドロ-5-オキソ-ナフタレン-1-スルホン酸(79重量%)との(モノ〜テトラ)エステル |
|
4.5.3.2 DSC試験
(1)試験装置の説明
示差走査熱量計(DSC)は、微少試料の吸発熱を定量的に測定する熱分析装置である。
当初開発されたDSCは熱補償型といわれたものであった。これは、熱的に安定な物質(アルミナなど)と試料を同時に一定速度で加熱し、試料の発熱や吸熱により、両者に温度差ΔTが生じると、ΔTが零になるように熱補償回路から基準側または試料側に熱量が供給されるものである。
その後、両者の温度差を一定の補正係数に基づいて積分して試料の吸発熱量を求める「熱流束型DSC」が開発された。
最近では、熱補償型よりもベースラインが安定し、温度検出が正確であるなどの理由から、熱流束型DSCが主流になっている。本試験では、この熱流束型のセイコーインスツルメンツ社製 DSC6200を使用した。
(2)DSC試験条件
測定条件は、試料量1mg、昇温速度10K/min、測定雰囲気は空気、試料容器はステンレス(SUS303)密封セルを用いた。
(3)DSCデータ解析と危険度判定値の算出方法
(1)DSCデータ解析
図2にDSCサーモグラムの例を示す。発熱開始点は、以下の2種類がある。
イ 発熱曲線がベースラインから立ち上がる温度Ta[℃]、
ロ 発熱曲線に対する接線とベースラインの交点の温度To[℃]
イは化学プロセスの危険性評価に使用する。ロは、消防法危険物の5類自己反応性物質式の発熱開始温度T0として利用されている。
Toに関しては、発熱曲線に対する接線は変曲点(加速度DDSC最小値のときの温度)を通る直線でこれとベースラインの交点としている。Ta、Teは測定者の目視で決定、To、Tp、QはDSC装置が保有している解析ソフトを用いて算出する。
(2)危険度判定値の算出方法
DSCを用いた危険度パラメータは、発熱量Q[J/g]、ベースラインからピークトップTpまでの発熱速度差PH[w]、ピークトップTp[k]と発熱開始T0[k]の温度差Tp−T0を用いて算出する。計算式は、以下のようになる。
Q×PH/(Tp−T0)
(4)DSC試験結果
DSCサーモグラム測定例の一部を図3と図4に示す。これらDSC試験結果から判定に必要な発熱パラメータを求めた。その結果を表2に示す。
尚、同表には、国連の危険度等級を記載した。
| (拡大画面:53KB) |
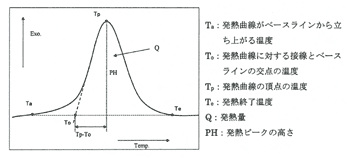 |
図2 DSCサーモグラム例
表2 DSCの発熱パラメータ算出結果
| 試料No. |
試料名 |
純度 % |
Q×PH/
(Tp-To) |
UN危険等級 |
| 1 |
ベンゾイルパーオキシド |
99.5 |
676 |
B |
| 2 |
t-ブチル パーオキシ ベンゾエイト |
>99 |
339 |
C |
| 3 |
2,2-アゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル) |
95 |
123 |
D |
| 4 |
2,2'-アゾビス(イソブチロニトリル) |
98 |
495 |
C |
| 5 |
アゾジカルボンアミド |
97 |
14213 |
B |
| 6 |
2,2'-アゾビス(2-メチルブチロニトリル) |
98 |
799 |
D |
| 7 |
ベンゼンスルホニルヒドラジド |
>99 |
343 |
D |
| 8 |
アゾベンゼン |
>99 |
160 |
|
| 9 |
4-ニトロソフェノール |
60 |
69 |
|
| 10 |
1-ジアゾ-2-ナフトール-4-スルホン酸 |
93 |
1077 |
|
| 11 |
2-ジアゾ-1-ナフトール-5-スルホン酸ナトリウム塩 |
>99 |
498 |
D |
| 12 |
NAC-4 |
>99 |
466 |
C |
| 13 |
NAC-5 |
>99 |
359 |
C |
| 14 |
4NT-350 |
>99 |
194 |
C |
| 15 |
4NT-38P |
>99 |
180 |
C |
|
|