|
予後について(資料P280)
がん患者の心理
告知の有無にかかわらず、医師・看護師または家族の態度や言動、また患者同士の情報交換を通じて、患者は自分が命を脅かすかもしれない重大な疾患に罹っていることを知っている場合が多い。
患者は、「がん」や「死」について十分意識しているが、自分自身の恐怖感や医療者・家族への配慮のため、がんや死について直接的な表現をすることは少ない。
「死ぬ瞬間」 否認・怒り・取引・抑うつ・受容 エリザベス・キューブラー・ロス
死を告知された患者は、どのような心理的変容をたどって死を迎えるか、「5段階説」は、死の過程に一つの輪郭を与えた。しかし全ての人に当てはまるものではない。
5段階説の落とし穴
1. 5段階全てを辿るとは限らないし辿る必要もないがん患者の心理状態はきわめて個別的で、多様である
2. 「怒り」を常に「がん患者の心のプロセス(段階)」と評価するのは誤りである。「怒り」はがんになったことよりも医療者や家族の不適切な態度によって引き起こされることが多い。
3. 「受容」を期待したり押し付けてはいけない。人はそんなに簡単に運命を受容できるものではない
死に行くことは一回限りの人生最大の不幸な出来事である。それはプロセスでは語りきれない複雑な体験である。
5段階ではなく5種類の心理分布(感情の五角形)と考えるほうが適切である。なぜなら順番を飛ばしたり、逆戻りしたり、同時に複数の心的状態が存在したりするから。「否認・怒り・取引・抑うつ・受容」は重大な危機(死別、離婚、リストラなど)に直面した人間が経験する正常な感情体験である。「自分自身の死」以上の重大な危機はない。自分自身の死はあまりに衝撃的であり感情体験も複雑になりやすい。
第一段階:否認・隔離「自分が死ぬわけがない」
否認はふつう一時的な自己防衛であり、まもなく部分的受容にとって代えられる。
否認は必ずしも不幸を増大するものではない。
第二段階:怒り
「もっと悪いことをしている人はたくさんいるのに、もっと年をとった人はいくらでもいるのに、なぜ私が死ななければならないのだ」
怒り、憤り、羨望、恨みなどの感情がスタッフ・家族の対処が難しいほどに、あらゆる方向へ向けられる。
尊敬され、理解され、世話をされ、時間をさいてもらえると患者は怒った要求は減る。→1ステップとして放置してはならない→「怒り」は適切なサポートによって改善できる
コミュニケーション、傾聴(ボランティア)、ピアカウンセリング
第三段階:取引き
「この子が高校を卒業するまで待って下さい」
「交換条件」のようなものであって、神仏や超自然な力に対して何らかのお願いをして約束を結ぶ。
心理学的に見れば、取引は罪責感と関係がある場合が見られる。
患者の心の悩みを探り続け、患者の不合理な恐怖感あるいは罪悪感を解放させるようにする。
第四段階:抑うつ
病状の進行や衰弱とともに、現在までにやり残してきた仕事や、さまざまな後悔などの思いが患者の心に去来し、抑うつ的になる。抑うつには反応抑うつと準備抑うつがある。
反応抑うつとは、原因を探り出し、罪責感や後悔を取り除くことによって軽減する抑うつである。積極的なコミュニケーションアプローチを必要とする。
準備抑うつは、過去の喪失からではなく、差し迫った喪失を思い悩むことから生じる。準備抑うつは反応抑うつとは異なり、ふつう静かな抑うつである。これに対しては言葉よりもスキンシップが有効かもしれない。
第五段階:受容
抑うつも怒りも覚えない段階。嘆きも悲しみもし終えて近づく終焉を見つめることが出来る。
宗教的サポートが受容を促進する可能性がある
この受容を幸福の段階と誤認してはいけない。あたかも“長い旅行の前の最後の休息”のように、受容にはほとんど感情がなくなっている。患者はそっと一人きりにされたいと望む。多くの場合、訪問者は喜ばれず訪問時間も短いことを望む。外部世界への関心は薄れ、テレビは消される。患者とのコミュニケーションは手を握ったり、黙ってすわることが有意義なコミュニケーションであり言葉よりも適切である。
チームケア:これからの課題
アメリカのホスピス HCRI(Hospice care of Rhode Island)/ロードアイランド州
HCRIは、末期患者及び家族に残された日々の質を向上させることを目的とする、総合的なターミナルケアを提供するスペシャリストである。(総合的なターミナルケアの専門家として、患者/家族及びその主治医も含めて支援する組織)
*アメリカでは患者は通常自分の主治医としてのプライマリードクターをもっている。
予後不良と診断された後、ホスピスケアを希望する患者/家族は、その主治医の手から離れることなく、HCRIに登録し、次のようなケアを在宅、また他の施設においても必要に応じて受けることになる。
1. 緩和ケア
1)問題症状のコントロール
2)社会的な問題への援助
3)精神的、霊的な問題への援助
1. 死への準備援助
2. 死別後の家族支援(グリーフケア)
*主治医はホスピス専門の看護師をHCRI専属の緩和ケア専門医のアドバイスを得て、指示を出す事になる。
HCRIの対象となるケース:
末期ガン、末期脳疾患、血液疾患末期、AIDSなど
患者層は乳幼児から高齢者までさまざま
*HCRIにはIN−Patient Center(いわゆる在宅支援病棟)があり、次の場合に利用される。
1. 疼痛を含めた問題症状のコントロールが在宅では困難な場合、緩和ケア”集中治療室”として短期間収容し、コントロールをはかる。
2. 病院から在宅ホスピスヘの移行に祭し、中間地点として、患者を短期間収容し、患者・家族の準備教育期間として利用する。(実際はそのまま死亡することが少なくない。)
3. 在宅で看護している家族が疲労の極限に達したとき家族に休息を提供する目的で利用される。
4. 週末の日々は在宅で過ごしても、死の瞬間は、家で迎えたくない場合、臨終の場として利用する。
*ここに滞在中は、HCRI専属の緩和ケア専門医が指示を出す
| (拡大画面:16KB) |
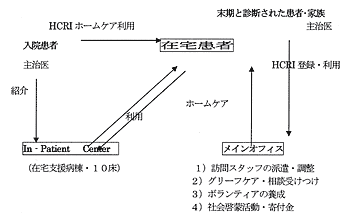 |
スタッフとその働き
HCRIでは末期患者のもつ痛みを総合的に受けとめているため、症状の緩和を図る医療スタッフの他に、社会的、精神的、また霊的なケアをする専門家とボランティアがチームの中に配属されている。患者カルテには、すべてのスタッフがひとつの経過記録に記入する。
週一回すべてのスタッフが集まり、ケース連絡・検討会をもつ。
メディカル・ディレクター(緩和ケア専門医)1人
●患者主治医のためのコンサルタントとして、緩和ケアのアドバイスをする。(往診はまれ)
●In−Patient Centerに収容中の患者の症状緩和をはかる。(毎日診察)
(夜間はOn−Callで対応し、週末は大学から医師、研修医が対応する。)
●専門医としての教育活動
ナース
在宅訪問ナース RN(正看護師)
●メインオフィスからの依頼を受けて患者を訪問し、一般及び緩和ケアを展開する。
●専門的な立場で患者・家族のアセスメントをし、主治医に報告、指示をもらう。必要であれば、主治医にホスピス専門医のアドバイスを得る様示唆する。
●訪問は担当ナースの判断で必要に応じてなされる。症状のコントロールが困難となり、頻回に訪問が必要となった場合、また、家族の意向などに応じて、In−Patientへの収容手続きをする。スタッフの訪問が必要であれば、その手配をする。
●患者・家族に最も近い存在としてホスピスチームのリーダーとなり、週一回の全スタッフによるカンファレンスをすすめる。
●在宅での臨終に立会い、臨終の宣告をする。(通常医師を呼ぶ必要はない)
常勤 5人(月から金まで日勤帯で勤務)平均患者数8−15人/ナース
非常勤 5時以降に日勤で終わらなかった仕事を引き継ぐ。 夜間のOn−Callとして緊急時に対処する。
休日専門ナース
CNA(看護助手)
ホスピスケアのトレーニングを受け、清拭などの身体介護の他、軽い家事援助も行う。
In−Patient Centerのナースの役割(3交代勤務)
●在宅担当のナースから患者を受け入れる。入所時直後用の指示書を使って、とりあえずの緩和ケアをこうじる。
その後に状態を医師に報告し、その患者に必要な指示を得る。入所直後は、通常Break Through Doseとして痛み方に応じて使うモルヒネの指示がだされる。(例 MSO4 20mg/必要時4時間ごと/無効時は30分間隔で5mgずつ増量可)この範囲内でナースは状態に応じてモルヒネの量とタイミングを調節できる。これにより、いちいち医師の指示を待たずに、症状に対処できる。またそれによって、患者の痛みのパターンを把握することができる。そのデータから、MSコンチンなど、ベースとして投与されるモルヒネの量が算出される。この手順で持続注入薬の開始、調節は、在宅ではなく、ここで行われる。もっとも良いコントロールができたところで、帰宅する。死が近い場合は、本人・家族の意向を確認する。また死後の具体的な準備について話をすすめておく。死への具体的な兆候などの家族指導。
●疲れている家族がひとときでも安心して家に帰れる様、状態をよく観察し、臨終直前には再び、患者のもとにいることができるよう、連絡をとる。
●ここでも臨終はナースのみで医師は必ずしも立ち会わない。
●In−Patientでは、患者の身体介護は、RNとCANが協力して行うことが多い。
●原則として、点滴や採血など針をさすような処置は行わない。チューブ栄養も患者・家族が続行を希望しない限りは中止する。経口栄養できない場合もそのまま自然にまかせる。患者はいつでも意思を変えることができる。
ペイシェント・ケア・コーディネーター
在宅とIn−Patientの両方を把握し、患者の入所、及び入所後の様々な問題に対処する。In−Patientの婦長的存在
医療社会福祉士
保険や制度上の社会的なニードに対応する。In−Patientには専門の医療秘書も配属されており、書類の作成などを担当。
チャプレン
●患者の依頼で訪問し、霊的なケアを展開する。患者自身の信仰のグループとの調整をはかる。
●In−Patientでは、病室を定期的に訪ねる。また神父などが、希望者に対して、聖餐式などの儀式を執り行うこともある。
●スタッフやボランティアの霊的なケア
カウンセラー
患者、家族、スタッフの依頼をうけてカウンセリングを担当。
*グリーフケアについて
患者の死後、家族に対して1年間はケアが続けられる。専門のカウンセラーが個人的に、またグループでのサポートを行っている。子供のグリーフケアもある。自由に悲しんで良い場所として提供されている。はげましのカードも定期的に送られる。
ボランティア
ホスピスボランティアとしての訓練をうけ、患者・家族の依頼をうけて、様々な助け手となる。買い物、家事、通院つきそい、話し相手、子供の世話など
III. 考察(HCRIにおける緩和ケアの利点)
1. 患者・家族の最も近くにおり、最新の状態を把握している担当ナースが、決められた範囲内であるが、医師を待たずに薬物を使用したり、増減量できる。これにより、刻々と変わる、状態や訴えに迅速に対処でき、早期に疼痛緩和がはかりやすい。
2. 医師のナースに対する信頼が高く、電話での報告のみで、指示を出している。また臨終に際しても、特別な例を除いて、呼び出されることはないので、医師の数は少なくても多くの患者を在宅で看取る事ができる。
*アメリカでRNの資格をとることは難関である。日本と同様、4年制大学を卒業し、大学院を出る者が多い。知識も相当要求される。(州位試験は2日間)医師と同様に、卒後教育の単位を取らなければ、免許の更新ができない州が多い。特にホスピスケアでは、ナースが担当者として、責任をおう部分が大きいが、そのぶん法的な責任も重い。ミスに対しては、きびしい法的な刑罰がともなう。それらを覚悟してのトレーニングを大学で、また職場で受けている。
3. 患者・家族の希望によるが、原則として、点滴や各種検査は行わない。そのため在宅に複雑なポンプ等を持ちこむ必要がない。チューブ栄養も希望しない限り、原則として行わないので在宅で看やすい。(末期においては、輸液やチューブ栄養は、分泌液を増すだけで、自然な体の終末を阻害し、かえって苦痛を増すと言われている。)
4. 医師だけでなく、訪問看護師にも夜間や休日専門の交代要員、On−Call体制も整っているので、無理なく24時間体制がとれている。
5. 身体的な疼痛以外の痛み(薬剤の届かない痛み)に対しては社会福祉士、チャプレンやカウンセラーなどの専門家が配属されているため、医療者が多くをかかえこむことがなく、チームとしてより質の高いアプローチができている。
6. In−Patient centerが在宅看護のよき補助として有効に活用されている。
In−Patientでは、症状のコントロールが困難な場合に、専門医のもとで集中的な観察と24時間体制で迅速な対応をしていくことができる。これは在宅ではできないことである。これにより、患者の苦痛をより早く緩和できる。また一人の訪問看護師が一人の患者を頻繁に訪問することがさけられる。また患者家族の休息のためにも有効に活用されている。在宅ホスピスを円滑に運営するにあたって必要不可欠な存在。
7. グリーフケアが充実しているため、死別後の家族のフォローもできている。
|