|
事業完了報告
2002年3月1日
特定非営利活動法人
青少年自立援助センター
理事長工藤定次
日本全国から予定人員の20名を超え、22名の参加を得た。不登校・ひきこもりの青少年に支援の手を差し伸べたいと考える人々が多数存在していることの証明である。
不登校・ひきこもりの青少年に関わる人間にとっての最終目標は一体何であるのか?端的に言えば“自立”“自歩の力をつける”ことである。しかし、この点に関してその指導力を有している人間と機関があまりに少ない。今後とも人材育成が必要である。又、更には“自立”“自歩の力をつける”機関の設置は急務である。
その上に立って、実質的に就労に繋がる道筋を設定する必要がある。青少年自立援助センターは【コミュニティーアンクルプロジェクト】(別紙添付)という顔の見える就労の育て上げシステムを実施中である。地域の事業・産業に携わる人々に若い大人を育成していただいている。
今後とも、青少年自立援助センターはやるべき事を地道に、確実に進めてゆきたいと考えている。
多くの御支援いただいている方々に更なるご支援を賜りますよう、この場を借りて、お願い申し上げます。
読売新聞掲載記事
| (拡大画像:293KB) |
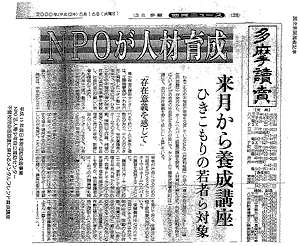 |
はじめに、当講座は、平成13年度日本財団助成金事業〔不登校児自信回復に係わるメンタルフレンド育成講座〕という名称で承認された。しかし、運営の関係上YSC独自に通称名〔HR(ヒューマンリレイション―人間関係)リーダー2級養成講座〕を設定し、これを常用したことをご承知おきください。
当講座を開講するに当り、全国のフリースペース、フリースクール、宿泊型施設などを対象に受講生の募集をした。その後、読売新聞多摩版に記事が掲載され、合計53名の募集要項希望などの問い合わせを受けた。しかし、就業中の方や、主婦の方が受講項目の施設研修・実習の期間を思うように取れないということで、何名かの方から再度問い合わせをいただいたが、当講座の目的が机上の学習以上に研修・実習に重点をおいている旨、説明させていただきやむなく受講を断念された。
最終的に受講課題の小論文を提出していただいた方が、22名。小論文の選考結果、22名の方に全員に受講していただくこととした。内訳は通学生5名。通信制が17名。北は青森、南は鹿児島からの受講である。しかも、その所属もバラエティーに富み、学生、主婦、団体職員、施設経営の方々など。
これほど多くの方に関心を持っていただいたことは、企画運営者として大変心強く、ありがたかった。
講座内容に関しても、YSCの現場で突き当たることの多い専門性の壁(青年期の病理・医薬知識など)を考慮し、この機会に受講生の方々にも学んでいただこうと考えた。研修や実習に比較すれば、ダイレクトに役立つ知識ではないかもしれないが、受講生の皆さんがいずれ現場に立つときがあれば必ず直面する課題であると思う。その時こそ、今回の講座を役立てていただけると確信する。
加えて、講師を快くお引き受けいただいた皆様も大変熱心で、ご多忙の中、資料をそろえていただき、又、遠方よりわざわざお越しいただいた。この場を借りて改めて感謝申し上げたいと思います。
しかし、開講早々企画運営の課題が発生した。通信制の方々の講座受講システムである。当初は資料を送付し、それに基づくレポート提出を考えていたが、それだけでは講座の内容がほとんど把握できない。急遽、講座内容をビデオに収録し、資料と共に送付させていただいた。ところが、ここでも問題が起こった。ビデオの声が聞き取りづらいという運営側の技術不足と、1回の講座が2時間という長い時間であり、通信制の方々にとっては、辛い受講となってしまった。にもかかわらず、皆さん毎回きちんとしたリポートを提出してくださった。ここでも、運営者として・受講生の皆さんに感謝申し上げなければならないと痛感する。提出していただいた、リポートには添削といってはおこがましいが、YSCを続けてきた者の感想を述べさせていただき、返送させていただいた。
先にも述べたが、当講座の主目的は受講生の皆さんに小田原の〔はじめ塾〕富山の〔はぐれ雲〕山形の〔いこいの里〕の協力各施設の研修、YSCの実習・家庭訪問実習を通して現場の状況を学んでもらうことである。各施設の受け入れ態勢と、受講生のスケジュール調整をしてみると、双方にかなりの無理を強いる状況にもなってしまった。各施設の代表者の方々には次世代のスタッフを育成するという目的に御協力をいただいたこと、休暇を利用してとはいえ全国を渡り歩くようなスケジュールをこなしてくださった受講生の方々の熱心さに頭が下がる思いでもある。
とはいえ、受講生の実習・研修記録、各施設のコメントは、正に本物という感があり、貴重な記録でもある。本来ならば講座資料・受講生全員のリポート・実習・研修記録の全てを添付させていただきたいのだが、膨大な量になってしまうことを鑑み、講座資料に関しては割愛(資料を閲覧されたい方はご連絡をいただけば提供できるよう準備しております)、リポートは企画運営側で選択させていただいた。ただし、運営側で手を加えることは一切せず、全て実際に提出された物を使用した。又、使用に際しては受講生の方々からの承諾を得たもののみ使用した。改めてご了承いただきたいと思う。
一年間を掛けて行われた当講座は、大変収穫の多いものであり、企画当初の不安も、運営中の様々な不備も何とか乗り越えた思いでいっぱいである。
これも一重に、この講座にかかわっていただいた多くの方のお蔭であると、感謝申し上げると同時に、心より感謝申し上げます。
この貴重な経験を生かし、この講座を1回で終了することなく、次に繋げて行くべく、準備を開始しようと考えております。その際には又多くの方の御協力、ご支援を賜りたくお願い申し上げます。
担当 井上哲夫
|