|
岩手の漆蝋・・・工藤紘一
一、漆蝋小史
岩手県北地方は国産漆の産地として知られている。それは漆の木が多いということでもある。明治以降は、福井県から出稼ぎに来た漆掻き職人がもたらした、できるだけ多くの液を掻き採るので、そのシーズンが終わると木は死んでしまう「殺し掻き」という掻き方が普及するが、それ以前は「養生掻き」という掻き方をしており、漆液は数年に一度の割りで少しずつ採っていた。それは漆の木になる実をたくさん採るため、すなわち漆蝋の原料確保のためであった。
藩制時代、今の岩手県から青森県東部にかけては盛岡藩の支配を受けるが、その家老日誌である『雑書』(盛岡市中央公民館刊行中)によると、藩には複数の「漆掻奉行」が置かれ、秋になると担当地域内から漆液と漆の実を集めたことが一七世紀半ばの記録に特に多く見られる。正保二(一六四五)年に盛岡藩が秋田藩との境にある沢内通の番所へ出した命令である「沢内通御留物之事」では、御留物として「武具類・くろかね類/へにはな・むらさき根/蝋漆あぶら/綿麻糸付布/無手形人/商売之牛馬/箔椀・同木地/皮類/塩硝・くんろく香」を挙げ、「右先年より御留物候之間、向後にをいても弥改可申候、若わき道かくれ通候ものとらへ上候ハ、為御褒美其物料可被下者也」として、これらを他藩へ勝手に持ち出すことを禁じ、違反者を捕まえたなら褒美を出すとしている。同様の命令は以後も各地の番所にも出されるが、「蝋」が除外されることはなかった。正保三(一六四六)年には「一戸蝋懸藤兵衛」とある。蝋燭を作ることを蝋懸(掛)というので、一七世紀半ばには一戸でこれを職業としていた人物がいたことを示している。
年代ははっきりしないが、盛岡藩の「御領分物産取調書」によれば、福岡通について「蝋 惣村より出/漆 惣村より出/蝋燭 福岡町一戸町」とあって、蝋と漆は二戸地方全域で、蝋燭は福岡町と一戸町で生産されていたことがわかる。
このように盛岡藩内で漆蝋が生産され、藩にとっても貴重な産物の一つであったことはよくわかるのだが、集めた漆の実をどこで、どのように絞って蝋を作り、これを原料にして何を、どれくらい作ったのかなどはまだ解明されていない。幕末の史料には、盛岡城下に住んでいた藩お抱え蝋燭師の名前もあるから、もちろん漆蝋を原料に蝋燭が作られ、城内や武家屋敷での照明として用いられたのであろうが、このほかに祭礼や祈願などの際、藩内の主な社寺への奉納物としても蝋燭は珍重されていた。
明治十(一八七七)年に来日し、大森貝塚の発見者としても有名なアメリカの動物学者エドワード・S・モースは、日本滞在中に各地を旅行しその記録を『日本その日その日』(平凡社、東洋文庫)として残した。彼は明治十一(一八七八)年八月二十日頃に現在の二戸市福岡を通過するが、そのときの印象を次のように書きしるしている。
漆の実
漆掻き(日本うるし掻き技術保存会提供)
蝋じめの図
(E・S・モース著『日本その日その日2』 東洋文庫 平凡社)
胴木 長さ293センチ
(『岩手県北地方の漆蝋』一戸町教育委員会 一部改訂)
| (拡大画面:42KB) |
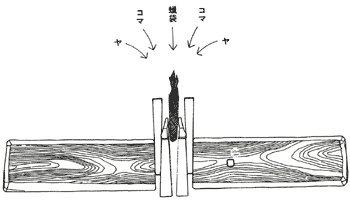 |
蝋袋 全長58センチ 編んでいる部分の長さ38センチ 巾34〜36センチ
(『岩手県北地方の漆蝋』一戸町教育委員会)
一軒の家の前を通った時、木の槌を叩く大きな音が私の注意を引いた。この家の人々は、ぬるでの一種の種子から取得する、植物蝋をつくりつつあった。この蝋で日本人は蝋燭をつくり、また弾薬筒製造のため、米国へ何トンと輸出する。(中略)ここ、北日本でも同国の他の地方と同じように、この蝋をつくる。先ず種子を集め、反槌で粉末にし、それを竈に入れて熱し、竹の小割板でつくった丈夫な袋に入れ、この袋を巨大な材木にある四角い穴の中に置く。次に袋の両側を楔を入れ、二人の男が柄の長い槌を力まかせに振って楔を打ち込んで、袋から液体蝋をしぼり出す。すると蝋は穴の下の桶に流れこむこと、図に示す如くである。
岩手県北地方での本格的な漆蝋生産は大正末期までだったらしい。水力発電所ができて新しい照明の時代になったこと、西洋ローソクの普及が著しかったことなどが衰退の理由である。
|