|
(2)エコドライブのための実施体制
チェック項目
| (拡大画面:3KB) |
 |
解説
会社としてエコドライブを推進するため、エコドライブについての推進責任者を設置します。エコドライブ推進責任者には、運行管理者が任命されるのが一般的です。
チェック項目
| (拡大画面:4KB) |
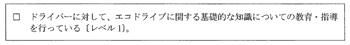 |
解説
エコドライブについては、ドライバーの日常的な実施を促すための教育や指導が必要です。エコドライブへの各取組内容の目的や効果は、次の通りです。
○過度の暖気運転はやらない
夏季3分、冬季5分で充分です。アイドリング15分間で消費する燃料は、約2km走れる300ccになります。
○ゆっくり発進、急発進・急加速はやらない
アクセルはゆっくり踏み込み加速します。急加速1回毎に5〜10ccの燃料が無駄となります。
○経済速度や、定速走行につとめる
一般道路なら40〜50km/hで走行するのが経済的です。また、のろのろ運転やスピードの出し過ぎなど波状走行は10%以上燃費を悪くしますので、定速走行に努めます。
○予知運転による停止・発進回数の抑制
交通状況や次の信号が変るタイミング等を予知することにより、停止・発進回数を抑制します。
○適切な車間距離をとる
適切な車間距離を取ることにより、走行中の加減速を抑制します。
○無駄な空ぶかしはしない
空ぶかし1回で5〜10ccが無駄となります。また、事故発生の原因にもなります。
○登り坂で停車の際は、ブレーキ及びサイドブレーキを使用し、アクセルワークは行わない
燃費の他、ミッションや安全面にも悪い影響を及ぼします。
○不必要なエアコン使用や必要以上の冷却温度使用をやめる
エアコン使用によりエンジンの回転数が高くなるため、結果として燃料の使用量が約10%増加します。エアコンの使用は最小限度に心がけ、こまめに適正な温度に調整することが重要です。
○駐停車中の無駄なアイドリングを止める/休憩中、仮眠、洗車時はエンジンを止める
2時間アイドリングを続けると、2〜3lの燃料が無駄となります。
○トランク内に無駄な荷物を積まない
10kgの不要な荷物を乗せて50km走ると乗用車でガソリン20ccの燃料が無駄になります。乗客のためにもトランク内は、整理整頓します。
○(AT車の場合)走り出したら、アクセルをいったんゆるめる
スピードに合わせた早めのシフトアップができます。走行中の燃費が安定し、燃費10〜20%の差につながります。
○(AT車の場合)走行中は、できるだけ床までアクセルを踏み込まない
アクセルを床まで踏み込みキックダウンさせると、燃費が悪化します。
走行中の燃費が安定し、燃費10〜20%の差につながります。
○(AT車の場合)信号待ち等の停止時にニュートラルにする
停止中に、エンジンにかかる負荷を少なくすることで低燃費につながります。
なお、油圧式のオートマチック車で走行中にニュートラルにすると、エンジンから発生する油圧が不足し、トランスミッションの故障につながります。
○(AT車の場合)オーバードライブ(O.D.)ボタンは通常時入れっぱなしにする
50km/h前後で自動的にオーバードライブとなり、走行燃費は向上します。
○(AT車の場合)平地走行はDレンジのまま、走行する
1.2.レンジは長い坂道等で使用します。低速レンジでは、約20%燃費が悪化します。
○(マニュアル車の場合)早めにシフトアップする
エンジンを高速回転で使うほど窒素酸化物の排出量が増大します。アクセルをいっぱい踏み込んで低速ギアで高回転まで引っ張る運転は避けて、早めにシフトアップすることが大切です。
参考:(社)東京乗用旅客自動車協会「乗務員向けの運転要領」
国土交通省「エコドライブ(10)のおすすめ」
教育・指導の手法としては、朝礼での周知徹底、ポスター掲示による啓発、講習会の実施、始業時や終業時における取組状況の確認と指導などがあります。
チェック項目
| (拡大画面:7KB) |
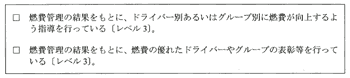 |
解説
エコドライブへの取組が一時的に終わることなく継続するように、ドライバー別あるいはグループ別の燃費管理の結果をもとに、日常の指導や教育に加えて、燃費の悪いドライバーやグループの指導、実技講習会への参加の促進など具体的な指導も必要になります。
また、燃費の優れたドライバーやグループに対して表彰等を行うことにより、従業員の取組意欲を向上させることも必要になります。
○従業員の取組意欲の向上
・表彰制度(営業所別、グループ別、個人別表彰制度)
・人事考課へのエコドライブの取組結果の算入
(3)アイドリングストップの励行
チェック項目
| (拡大画面:3KB) |
 |
解説
アイドリングストップはエコドライブの取組のひとつですが、エコドライブの中でもとくに重要な取組であり、東京都などではアイドリングストップの遵守が条例で義務づけられています。(社)東京乗用旅客自動車協会の資料によれば、15分間のアイドリングで約2km走行できる300ccの燃料を消費するといわれています。仮に1台が毎日15分ずつアイドリングストップを行った場合、1年間で燃料を約100l、燃料費にして約7,000円削減できることになります(LPG価格:70円/lとして算出)。
アイドリングストップの重要性を認識したうえで、エコドライブに関する情報提供・教育の実施などに加え、特に、アイドリングストップの必要性や実施方法について周知している場合を想定しています。
従業員に対する周知方法には、資料の掲示や回覧、点呼・出庫時の確認等があります。
チェック項目
| (拡大画面:4KB) |
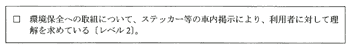 |
解説
環境保全への取組については、従業員の理解や意識を高めることと同様に、利用者に対して理解を求めることが重要です。アイドリングストップの実施により、冷暖房などで利用者に不便をかけることも想定されますので、利用者の理解を求める内容のステッカーなどを車内掲示することにより、取組内容や取組姿勢を伝えることが望まれます。
環境保全への取組について利用者の理解を求める車内掲示用のステッカー等の内容として、次のようなものがあります。
○車内掲示の例
エコドライブ推進について
地球環境を保全するため、
アイドリングストップ(エンジン停止)をいたします。
このため、車内の温度調整が十分でない場合がありますが、
何卒趣旨をご理解いただき、皆様のご協力をお願いいたします。
株式会社△△
チェック項目
| (拡大画面:3KB) |
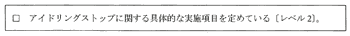 |
解説
タクシーの場合、乗客を乗せている時にこまめなアイドリングストップを行うことが難しいかもしれませんが、それ以外でもアイドリングストップを具体的に行う場合の基準を定め、あらかじめドライバーに周知しておくことが有効です。
基準として、次のような例があります。
・営業所及び車庫停車時
・始業点検時
・休憩、仮眠、洗車時
チェック項目
| (拡大画面:5KB) |
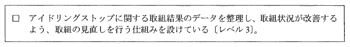 |
解説
アイドリングストップに関する取組状況は、運転日報に設けられたアイドリングストップ実施状況に関する記載等によって把握することが出来ます。
見直しの仕組みとしては、実施状況の把握、評価の手法、ドライバー教育、見直し時期などエコドライブ推進計画に定めておきます。
|