|
5. 廃棄物の適正処理およびリサイクルの推進
(1)取組のポイント
○廃棄物の適正な管理
自動車の整備に伴って生じる廃油、廃タイヤ、廃バッテリーの処理に際しては、不法投棄や、再生可能な部品が捨てられることがないようにする必要があります。そのためには、廃棄物の処理やリサイクルを適切に実施できる事業者に委託することが必要です。
(2)チェック項目の解説と関連資料
(1)廃棄物の適正な管理
チェック項目
| (拡大画面:18KB) |
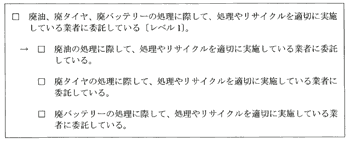 |
解説
このチェックリストは、整備に伴って生じる廃油、廃タイヤ、廃バッテリーを対象にしています。
廃車に伴う廃棄物に関する事項は対象外としています。
廃車に伴うフロン類、エアバック及びシュレッダーダストは、自動車リサイクル法(使用済み自動車の再資源化等に関する法律、平成14年7月12日公布)により、適正に回収され、自動車製造業者等に引き渡されることになります(引取、引渡義務、リサイクル義務等は、法公布後2年6月以内に施行)。
また、自動車搭載のエアコンディショナーのフロン類の回収破壊については、フロン回収破壊法により、機器の廃棄時における適正な回収及び破壊処理の実施が義務づけられています。カーエアコン関連部分は、平成14年10月1日に施行されています。
自社整備を行っている事業者では、整備に伴って生じる廃油等の処理については、直接の排出事業者となるため、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を発行し、適正な管理を行う必要があります。また、整備を委託している場合は、整備に伴って生じる廃油等の処理については、バス事業者が直接の排出事業者とはなりませんが、油等を購入した事業者や整備を依頼している整備事業者を通じて処理する必要があります。
また、自動車に限らず廃棄物処理全般において、マニフェスト制度等にみられるように、法規制は排出者責任を強化する流れになっています。今後の法規制の動向に留意していく必要があります。
関連資料
a. 自動車リサイクル法
自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)は、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務づけることにより、使用済自動車のリサイクル・適正処理を図ることを目的としています。この法律では、次に掲げるものを除くすべての自動車が対象となります(※次に掲げるものを除く:被けん引車、二輪車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、その他政令で定めるもの)。
<関係者の役割>
一般のドライバーやトラック、バス、タクシーなどの事業者は、次の関係者のうち「自動車所有者」として、使用済となった自動車を自動車販売店などの「引取業者」に確実に引き渡すことが義務づけられます。
自動車リサイクルに関連する以下の関係者には次のような役割分担が義務づけられています。
○自動車製造業者、輸入業者
「拡大生産者責任」の考え方に基づき、自らが製造または輸入した自動車が使用済となった場合、その自動車から発生するフロン類、エアバッグおよびシュレッダーダストを引き取り、リサイクル(フロン類については破壊)を適正に行う。
○自動車所有者
使用済となった自動車を引取業者に引き渡す。
○引取業者(都道府県知事の登録制:自動車販売、整備業者等を想定)
自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す。
○フロン類回収業者(都道府県知事の登録制)
フロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡す(自動車製造業者等にフロン類の回収費用を請求できる)。
○解体業者、破砕業者(都道府県知事の許可制)
使用済自動車のリサイクルを訂正に行い、エアバッグ、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す(エアバッグについて、自動車製造業者等に回収費用を請求できる)。
<費用負担方法>
使用済自動車のリサイクル(フロン類の回収・破壊ならびにエアバッグおよびシュレッダーダストのリサイクル)に要する費用については、自動車の所有者がリサイクル料金を負担します。
○リサイクル料金の負担の時点
・制度施行後に販売される自動車:新車販売時
・制度施行時の既販車:最初の車検時まで
○リサイクル料金の設定
・予め各自動車製造業者等が定め、公表
<フロン類の回収・破壊について:自動車リサイクル法とフロン回収破壊法との関係>
使用済自動車のフロン類の回収・破壊については、先に施行されたフロン回収破壊法(カーエアコンのフロン回収については平成14年10月1日より施行)の枠組みの中で先行して実施されていますが、自動車リサイクル法が本格施行された後は、自動車に関わるフロン回収の枠組みは自動車リサイクル法に引き継がれることになります
b. フロン回収破壊法
フロン回収破壊法(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律)は、オゾン層の破壊や地球温暖化を招くフロンを大気中にみだりに放出することを禁止するとともに、機器の廃棄時における適正な回収及び破壊処理の実施等を義務づける法律です。
この法律では、クロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)の3種類の冷媒用フロンが対象となり、これらフロン類が充てんされている自動車搭載のエアコンディショナー(第二種特定製品)は、機器の廃棄時における適正な回収及び破壊処理の実施が義務づけられています。
<関係者の役割>
自動車の所有者やトラック、バス、タクシーなどの事業者は、「第二種特定製品廃棄者」として、カーエアコンを「第二種特定製品引取業者」に確実に引き渡すことが義務づけられています。
○フロンの回収破壊のための経費
フロンの回収破壊の経費は自動車所有者の負担とし、事前に「フロン券」を購入し、廃棄する際に引取り者に「フロン券」を提示することとが求められます。
フロン券は、郵便局及び主要コンビニエンスストアで購入可能です。
A. バスの利用促進 ※路線バス事業者の方のみご記入ください
(1)取組のポイント
○乗りやすさ、使いやすさを考慮したサービスの提供
○効率的な運行ルートの設定
(2)チェック項目の解説
チェック項目
| (拡大画面:22KB) |
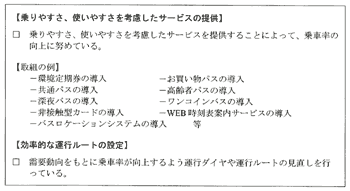 |
解説
バス事業者は、公共交通機関の担い手として、利用者の要望に沿った運行や乗降に便利な定期券や装置の導入等、乗りやすさ使い安さを考慮したサービスの提供により乗車率の向上に努めることが望まれます。同様に、常に、需要動向を踏まえた運行ダイヤや運行ルートの確保も重要です。
バス事業者は、こうした取組を進めることによって、交通混雑の解消や環境保全に貢献することが可能です。
関連資料
a. 環境定期券
土・日・祝日のマイカー利用の抑制と環境保全を目的に、通勤定期を所有している人が、土・日・祝日に家族とともにバスを利用して外出するときに、低廉な料金で区間外でも利用できるサービスです。
b. お買い物パス
商店街などで実施されている買い物ポイントカード(例えば買い物100円につき1ポイント1円の還元となる)制度を、バス利用にも拡大したサービスです。
c. 共通パス
利用客の利便性向上と利用範囲の拡大を目的に、複数の鉄道、バス路線に共通して利用することを可能にした運賃カードです。
d. 高齢者パス
高齢者福祉や中心市街地の活性化を目的として、高齢者を対象にした格安の定期券です。乗車回数や乗車区間には制限を設けない方法や、1乗車につき100円で利用できるようにするなど、サービスの内容は様々です。
e. 深夜バス
深夜(例えば夜23時以降)に出発地(ターミナル駅など)を出るバスのことで、通常料金の倍額(定期券、一日乗車券、敬老パス等では半額を支払う)の運賃や、定額料金により運行されています。
f. ワンコインバス
中心市街地の活性化、観光客及び市民の利便性の向上、交通渋滞の緩和、あるいは過疎地域におけるバス離れを食い止めることなどを目的として、ワンコイン(100円)で乗車できるバスです。
g. 非接触型カード
バス利用客の利便性を向上させることによりバスの利用促進を目的とした非接触ICカードシステムです。かざすだけで運賃が支払えるため、現金支払の煩わしさが無くなり、乗降時間が短縮され定時運行の確保にもつながります。
h. バスロケーションシステム
主要バス停、待合所に運行表示装置を設置し、停留所での到着予測時間や主要目的地までの所要時分を表示するサービスです。
i. WEB時刻表案内サービス
バスロケーションシステムによるバスの運行状況を、インターネットや携帯電話などにより、リアルタイムで検索が出来るサービスです。
|